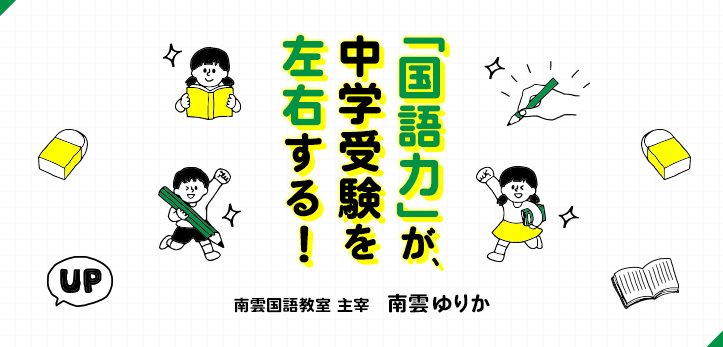
どうすればいい? 塾との上手な付き合い方|「国語力」が、中学受験を左右する!
専門家・プロ
2019年12月23日
水溜 兼一(Playce)
0
本連載では、国語の講師として、中学受験を目指す子どもたちを長年指導している南雲ゆりか先生が、国語力アップにつながるさまざまな方法を紹介します。
年明けから入塾を考えているご家庭も多いと思います。今回は、多くの受験生を指導してきた南雲先生が、塾との良好な関係の築き方や、面談で押さえておきたいポイントなどを紹介します。
先生と直接会うことが、コミュニケーションを築く第一歩
塾とのコミュニケーションは、親が先生と直接会うことから始まります。多くの塾では定期面談を行っているので、入塾後、最初の面談には必ず参加して先生と顔合わせをしておきましょう。
面談では、どんな思いで子どもを塾に入れたのかを話し、お子さんの性格も伝えてください。お子さんのことを知っておくと指導しやすくなりますし、親と会って話をすることで「大切なお子さんを預かっている」という意識も一層強くなります。また、健康上の留意点があればできるだけ伝えて、先生方やスタッフに共有してもらいましょう。
勉強の仕方や志望校選びについて悩みがあれば、
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

