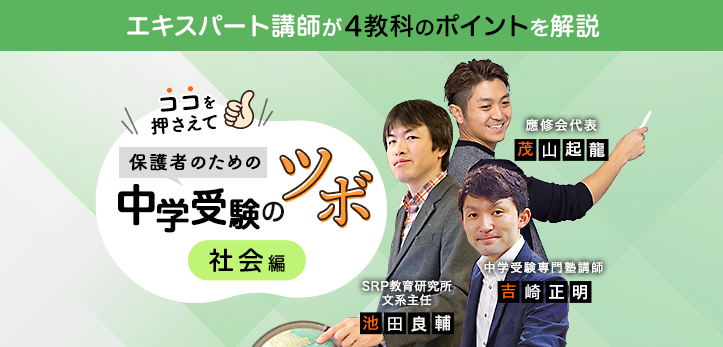
【小5社会/奈良時代】奈良時代を攻略するための3つのポイント ―― 税・仏教・土地|中学受験のツボ[社会編]
こんにちは、吉崎です。
今回のテーマは奈良時代。
710年、元明天皇が都を奈良の平城京に移しました。これが奈良時代のスタートです。
時代の区切りとなる年号は暗記しておくとよいでしょう。
奈良時代ってどんな時代?
710年の出来事の語呂合わせといえば、以下のふたつが有名です。
・なんと立派な平城京
・納豆ネバネバ平城京
ちなみに、私は「平城京は、納豆を買い占めて、フタを開けてひと粒ずつ敷きつめて……」と授業で笑いを狙うほど、ダンゼン「納豆」派です。
飛鳥時代の政治でも仏教を取り入れていましたが、奈良時代の政治では、全力で仏教を取り入れています。もはや「政治=仏教」くらいの勢いで。
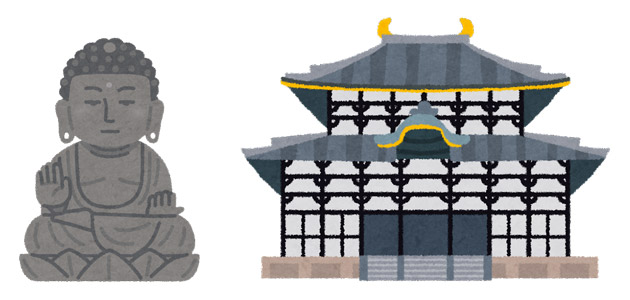
今回は、奈良時代を攻略するためのポイントを3つにまとめました。
1.律令政治の税制度
2.聖武天皇の仏教政治
3.土地の制度を理解する
それでは、順番に見ていきましょう。
1.律令政治の税制度
大宝律令(710年)
中臣鎌足(藤原鎌足)の子である藤原不比等が中心となって編集したルールが、大宝律令です。このルールにしたがう政治を「律令政治」といいます。
今はあたりまえですが、当時はルールにしたがう政治は画期的だったのです。
大宝律令による税制度
大宝律令では、国や地方の政治のしくみ、税に関するしくみが決められていました。税制度については、とくに復習してほしいと思います。
■税
租:収穫したうちの3%の稲
庸:布
調:地方の特産物
覚え方のコツですが、まずは「言えるようにすること」です。
お子さんと「ソヨウチョウ」と繰り返してみてください。
もちろん、漢字で書けるようにすることも重要ですね。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

