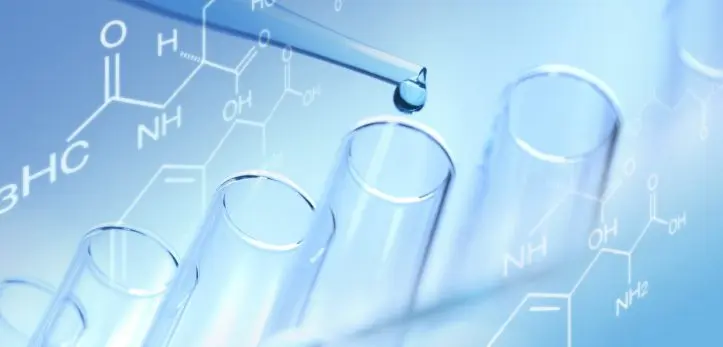
中学受験 理科 2018年入試のトレンドと2019年に向けての勉強法
2018年3月14日に、新5年生・6年生の親を対象とした『2018年入試分析からわかる! 2019年入試に向けてすべきこと』というイベントが開催されました。今回は、このイベントの中で紹介された「理科」ついての中学受験のトレンドと勉強法をまとめてみました。
Contents [hide]
中学受験 理科のトレンドや勉強法とは

『中学受験情報局 かしこい塾の使い方』と『中学受験専門個別指導教室 SS-1』、そして『家庭教師 名門指導会』の3団体の共催で行われた本イベントでは、「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」の主任相談員たちが登壇。2018年入試から見たトレンドや今後の勉強法について紹介しました。
理科のパートでは「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」の辻義夫先生が、2018年の理科入試問題のトレンドや2019年度入試に向けての勉強法を解説しました。
2018年の理科の入試問題のトレンド
辻先生によれば、理科の入試問題には、主に「処理力」を問うものと主に「思考力」を問うもののふたつがあるそうです。有名校では、開成中学校は処理力、麻布中学校が思考力を重視しているといわれています。
実際に2018年度入試で出題された問題を見てみると、開成は合格最低点を取ることは難しくないものの、100%の解答を目指してほしいという意図を感じる、正確な処理力を見る内容。一方、麻布の問題は、普段目にしていることについて深く観察・分析できているかという思考力を見る内容になっていました。
全体的に思考系問題がトレンドに
麻布の理科の問題は上述のように思考力を試す内容でした。「初めての問題にも興味を持って考え、取り組むことができるか」ということが重視されるのは麻布の理科に限ったことではなく、中学受験の全体的な傾向として、こうした「思考系問題」がトレンドになってきているそうです。「学校側としては、合格できる学力を持っているだけでなく、『楽しく理科を学んできた子供』を求めているのではないか」というのが辻先生の考察です。
もちろん学校ごとにその程度は異なるものの、深い思考力を求める問題が出る傾向は今後も続くと予測されます。実際に2018年度入試では、麻布中で出題されたものと同じ問題が桜蔭中でも出題されています。
2019年以降の中学入試に向けてやるべきこと

今後も増えるであろう、思考力が試される問題をクリアするには、親としては勉強面でどのようなアプローチをすればいいのでしょうか。
体験を知識に落とし込むことが重要
辻先生によれば、2019年の入試では「理科の学習内容を身近な例に落とし込んで体験的に理解できているか」がポイントになるとのこと。たとえば、「炭酸水素ナトリウム」ときくと難しく感じますが、「泡のでる入浴剤に使われている物質」と身近なものに置き換えると理解しやすく、子供も興味をもって学びやすくなるというのです。抽象的でわかりにくいことがあれば親が具体的なものに置き換え、興味をひきよせるというサポートをしてみましょう。
わからないことがあれば、今の時代、たいていのことはインターネットで調べることができますし、商品のしくみなどに興味がある場合は企業のお客様センターに問い合わせてみるというのもいいでしょう。自分たちで調べてみるという体験をともなった知識は定着しやすいのです。そこを意識し、子供と一緒に楽しみながら理科への興味を引き出してあげることは親が一番できることではないでしょうか。
理科のアンテナを張り、「なぜ」のスタイルを築こう
理科の入試問題の傾向として、その年や前年の理科分野の時事的なトピックスが取り上げられることがあります。たとえば2018年度の麻布中の入試では、土星の衛星「タイタン」とNASAの探査機「カッシーニ」に関する問題が出ています。これは2017年の大きなトピックでした。
こうしたトピックに関する知識を養うには、日ごろから理科的な視点で世の中の出来事やものごとについてアンテナを広げておくことが何よりも有効です。興味を持って楽しみながらそれができれば一番理想的ですね。
また、普段の生活の中で出合う物事にたいして「なぜ」と問いかけて考えるくせをつけておくこともおすすめです。「お茶と炭酸飲料でペットボトルの形が違うのはなぜだろう」「マンホールが丸いのはなぜだろう」――そんなふうに生活のあらゆるシーンでいろいろなことに興味をもつ習慣ができると、理科のセンスはどんどん磨かれていきます。またその習慣が身につくと、試験問題で初見の問題や話題に出合っても、出会ったことのない問題だからあきらめようとならず、興味をもって取り組み、これまでの知見に基づいて回答にたどりつくこともできるようになるのです。
親としては、日常会話の中で理科に関する話をしたり、子供が「なぜ」と考えたくなるような要素を提示したりすることで、日々の勉強の中に子供の「へえ、そうなんだ!」をどれだけ散りばめられるか、その環境作りが、2019年以降の入試に向けての対策のひとつとなるでしょう。
理科が得意になりたいなら、理科好きになるのがいちばん!
辻先生によれば、理科については、オーソドックスな問題を理解していれば合格最低点を取ることはそこまで難しくないのだそうです。しかし、問題を十分に理解した上で解くには、「理科を好きであること」がポイントとなります。親も、普段から子供との会話で理科の問題に紐付くことを話したり、学習内容を身近なものに落とし込んで興味を持たせたりといった工夫をするのが大事。そうすることで、子供の理科に取り組む姿勢が変わってくるかもしれません。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

