
そろばんの効果はほんとにあるの? 小学生の算数
「算数の力を伸ばすにはそろばんが効果的」と聞いたことのある人が多いと思います。だけどそうは言っても、そろばんはしょせん計算、難しい文章題を解くことにどれだけ繋がるのかわからない、というのが正直なところだと思います。そろばんになぜ効果があるのか。算数の本質に触れながら、そろばんの有用性をみていきましょう。
Contents [hide]
計算ができれば、文章題も解ける!?

「計算ができる」には2つの段階があります。「できる」と「早くできる」の2段階です。「早くできる」ようになれば、算数で大きなアドバンテージを得ることができます。
「できる」と「早くできる」の大きな差
「できる」が計算方法を知っている、時間をかければ解くことができるというレベルです。一方「早くできる」は計算にかかる時間が少ないのはもちろん、「ほぼ無意識に計算をすることができている」状態です。「早い」と聞くと「雑」な印象を受けるかもしれませんが、それは違います。ここでの「早い」は「正確」とほぼ同義です。たとえばPCのタイピング。反復のなかで「身体で覚えた」動きは、正確に繰り返すことができますよね。
「遅い」はミスに繋がる
つまり「早くできる」と試験では、
[1]時間を短縮でき、さらに考える時間を確保できる
[2]無意識にできるので、ミスを減らすことができる
の2つの意味で効果を発揮します。
[1]は当たり前ですよね。時間が早ければ早いほど有利なのは良く理解できると思います。でも実は[2]も非常に重要なのです。
たとえば今私はPCで文章を打っています。タイピングは苦手ではないので、キーボードは見ずに(タイピングには無意識に)文章の内容を考えながら打っています。
これがタイピングの苦手な人だったらどうでしょうか…? タイピングに意識を取られて、文章の内容に集中できませんよね。算数も同じです。計算を無意識にできるようになって初めて、より本質的な内容を考えることが可能になるのです。
そろばんは算数の導入に非常に効果的
このように算数ではとにかく計算力が重要。では計算力を伸ばすのに、なぜそろばんが優れているのでしょうか。
ゲーム感覚で反復練習を有意義に!
反復練習はつらいものです。意義の分からない反復練習が辛いのはもちろん、意義を理解できたとしてもなかなか続けられない……。大人でもそう思いますよね。子供であれば言わずもがな。こういうときは「ゲーム感覚で、楽しんで」が継続のコツです。
そういった意味でそろばんをみると、同じ計算でも読上算、見取算など複数のアプローチがあります。時間制限があったり、身体を動かしたり、ただの計算問題集に比べてゲーム感覚で飽きずに続けられる要素が詰まっていることが大きな魅力です。継続するという効果がえられやすいのです。
計算の正確性を一気に伸ばす、そろばんの「読上算」
前述した「読上算」とは、「願いましては~」以降先生が読み上げる数字を聞き取り、生徒はそろばんを使って計算をする、というものです。
読上算では先生は決められたスピードで読上げます。読み上げられる数字を聞き逃さないように集中する必要があります。
また「生徒が自分のペースで」ではなく、「決められたペースで」計算する力が求められます。
入試では当然「決められた時間内で解く」力が要求されます。「自分のペースで」勉強していては、求められるレベルに到達できないのです。
このように常に緊張感のなかで、計算を繰り返すことで、受験の時間制限にも負けない、「真の計算力」が身についていくのです。
スピード勝負の中学受験の本質
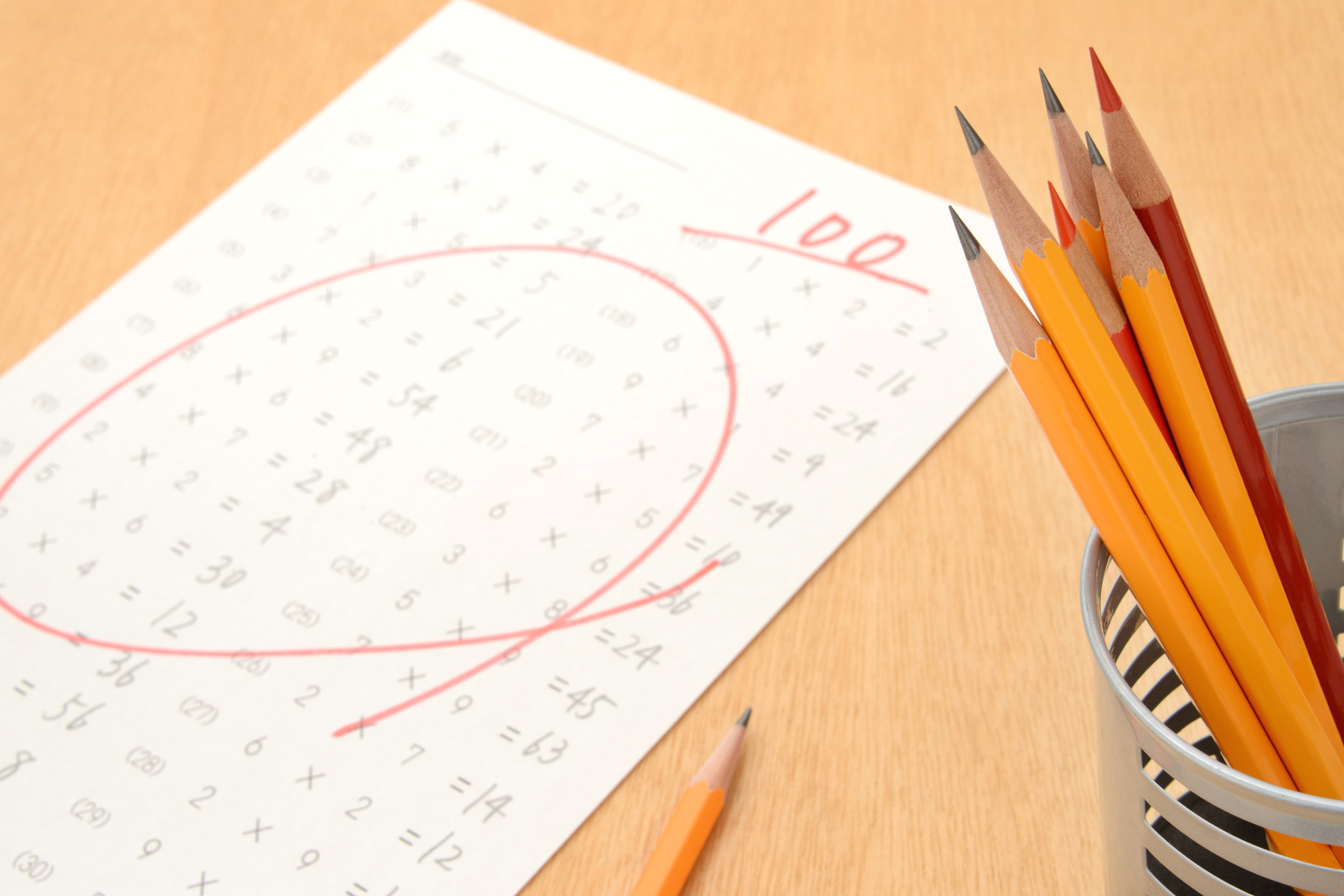
「早くできる」=「正確」であることはご理解いただけたかと思います。そしてこの「正確」こそが、中学受験で求められる大切な力なのです。
倍率が高い=スピード勝負
倍率の高い学校の試験では、時間制限を厳しく作るのが、試験作成者の鉄則です。時間のプレッシャーをかけると、適度に受験生を分散させることができるからです。
多くの人気校の算数の問題はこの理由から、問題量に対して時間制限が短く設定されます。「早くできる」と「できる」の差はそのまま合否に直結するといっても過言ではないのです。
中学受験の導入に効果的
もちろん計算だけで入試を突破できるわけではありません。そういう意味でそろばんは小学校の低学年から開始するのがおすすめです。小学4年生、5年生までに、3級、願わくば2級程度まで取ることができていれば、そこから始まる本格的な受験勉強の大切な素地ができているということができると思います。
計算を「早くできる」ことこそが、算数力の礎
算数を楽しむためには計算力が重要です。そしてそろばんにはその計算力をも楽しく身に着けてくれる仕組みが備わっています。このような「楽しいの連鎖」こそが学力を伸ばす一番の秘訣。自分に合った方法を探すとき、そろばんは検討に値するとても有力な方法であると言えるでしょう。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

