
【武蔵】2018年入試の分析からみる武蔵入試の傾向と対策とは
2018年3月14日に、『中学受験情報局 かしこい塾の使い方』と『中学受験専門個別指導教室 SS-1』、そして『家庭教師 名門指導会』の3団体が「2018年入試分析からわかる! 2019年入試に向けてすべきこと」というイベントを共催しました。今回は、この中で紹介された武蔵中学校(以下「武蔵」)の「算数」と「社会」の傾向についてまとめてみました。
Contents
武蔵 入試算数の傾向と対策は?
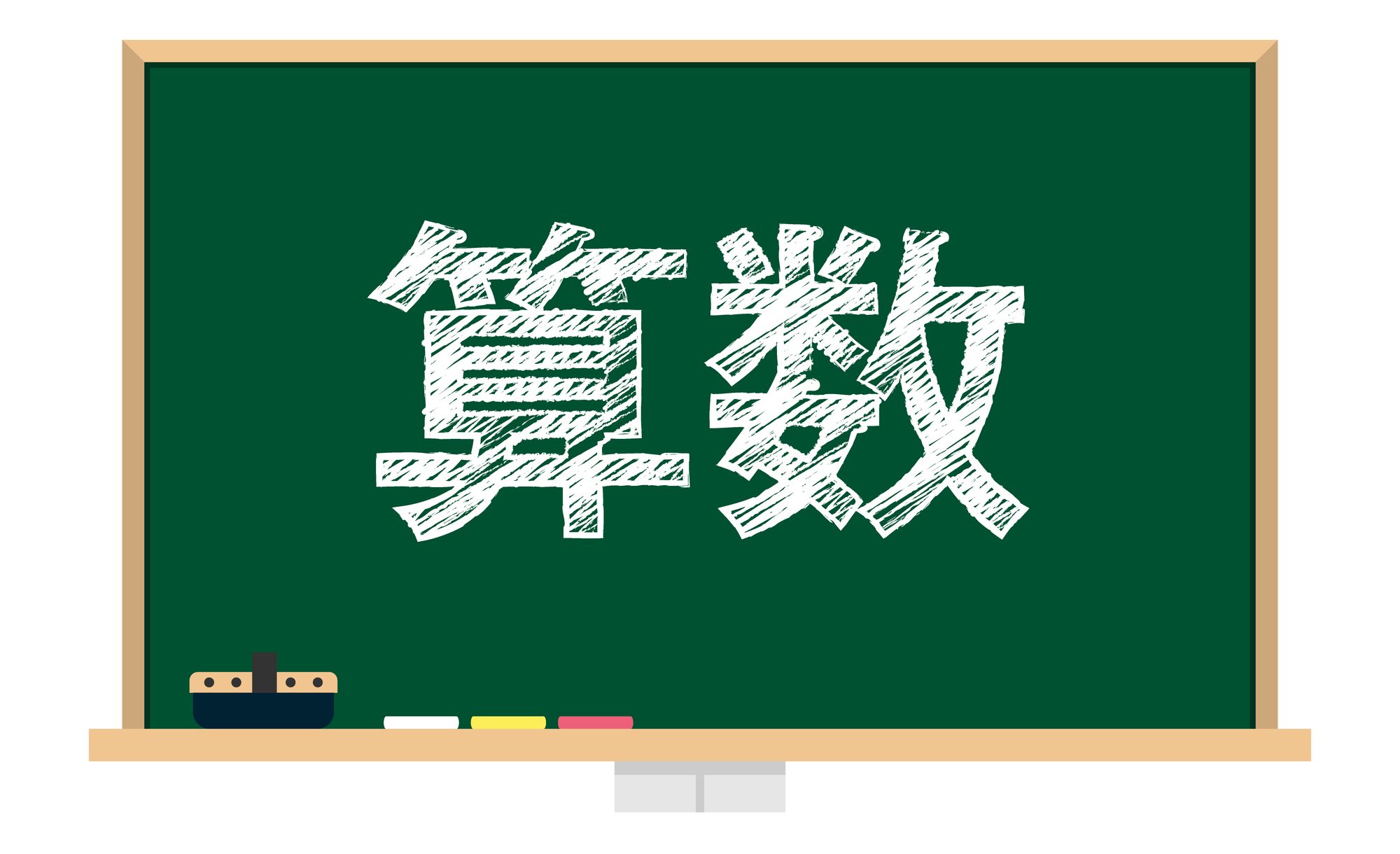
算数の傾向と対策のパートでは、「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」の主任相談員である西村則康先生による解説が行われました。
武蔵の算数問題は「試行錯誤型」
西村先生によると、2018年の武蔵入試の算数問題は「解答に至る流れを自分で構築し、表現する」ことが求められるものでした。つまり「正解を導き出すにはどうすればいいのか」を、自問自答しながら考える「試行錯誤型」の問題だったといえるようです。
もちろん、正しくスピーディーな計算力も必要不可欠ですが、それ以上に表現力が求められる武蔵の算数問題。そのために「正解だけを追い求める学習」では、良い点数を取ることは難しい、と西村先生は分析しています。
2019年の算数入試に向けてやるべきことは?
武蔵の算数問題は、2019年入試でも試行錯誤型の問題が中心になると予測されます。西村先生によると、こうした試行錯誤型問題の対策としては、以下が大切とのこと。
・「この解き方は、どのような問題を解くときに利用できるんだろう」と考える習慣が大切
・答案を見る人の立場に立って、自分の答案を見返してみることが大切
問題に対して試行錯誤するには、覚えた解法を、どういった場面・問題で使えるかを理解してカテゴリー分けすることが重要です。そして試行錯誤して答えを導いた過程を表現することも重要ですから、その力を磨くことも怠ってはいけません。
また「設問の意図をくみ取る共感力」も武蔵の算数問題を解くために忘れてはならない要素だと西村先生は解説しています。「なぜこうした問題なのだろう」という「なぜ?」の姿勢が、表面だけの理解に留まらない、深い思考力につながっていくとのことでした。
武蔵 入試社会の傾向と対策とは

続いて、武蔵の社会の入試問題についてです。社会では、算数の西村先生と同じ「中学受験情報局 かしこい塾の使い方」の専任講師・馬屋原吉博先生が登壇。2018年入試問題から分かるトレンドや、今後の勉強法を解説しました。
ただの暗記にあらず。有名校の問題レベルは非常に高い
馬屋原先生の解説によると、ここ数年の有名校全体の社会の入試問題の傾向としては、ただ暗記して覚えるだけでは合格することが難しいほど高いレベルにあるとのこと。2018年入試もその傾向にあり、武蔵も非常に難易度の高い問題だったと分析しています。
ご存知の方も多いかもしれませんが、武蔵の社会は非常に特徴的で、8割以上が文で答える記述問題です。さらに、世の中の仕組みや常識といった「大人ならだいたいわかる」ことを、あえて小学生に聞くから難しい、という問題を好んで出題してくるのが武蔵の特徴です。
たとえば、2018年の最後の問題は、19世紀末から20世紀前半にかけて銅線の需要が増えた背景と、それによって社会や経済がどのように変化したのかを書かせる問題でした。大人であれば、電気の使用によって世の中がどう変わったか、なんとなくでも書けそうなものですが、さて小6の受験生の何割が答えきれたでしょうか。
こういった世の中のさまざまな事象について語らせる問題で得点するには、答えを考えるための材料となる知識を持っておく必要があります。当然のことながら、こうした知識は一朝一夕で身につくものではありません。では、親としてはどんなサポートができるでしょうか。
武蔵の社会を制するためには、世の中について語るべし
難問である入試社会の記述問題を乗り越えるために大事なこととして、「世の中について語れ」と馬屋原先生はアドバイスしています。先ほどの「ネット炎上」のように、問題のテーマは世の中の出来事。子供が解答するための足掛かりとなる知識を頭に入れておくには、日ごろから家庭で社会問題について話をするなど、情報を知る機会を多く設けてあげるのが重要。
また「過去問題の演習」に多く取り組ませることも大切です。社会の問題は出題パターンが似ていたり、過去問題と同じテーマの問題が出ることもあります。過去問題をやり込むことで、難問をクリアする可能性が高まります。
馬屋原先生によると、子供が武蔵を受験する可能性が出てきた時点で、親は社会の問題にざっと目を通しておくべきだ、とのことでした。
そのうえで、武蔵の入試問題で問われそうな話題が世間を賑わせているようなときは、保護者の方も、「世の中の仕組み」や「常識」について知っていることを積極的に教え、考える機会を設けてあげることが重要とのことでした。
とはいえ、全問が「初見」の問題というわけでもありません。SAPIXのSSや早稲アカのNNといった志望校別の講座に通い、類似問題に取り組み続けていれば、ある程度「見たことがある」と感じる問題も出題されますので、机に向かう勉強も欠かすわけにはいかないようです。
算数と社会の両方で「深い理解と表現力」が重要
武蔵の入試の傾向と対策をみてきました。算数は「『なぜ?』という姿勢で試行錯誤する力」、そして社会は「世の中について語り、さまざまな問題を解くための足がかりを頭に入れておくこと」が大事とのことでした。
また、両教科共に、表面上ではなく深い理解が大切。親としては、子供に対してより深い問いかけをするなどして、考える姿勢作りのサポートをしていきましょう。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

