
適性検査や記述問題にも使える! 作文の上手な書き方
2022年6月02日
天海ハルカ
2
公立中高一貫校の適性検査、国語読解の記述問題、学校の読書感想文など、中学受験を目指す小学生には、作文を書く機会が多くあります。しかし、作文が苦手な子は、1文字も書けなかったり、思いついたまま書き始めて、止まってしまったりします。
作文の書き方をイチから丁寧に勉強できる機会はあまりないため、自分で試行錯誤しなければなりません。そこで今回は、作文が苦手な子でも上手に作文を書けるようになるポイントを、3つに分けて紹介します。
Contents [hide]
- [1]結論を決めておく
- [2]書く前にメモをつくる
- 時間制限がない場合
- 時間制限がある場合
- [3]一文は短く書く
- まとめ
[1]結論を決めておく
漠然とした考えのまま作文を書き始めると、途中で余計な文が増えて、結論にたどり着かないことがあります。論理的に作文をまとめるために、まずは結論を決めましょう。
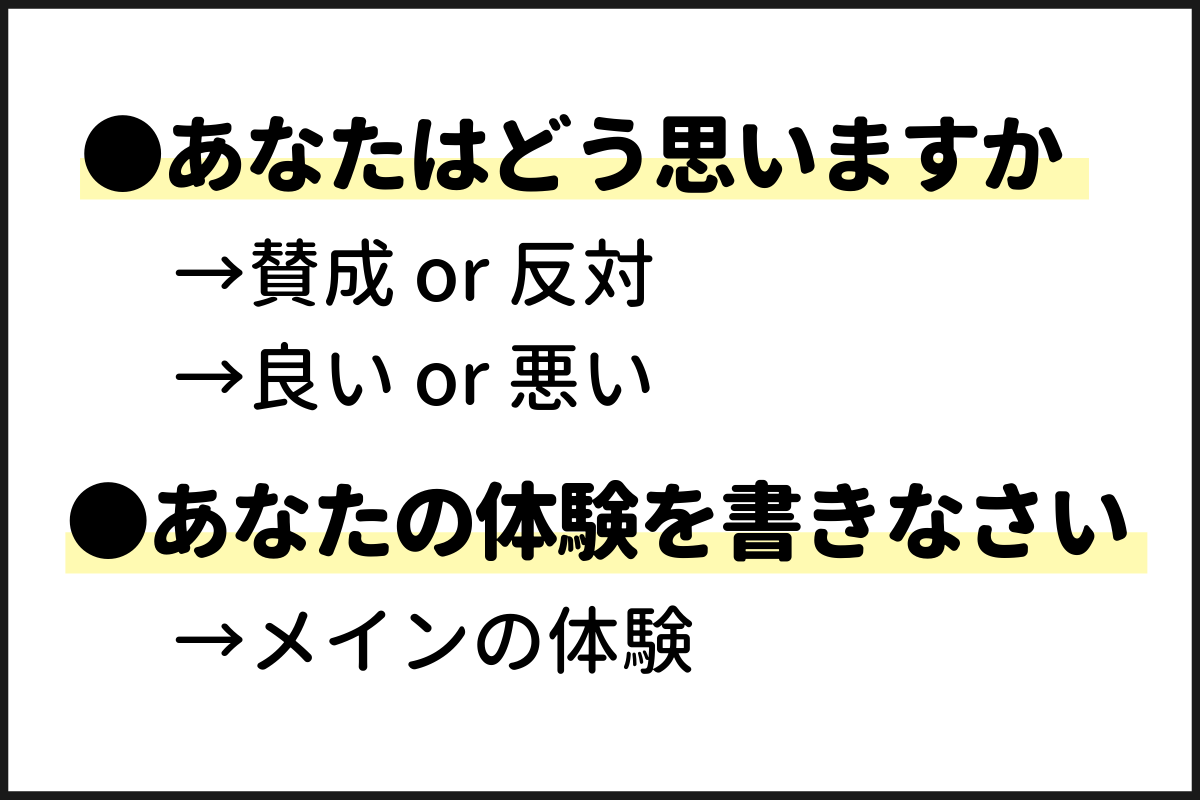
たとえば、「あなたはどう思いますか」について書く場合は、まず「良い/悪い」「賛成/反対」といった結論を決めます。「あなたの体験を書きなさい」という作文なら、メインとなる体験をひとつ選びます。
2
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

