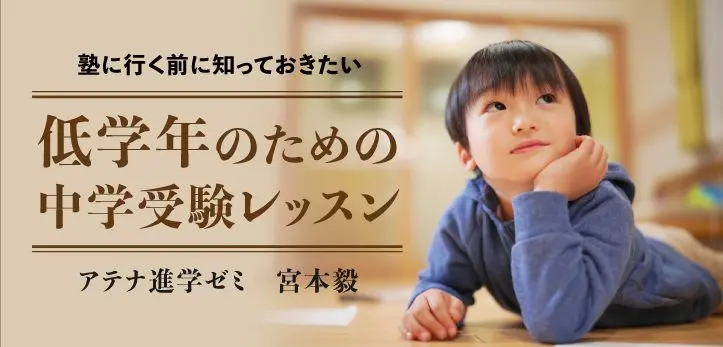
身近な話題から気候や温暖化について考えてみよう|低学年のための中学受験レッスン#41
日本は明確な四季があって、折々の美しい風景が魅力だといわれます。
しかし最近では、地球温暖化の影響により冬が終わったと思ったらあっという間に夏になる気がしませんか? その分、春や秋がとても短くなってしまったと感じる方も多いようです。
中学入試でも気象分野、特に近年の異常気象を取り上げた問題はよく出題されます。
……と、聞くと、すぐに関連書籍やテキストを子どもに買い与えたくなってしまう方も多いかもしれませんが、低学年の保護者の皆さんはまず、毎日の天気予報でも聞くついでに、気候について子どもと話すことから初めていただきたいですね。
気温、湿度、温暖化といった言葉や事象を、子どもが身近なものだと感じられることは、将来の学びに必ず役立つからです。
今回は「天気」「気候」をテーマにお話できればと思います。
Contents [hide]
日本の年平均気温は100年あたり1.28度の割合で上昇中
天気といえば、これからの季節に気になってくるのは、「夏の異常な暑さ」ではないでしょうか。
実際、夏の間(5~9月)の熱中症による救急搬送数は、今から10年前の2014年は約4万件だったのに対し、2023年は約9万1千件と1.8倍にまで増えています。
もちろん猛暑だったか冷夏だったかでその件数は大きく上下しますが、21世紀で冷夏となったのは2003年と2009年だけなので、2014年が飛びぬけて少なかったというわけではありません(ちなみに2009年は約1万3千件でした)。(※1)
5年ほど前までは、ニュース番組やワイドショー番組での夏の猛暑日や酷暑日などのリポートで、キャスターがヘラヘラしながら(いや失礼)「いやー今日も暑くなりそうですねー」と言いつつ公園の噴水で遊ぶ児童の映像を流していたように思います。
実はわたくし現在「気象予報士」の資格を取るべく猛勉強中でして、気象に興味をもつ者のひとりとして、「猛暑」を明るい雰囲気で報道することに、当時から違和感を覚えていました。
最近では少なくともニュース番組ではそのようなシーンは見られなくなりました。それだけメディアも環境問題を身近なものとして捉え、真剣に考えるようになってきたのだろうと思います。
先日も、現役で活躍中の気象予報士と気象キャスターの方々が「気候危機に関する共同声明」を出して、話題になっていましたね。(※2)
こうした実社会における問題意識の変化は、中学入試の作問にも着実に影響を及ぼすため、保護者の皆さんにも敏感になっていただくことが肝要です。
「夏日」「真夏日」「猛暑日」「酷暑日」の使い分け
ところで皆さんは「夏日」「真夏日」「猛暑日」「酷暑日」という言葉を聞いたことがありますか?
まとめると、一日の最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」、30℃以上の日を「真夏日」、25℃以上の日を「夏日」といいます。また、夕方から翌日の朝までの最低気温が25℃以上になる夜のことを「熱帯夜」といいます。(※3)
今の若いお母さんお父さんたちはもしかしたら違った感覚を持ってらっしゃるかもしれませんが、私が子どもの頃(1980~90年代)は気温が30度を超えると「今日は暑いね。熱射病に気をつけてね」などと親に注意されたものです。
夏休みの間に気温が30度を超えることなんてそうそうあることではなかったはずなのに、それが今や「真夏日」なんて当たり前。
2007年には気象庁が「猛暑日」などという言葉をつくって、正式に使われるようにもなりました。
最近は、最高気温40度以上の日は「酷暑日」などと呼ばれています。こちらは気象庁が正式に定義した言葉ではありませんが、日本気象協会が命名したものです。まさに異常事態です。
「平年並みの気温」に惑わされてはいけない
そんななか、2021年3月24日、気象庁は気温や降水量などを評価する基準となる「平年値」を更新しました。
同年5月19日から、1991~2020年の30年間の平均値を使った「新平年値」が使用されています。それまで気象庁は1981~2010年の平年値を使用していたため、10年分スライドしたことになりますね。
新平年値では従来の平年値と比べ、年平均気温が全国的に0.1~0.5度程度高くなります。これがどのような影響を及ぼすかというと、かつては異常気象に分類されていたような酷暑日であっても、平年と比べると差が小さくなってしまうということです。
つまり、危機感が薄れてしまうということにつながります。
事実、この変更により、多くの報道機関では「昔と比べると異常に暑い日」であっても「平年並み」と表現するようになってしまいました。
この暑さが当たり前と感じてしまうような表現に変わったことで、熱中症対策がおざなりになったり、異常気象もどことなく当たり前のように感じてしまうのではないかと危惧しています。
中学受験で出題される気象や環境の問題
SDGsの意識の高まりを受け、中学受験の世界では毎年どこかの中学で気象関係の問題や環境破壊に関する問題が必ず出題されています。
2024年度の早稲田実業 ではこんな問題が出題されました。
温暖化対策として2つの考え方があります。一つは温暖化の原因となる二酸化炭素をこれ以上増やさないというもので、電気自動車や再生可能エネルギーの開発・導入などがあげられます。もう一つは、これ以上二酸化炭素を増やさないための社会的な仕組みを作るというもので、プラスチック製品の利用をやめる取り組みに資金援助することなどがあげられます。
世界中で二酸化炭素を一気に削減することが難しい理由に、発展途上国において二酸化炭素の発生量は多くてもコストの低い石炭が便利なエネルギー源として広く利用されることがあります。そこで二酸化炭素を削減したい発展途上国が、削減技術のある先進国や企業に助けてもらい、二酸化炭素を削減するという取り組みが重要になってきます。
問 下線部のような取り組みは、技術協力する国や企業にとってどのようなメリットがありますか。
(本文に合わせて問題を一部改変しています)
いかがでしょう?塾のテキストだけで勉強している子どもたちにとっては、ちょっと答えるのが難しい感じですよね。というか大人でも答えに窮するような問題です。
もちろんこうした入試問題はトップ校のごく一部でしか出題されませんが、もう少し難度を下げた問題なら、多くの学校で、あらゆる角度から出題されています。
幼少期から気象や環境問題について興味関心を持ち、危機意識を高めていくのが大切かと思います。
親子で身近な「天気」「気象」について話してみよう
ただ、低学年のお子さんにとっては、ピンとこない部分もあると思います。
気温上昇など深刻な話題ばかり考えていますと、親も子も滅入ってしまいますしね。
そこで、もう少しライトにとらえて、地球環境や天気の変化について子どもに興味関心を抱いてもらうのもアリです。
たとえば、天気予報関連のニュースで「雨雲レーダー等の発達により日本人の傘の購入本数が減っている」というおもしろい記事がありました。(※4)
たしかに、私の子どもの頃に比べて天気予報の精度は格段に上がりました。天気予報で「午後、雨が降る」といえばほぼ確実に雨が降ります。
私は天体写真を撮るのが趣味なのですが、今は雲の詳細な動きの予報もネットで調べられますので、本当にありがたい時代となりましたね。
また、実際に目で見て、身体で感じる体験も重要です。
一緒にお風呂に入ったときに湯気を見て、「この白いモヤモヤしたものって何だろうね?」などといった会話から話を広げてみるのもよいでしょう。
湯気の正体は細かい水の粒であることを子どもが理解したら、「じゃあ湯気はどうして上にのぼっていくのかなぁ」と質問してみたり、浴室の天井から落ちる水滴を見ながら「雨ってこうやって降ってくるんだね」なんて話にもつなげられます。
雨の話をした後には「川の水が海にたくさん流れ込んでいるのに、海が満杯になってあふれちゃわないのはなぜかなぁ」と聞いてみたりするとよいでしょう。
こういった、子どもの頃の他愛のない体験や会話が、後々の学習の役に立つものなのです。
【参考資料】
※1 総務省報道資料「令和5年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況 」
※2「気候危機に関する気象予報士・気象キャスター共同声明」(2024年6月5日発表)
※3 国土交通省気象庁HP「よくある質問集」
※4 デイリー新潮「変わる日本の「傘」事情 “平均で4.2本を所有”が減る?意外な立役者とは」
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

