
[7月号/6年生保護者向]夏休みは3タームに分けて計画立て|過去問演習は量より質を重視!|にしむら先生の保護者通信
にしむらです。
いつも私のYouTube動画、「中学受験ナビ-3分メソッド-」をご視聴いただき、ありがとうございます!
そして、日々のお子さんのサポート、おつかれさまです。
さあ、いよいよ、受験生の夏がやってきますね!
そこで、今月は「中学受験ナビ」の会員で、6年生のお子さんをお持ちの方に向けて、夏のスケジュールの立て方と過去問の取り組み方についてお伝えします。
▼動画の再生|画像をタップで再生できます

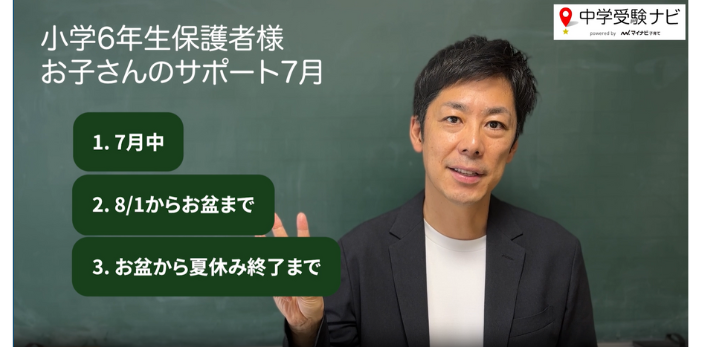
※動画の視聴は会員登録とログインが必要です
夏休み40日間は3タームに分けて計画立て
夏のスケジュールづくりとして私がおすすめするのは「分ける」ことです。
「分ける」こととはどういうことかというと、夏休みの40日間を分けて考えるということです。
子供にとっての40日間って、もう無限に感じるほどの長さですからね。
9割の子は、まだまだ先があると思ってダラダラしているうちに、気づいたら夏休みも終盤……となってしまうんです。
そこで、夏休みは、
- 7月中
- 8/1からお盆まで
- お盆から夏休み終了まで
の3つの期間に分けて、各期間が終わる日に、その期間の振り返りをすると
「この期間のスケジュールは無理があったから、明日からの期間はもっとやることを絞ろう」
というように調整することができます。
スケジュールは柔軟に調整して
立てたスケジュールをうまく活用していくコツは、一度立てたからと言って固定させずに、スケジュールを調整しながら進めていくことです。
スケジュール作成のコツ、その2は、スケジュールを「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分けることです。
せっかく立てたスケジュールがうまくそのとおりに進まないのは、やることを欲張りすぎるからなんですよね。
完璧なスケジュールを作ることは、実は大してむずかしいことではないんです。
むずかしいのは立てたスケジュールを遂行することです。
そこで、スケジュールを「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分けて、「必ずやるべきこと」は「必ずやる」
「できればやること」はできなくてもOK、できれば達成感を味わえます。
立てたスケジュールが失敗に終わるのは、やると決めたことが全然終わらなくて、「もうスケジュールを見るのも嫌」という状態になって、立てたスケジュールが形だけのものになってしまうからです
- スケジュールは、期間を分けて、振り返って調整しながら取り組んでいく
- 「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分ける
夏のスケジュールを立てる際の参考にしてもらえたらと思います。
過去問演習は量より質を優先して
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

