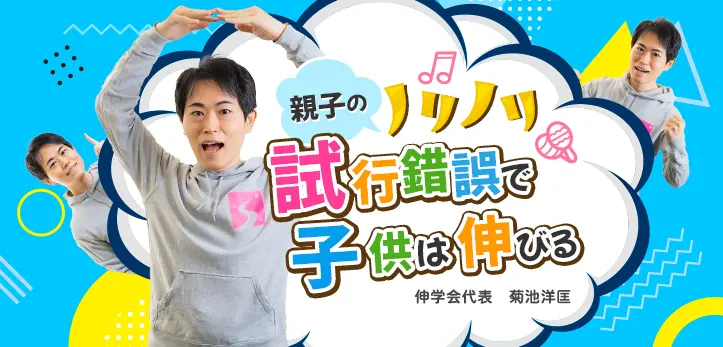
「中受で成績って伸びるの?」に本音で答えます。―― 親子のノリノリ試行錯誤で、子供は伸びる
こんにちは。中学受験専門塾 伸学会代表の菊池です。
中学受験を考えている保護者の方なら、こんな言葉を一度は目にしたことがあるかもしれません。
「中学受験の成績は小4で決まる」
「小5夏までに偏差値が大体固定される」
……え、うちの子はもう手遅れってこと?
と不安になったことがある方も多いんじゃないでしょうか。
たしかに、小4の時点の成績はその子の基礎力や特性を表しているため、それをもとにしてその子の成績がその後どう伸びていくかの予測することは”ある程度”可能です。ただし、それは「未来は変えられない」という意味ではありません。
今回は、
「成績って本当に伸びるの?」
「いつまでに伸ばせばいいの?」
「そもそも“成績が伸びる”ってどういうこと?」
という疑問に、私のこれまでの中学受験指導の経験も踏まえて本音でお答えしていきます。
Contents [hide]
「成績は小4で決まる」って本当?
結論から言えば、これは「本当でもあるし、ウソでもある」と言えます。
というのも、小4時点の偏差値というのは、
- その子の語彙力・計算力・空間認識力などの基礎学力
- 学習習慣(宿題をやる、字を丁寧に書く、読み飛ばさない)
- 家庭のサポート環境
などの「土台」が、数字になって出ていることが多いからです。
だから、小4で成績が良い子は“土台が整っている”ということですから、その先も安定して成績を出しやすいのです。
でも、逆に言えば、小4で成績がイマイチでも、「学習習慣が整っていない」「復習の仕方が分かっていない」「時間の使い方が下手」など、努力や環境へのテコ入れで“改善できる部分”が多い子もたくさんいます。
あたりまえのことですが、小4時点の偏差値は「現在の状態への評価」です。
同じ行動を続けていたら同じ結果が続きますし、実際そうなってしまっているご家庭が多いために「小4の時点で決まってしまっていて変わらない」と言われたりもします。
一方で、日々の学習や家庭環境の改善に取り組んだご家庭は、それに伴って成績が変わっていくことが多いのも事実です。
未来の成績を変えたければ、現状を変えていくための行動を始めましょう。
この改善の取り組みは早ければ早いほど大きな違いを生みます。
だから、早いうちに着手することをお勧めします。
確かに、いつになっても改善はできますし、着手が遅くなったとしても、改善し始めたときから成績にも変化は出ます。
しかし、中学受験は小6の2月(地域によってはそれ以前)と、時期が決まっています。
ですから、着手が遅くなれば、学力の伸び盛りが入試に間に合わず、終わった後にやってくるということもあります。
例えば、私のこれまでの教え子の中には、小6の最後にスイッチが入り成績が上向いた子が、「せっかく伸びてきたのにここで終わりにしたくない」と言って、合格した私立中学校に進学せずに公立中学校へ進学したケースがありました。
彼は小6のときには偏差値50がなかなか取れない子でしたが、中1の1年間でグッと成績を伸ばし、高校受験で早慶にダブル合格を果たしました。
小学生のときとは見違えるほどの成績です。
とてもよく頑張ったことを称えたい気持ちと同時に、スイッチが入るのがもう少し早かったらどうなっただろうか?という気持ちがあるのも事実です。
いつになってももう手遅れとあきらめる必要はありませんが、いつになっても間に合うと先延ばしにしたりはしないようにしてほしいと思います。
成績が“伸びる”子ってどんな子?
では、実際に我が子の成績を伸ばしてあげたいと思ったら、どんなサポートをしていけばよいのでしょうか?
まずは、伸びる子はどんな子なのか、あらためて整理してみましょう。
伸びる子に共通しているのは、次のようなタイプです。
・基礎の積み重ねをサボらない子
→ 例えば、計算や漢字、語彙の復習など「地味な学習」をコツコツこなすことにより、学習の土台となる基礎学力が向上します。また、読書や図形のトレーニングといったものもプラスアルファで行うとさらに効果的です。
・間違い直しをきちんとやる子
→ 解きっぱなしにせず、「何が原因で間違えたか」を振り返れる子は強いです。小4の時点でこれが徹底できている子は少ないので、この当たり前の学習の基本ができるようにするだけで成績がグッと伸びますよ。
・親が“過干渉ではなく伴走型”のサポートをしている
→ ガミガミ言われて育つより、一緒に振り返ってあげる姿勢の方が、子どもも前向きになります。結果として勉強量が増えるので、他の子を追い抜くことにつながります。
・適度に本人に時間的・体力的なゆとりがある
→親が焦っていろいろ詰め込みすぎて、本人がキャパオーバーになってしまっていると、頑張っていても成果につながらないことがあります。親の焦りは子どもに伝染するので、伸びるチャンスすら潰してしまうこともあるので、注意が必要ですよ。
親ができる「成績が伸びる環境づくり」のコツ
お子さんの成績がぐっと伸びるためには、「家庭での学習環境」や「親の関わり方」が大きな影響を持ちます。
例えば、間違い直しが大事だからといって、「ちゃんと間違い直しをしなさい」と子どもを日々叱る家庭は、子どもの成績がどんどん下がります。
そんなやり方では、子どもは勉強を好きにはならないとわかりますよね?
勉強が嫌いになれば、勉強量が減り、成績が下がるのは自然な流れです。
ここでは、指導現場で見てきた“伸びる子”の家庭に共通していた「環境づくり」のポイントを5つご紹介します。
①「間違いを責めず、使う」スタンスを持つ
テストで間違えたとき、つい「なんでこんなミスしたの!」「前もやったでしょ!」と言いたくなるかもしれません。でも、成績が伸びる子の家庭はむしろ逆です。
伸びる子の親の特徴:
- 間違えたとき「ラッキー!今わかって良かったね」と言う
- 間違いノートを一緒にまとめる(解き直しノート)
- 「次に同じ問題が出たら絶対取れるね!」と前向きに励ます
“間違いを財産にする姿勢”が、失敗を怖がらないメンタルを育てます。
②「わかる!」より「できる!」を重視した声かけ
多くの親御さんが「ちゃんと分かってる?」「説明できる?」と確認したくなる気持ちはとても分かります。が、大切なのは「理解したつもり」で終わらせず、「実際にできる」までやりきること。
声かけの例:
×「さっきやったとこ、わかった?」
○「じゃあ、似た問題やってみようか」「この問題、前より早く解けたね!」
「定着の確認」を親がナビゲートしてあげるだけで、アウトプット力がぐんと育ちます。
③「小さな成功体験」を積ませる工夫をする
成績が伸びるかどうかは、単に「勉強時間」では測れません。むしろ、「できた!」という感覚の積み重ねが、子どものやる気を引き出し、成長スピードを加速させます。
成功体験の例:
- 苦手単元で正答率が上がったときに褒める
- 漢字テストや計算練習を繰り返し、満点が取れたらご褒美シール
- 過去より早く問題が解けたら「成長したね!」と伝える
「他の子よりできている(良い偏差値)」ではなく「以前の自分よりできている」を実感させることがポイントです。
④「勉強することが“当たり前”の空気感」をつくる
家庭の中に「自然と勉強するムード」があると、子どもは努力を苦にしません。
例えば:
- 親も一緒に読書したり、資格試験の勉強をする(=勉強してる姿を見せる)
- リビングに「今日の漢字」や「ことわざカレンダー」などを置く
- エンタメテレビよりも学び系YouTubeやドキュメンタリーを観る機会を増やす
「学びって楽しいよね」「知るって面白いよね」という“家庭の文化”が、やる気の土台になります。
⑤「勉強以外の時間」も子どもを肯定してあげる
最後の5つ目に、とても大切なこと。
子どもの自己肯定感は、勉強以外のところで大きく育ちます。
たとえば…
- 料理の手伝いができたら「助かったよ、ありがとう」
- きょうだいに優しくできたら「素敵だよ」
- サッカーで頑張ったら「最後まであきらめなかったね!」
「あなたには価値がある」と伝える時間を持てている子は、勉強でつまずいたときにも立ち直りが早いんです。
中学受験は、子どもが主役であることは間違いありません。
でも、その子どもが「自分の力を信じて努力を続けられるかどうか」は、親が用意する環境の影響がとても大きいです。
- 小さな成功を一緒に喜ぶ
- 間違いや失敗を責めない
- 学びの空気を家庭に作る
- 勉強以外の努力も認める
これらの積み重ねが、成績の“数字”以上に、お子さんの「受験期を乗り越える力」を育ててくれます。
不安な気持ちになる日もあると思いますが、「うちの子はこれから伸びる」と信じて、長い目で見守っていきましょう。
持ち偏差値で志望校を決めるのはいつ?
最後に、多くのご家庭が気にしている「いつ頃志望校を“現実的に”決めるべき?」ということについてもふれておこうと思います。
これから伸びることを信じつつも、一方では冷静に伸びなかった場合のことも考えておく必要があります。
一般的に、小6の夏〜秋ごろが志望校を絞り込まなければいけません。
なぜなら、夏以降の勉強は過去問演習や志望校対策が重要になるので、志望校が決まっていないと学習に支障が出るからです。
もし絞り切れないようでしたら、過去問演習をしながら「この学校の出題形式ならいけそう」「こっちはちょっと厳しいかも」といった情報をもとに、相性の良さそうな学校に絞り込んでいくと良いでしょう。
過去問をやって手も足も出なさそうなレベルであれば、その学校からは撤退して方向転換という判断も妥当だと思います。
ただし、小6の夏まではどんな目標を持っても良いということでもありません。
目標が「非現実的」と感じれば、子ども本人にやる気が起こりにくいものです。
その結果、口では「〇〇中学校に行きたい」と言いながら、行動はまるで伴わないといった状態に陥りがちです。
ですから、いつの時点であっても、子ども本人が「やればできそう」という現実感を持てることは必要です。
小5や小4であったとしても、高すぎる目標にならないようには気を付けてくださいね。
まとめ
「成績は伸びますか?」と聞かれたら、私はこう答えます。
「伸びます。ただし、“伸びるための条件”はそろえる必要があります」
中学受験における成績というのは相対評価です。
他の子を追い抜かなければ成績は上がりません。
偏差値アップもクラスアップも、他の子を上回る成長をした時に起こります。
小4や小5の偏差値が“参考になる”のは事実です。
それは、みんな頑張っている中で、人並み以上の頑張りをして、人並み以上の速さで成長し、他の子を追い抜くのは困難なことだから。
他の子と同じペースで成長し、結果として同じくらいの成績(順位)が維持されることが多いのは当然のことです。
でも、他の子を追い抜くのは不可能なことではありません。
地道な学習習慣、復習の徹底、親子の適切な関わり方——
これらを大事にできる家庭は必ず伸びてきます。
SNSの言説に不安になるのではなく、長い目で見た“育ち方”に目を向けてほしいなと、心から思います。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

