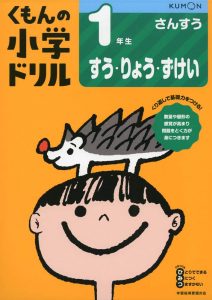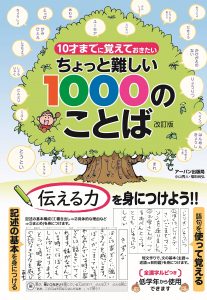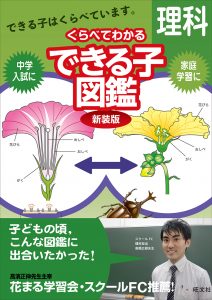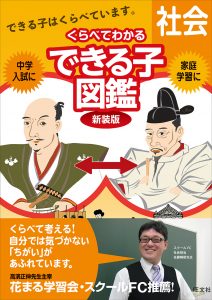低学年でやっておくといいおすすめ教材は?|低学年のための中学受験レッスン#8
中学受験を目指そうと思い立つと、どうしても「低学年から塾に通わせないと間に合わない」とか「小さな頃からガツガツやらせないと周りに置いていかれる」といった焦りが生じがちですよね。
でも落ち着いてください。
正直わたしは、早くから受験勉強を始める方が有利だとはどうしても思えないのです。
かといって、保護者が何も働きかけなければ、子どもたちの持つ大きな可能性を伸ばしてあげることはできないのも事実。
今回の記事では、家庭でできる「中学受験に向けた土台づくり」と、私がおすすめする低学年向け教材をお教えします。
Contents
5年生からのスタートでトップ校合格をつかむ子どもたち
実際、うちの塾に通っている生徒で、いわゆるトップ校に合格していく子たちの中には、中学受験のお勉強を5年生から始めたという生徒が大勢います。
その子たちは、低学年のうちからほかの塾に通っていて、5年生になってからうちの塾に転塾してきたわけではありません。本当に5年生から、中学受験のお勉強を始めた子ばかりです。それなのに、中学受験で成功したのは一体なぜなのでしょうか?
「地頭が良い」だけじゃない!
このように書くと「どうせ地頭がいいんでしょ」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
もちろんそうした要素もまったくゼロではないでしょう。
しかし「地頭」という言葉で片付けてしまっては身もフタもありません。
早くからガツガツやらなくても中学受験を乗り越えることができる子ども達。彼らの成功のポイントはふたつあると思います。
基礎力(=計算力・ことばの力)と一般常識力の充実が子どもの未来を決める
まずは「基礎力が充実している」ということ。次に、「高い常識力」です。
「基礎力」とは、噛み砕いていうと「計算力」と「ことばの力」ですね。
小5からでもグングン伸びていく子と言うのは、このふたつがきちんと身に付いているのです。だから、少し難しい内容のことを学んでも、計算やことばでつまずくことがないため、スイスイ理解していきます。当然成績もあがっていき、最終的にはトップ校に合格できる実力を身に付けられるのです。
1.「計算力」習得におすすめの教材
基礎力のひとつである「計算力」は、どうやって身に付けさせればよいのでしょうか。
おすすめの教材は公文式の計算ドリルです。いろいろありますが、オーソドックスなのは、『くもんの小学ドリル』シリーズ。
『1年生すう・りょう・ずけい (くもんの小学ドリル 算数 数・量・図形 1)』くもん出版(2020/2/14)
最初から難しい計算問題をやらせる必要はありません。
難しすぎますとモチベーションがあがりませんし、途中で嫌になって継続できません。
毎日コツコツ続けられるものがよいでしょう。
かのイチローも言っています。「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道」だと。
継続することが大切なのです!
2.「ことばの力」習得におすすめの教材
次は「ことばの力」についてです。
これは結構大変で、子どもが自分で勝手に「ことばの力」を高めることはなかなか難しく、どうしても親の手助けが必要になってきます。
『10歳までに覚えておきたい1000のことばジュニア改訂版』などはおすすめです。
ただし、親御さんに子どもが書いた短文を添削していただく必要があります。「ことばは親から子へと伝えられるもの」と腹をくくって、ぜひ向き合ってほしいです。
『10歳までに覚えておきたい1000のことばジュニア改訂版』アーバン出版局(2021/1/15)
ほかに、ことわざや慣用句は、マンガ形式の学習本で覚えるのもアリですね。
わたしは親にことわざ・慣用句などが分冊になっているミニ本を買ってもらい、それを常に愛読していました。おかげで国語は常に好成績で、困ったことはありませんでした。
3.「一般常識力」をはぐくむおすすめの教材
早くからガツガツやらなくても成功する子のポイント、ふたつめは「高い常識力」です。
たとえば「生卵を茹でると茹で玉子になって、冷やしても生卵には戻らない」とか「川崎は石油化学コンビナートがたくさんあって昔は大気汚染がひどくてぜんそくが流行した」といった一般常識をたくさん持っている子ほど、塾の授業で習ったことが自分の知識と結びつきやすく、暗記に苦労することはほとんどありません。
一方で、最近の子どもの中には「太陽は東から登って西に沈む」とか「都道府県名・県庁所在地名」といった常識中の常識が頭に入っていない状態の子が多いと感じます。
そうすると塾の授業で習うことをすべてイチから覚えねばならず、大変な苦労を強いられます。
高学年になったときに効率よく理社の学習を進めるためにも、「常識力」は低学年のうちに身につけておきたいですね。
そこでおすすめの本が『くらべてわかるできる子図鑑理科』『くらべてわかるできる子図鑑社会』(旺文社)の2冊。
2023年2月現在は改訂版が最新ですが、3月に新装版が新しく出るようですので、購入する場合はそれを待ってからがいいでしょう。
『くらべてわかるできる子図鑑・社会 新装版』旺文社(2023/03/16)
『くらべてわかるできる子図鑑・社会 新装版』旺文社(2023/03/16)
全ページ、カラーイラストでとても分かりやすく、楽しみながら「常識力」を身につけることができます。
理科社会は、問題を解くよりもまず「興味・関心を育む」ことが大切です。おうちにこうした本がそろえてあれば、ちょっとした合間時間に手に取って、楽しみながら知識を増やすことが可能です。
まとめ
よりレベルの高い学校に合格させるためには、早くから塾通いをさせ、早くから問題を解き、早くから志望校対策をおこなうべきだという風にとらえられがちですが、決してそんなことはありません。
一見遠回りなようでも、むしろ「基礎力」と「常識力」を伸ばしてあげる方が、いざ中学受験の勉強を始めたときに、それがターボチャージャーのように働きます。参考にしてみてください!
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます