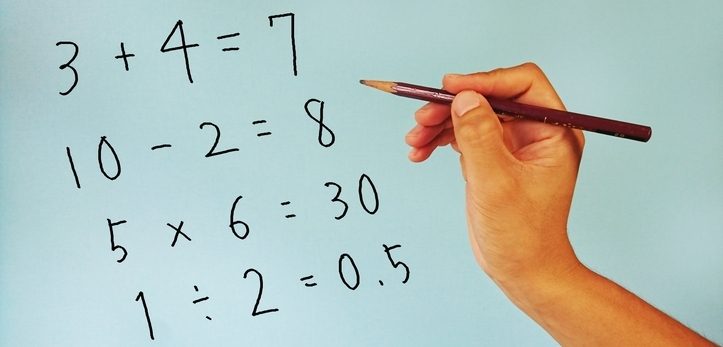
四則計算でチェックすべきポイント5選! 算数の「ケアレスミス」の原因を分析する
算数でなかなか正解できない原因に計算間違いがあります。こうした間違いについて「ケアレスミス」などと軽く考える中学受験生や保護者がいます。しかし、実際は、不注意によってミスが生じたのではなく、四則計算を根本的にわかっていない場合も少なくありません。保護者は子どもの計算過程を一度チェックしてみましょう。
Contents
四則計算に関する用語
保護者は子どもが四則計算に関する用語を正しく覚えているかをチェックしましょう。用語が曖昧だと説明を理解できなくなるので、正しく覚えさせることが大切です。
足し算・引き算・かけ算・割り算を、それぞれ「加法・減法・乗法・除法(加減乗除)」ということがあります。また、足し算・引き算・かけ算・割り算の答えはそれぞれ「和・差・積・商」です。
足し算で7+8=15、29+15=44などのように、ある位の数の和が2けたになったとき、1つ上の位に数が加わることを「くり上がり」といいます。一方、引き算で13-5=8、54-6=48のように、ある位の引かれる数が引く数よりも小さいとき、1つ上の位の数を1小さくして、引かれる数に10を加えることを「くり下がり」といいます。
割り算でA÷B=C…Dのとき、Aは「割られる数」、Bは「割る数」、Cは「商」、Dは「あまり」です。式を変形すれば「割る数×商+あまり=割られる数(B×C+D=A)」が成り立ちます。
A×(B+C)=A×B+A×Cを「分配法則」といいます。これはよく出てくる用語なので、覚えておくとよいでしょう。他にも「交換法則」「結合法則」がありますが、無理に覚えなくても問題ありません。
四則計算でチェックすべきポイント5選
保護者は子どもが書いた途中式などを観察して、以下の5つのことが正しくできているかをチェックしましょう。
1. 計算の順序は正しいか?
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

