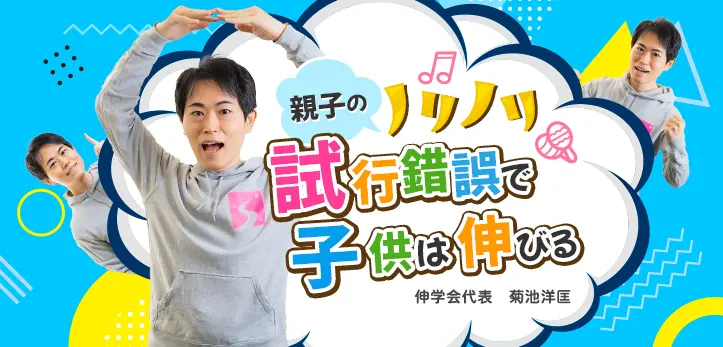
子どもの勉強サポート失敗事例3選―― 親子のノリノリ試行錯誤で、子供は伸びる
こんにちは。中学受験専門塾 伸学会代表の菊池です。
情報化が進んだ昨今、子育てに関する情報も様々なところから入ってきますよね。
中学受験で難関校に合格した親子が、確信をもって語る「成功したのは○○をしたおかげ!」という話はとても魅力的に見えます。
確かにこうした話からは学ぶべきこともあります。
しかし、気を付けてほしいのは、こうした体験談はあくまで「サンプル1」に過ぎないということです。
同じことをした人を100人集めたときに、そのうちの何人が同じように成功したのかという「データ」は、その「体験談」の中にはないのです。
あなたにはぜひ知っておいてほしいことがあります。
それは、世の中にはこれ1つだけやれば成功できるという「必勝法」はありませんが、これ1つやらかしただけで失敗に直結する「地雷」はたくさんあるということです。
例えば、これだけ食べ続ければ健康になるという魔法の食材は無いですが、これを食べただけで身体を壊す(なんなら命の危険さえある)という食材(?)はたくさんありますよね。
勉強でも同じように、これ1つやるだけで成績が上がるとか受験に合格できるとかいうものは無いですが、これ1つやってしまっただけで成績が下がるというものはたくさんあります。
成功するために重要なことは、「必勝法」を追い求めることよりも、むしろ「地雷」を避けることの方です。
そして、「地雷」はときどき不発弾となります。
つまり、致死率の高い毒キノコを食べても生き残る人がいるように、これをするとほとんどの子は成績が下がるという悪いやり方をしても、大丈夫な子がまれにいるのです。
こうしたことは「サンプル1」を見ているだけではわかりません。
ですから、「成功事例は軽々しく鵜呑みにしない」「失敗事例は参考にする」という慎重な姿勢を持つようにしましょう。
ということで、今回の記事では、成功事例以上に学びになる失敗事例を3つ挙げて、失敗の要因を解説します。
これらを参考にして、地雷を上手に避けてくださいね。
Contents [hide]
1.先取り学習で苦手意識を植え付けられたA君のケース
A君は中学受験率の高い教育熱心な地域に住んでいて、通っている小学校はほとんどの児童が中学受験をするようなところでした。
親同士の会話では、習い事・塾通いの情報が飛び交います。
小学校に入る前に公文は○○まで終わらせると良い。
○年生になったら算数単科塾の◆◆に通わせるのが良い。
そんな話が嫌でも耳に入ります。
そして、「○○をすると良い」という話は、徐々に「○○をさせなきゃダメだ」という話に聞こえて来てしまいます。
焦ったA君の両親は、それらの情報を信じて、さまざまな習い事・塾通いをさせました。
私がA君を初めて見たのは、4年生のときでした。
算数の授業を担当したのですが、他塾で先取り学習をしていたため、授業で教えることの多くをすでに知っていました。
そのため4年生の間は比較的良い成績が取れました。
しかし、私はすぐに、「この子は早々に頭打ちになるな」とわかりました。
すごいスピードで進む先取り塾の授業についていくのに必死で、「よくわからないけどとにかく覚える」という勉強スタイルが身に付いてしまっていたのです。
その根底には、算数に対しての苦手意識もありました。
どうしてこういう解き方をするのかなんて、考えても分からない。
そうした無力感を学習してしまい、考えることをあきらめてしまっていました。
そんな姿勢では、成長が遅いのはわかりますよね?
確かに4年生の最初の時点では他の子たちよりもいろいろな問題の解法を知っていて、テストでは良い点を取れるのですが、成長力という点では他の子に完敗でした。
ですから、時間の経過とともにどんどん抜かれていき、5年生になる頃には算数の成績は平均以下になっていました。
このA君のケースで、失敗に終わった根本原因は「苦手意識を持たせてしまったこと」です。
先取り学習によって、同世代の子たちよりもはるかに早くたくさんのことを学び、できるようになっていたにもかかわらず、苦手意識を持ってしまっているというアンバランスさ。
おかしいと感じるのではないでしょうか。
でもこういうケースはA君に限った話ではなく、けっこういます。
先取り塾で他の子との比較にさらされ続けたり、塾やご家庭でたくさん叱られて「自分なんかできない」と思いこまされたり、苦手意識を持たされてしまう要因はいろいろ考えられます。
こうした失敗をしないためには、無理のないペースで学習を進めることです。
そして、できるようになったことを認めて褒めることです。
もっとやらせなきゃ、すごい速さで進む先取り学習のペースにちゃんとついていかせなきゃと追い立てると危険です。
お気をつけください。
2.勉強・受験は嫌なものと刷り込まれたBさんのケース
Bさんはとても熱心にやっている習い事がありました。
中学校・高校に入ってもずっと続けたいと思っています。
そんなBさんに、両親は言いました。
「中高生になったら、いろいろな大会に出てみたいんでしょ?だったら中学受験をして私立の学校にったら、高校受験をしなくて済むから、中学校の間練習に集中できるよ」
そう言われて、だったらやってみようかと中学受験をすることにしたBさん。
しかし、勉強に身が入りません。
なにしろ、高校受験が嫌で中学受験をしているだけで、中学受験がしたいとか、勉強が楽しいとか、前向きな動機が無いのです。
こうした「高校受験はできればしたくないもの」というアンカリングがされてしまうと、中学受験はそれとの比較で「できればやりたくないけれど高校受験よりはマシなもの」という意識を持たされてしまうのですね。
モチベーションが上がらないため、必要最低限の勉強しかせず、成績は当然上がりません。
そんなBさんに対して、ご両親は「やるからにはちゃんと勉強して偏差値を上げてレベルが高い学校に行ってほしい」という期待を押しつけます。
ますます勉強が嫌になり、勉強しなくなるBさん。
成績は徐々に下降していってしまいました。
このBさんのケースの失敗の根本原因は、「受験勉強は嫌なもの」というアンカリングです。
「高校受験をしなくて済む」というのをプラス材料として子どもに伝えた時点で、自らの手で子どもを勉強嫌いに導いてしまっていたということです。
同じように「この子は先生に好かれるタイプじゃないからきっと内申点が取れなくて高校受験は不利」といった考えから、高校受験をしなくて良いように中学受験をさせようというご家庭は少なからずあります。
お子さんにとって有利な土俵で戦わせようという考えは、決して間違いではありません。
しかし、こうした状況で「あなたは高校受験は向いていないから高校受験をしなくて良いように」といった伝え方をしたせいで、Bさんと同じように中学受験に対してもネガティブな印象を持たせてしまい、モチベーションが上がらなくなることがありがちです。
こうした失敗をしないためには、「高校受験をしないで良いように中学受験」とか、「大学受験をしないで良いように大学附属校」といったネガティブな動機づけをしないようにしましょう。
そして、中学受験をして私立に行く魅力に焦点を当てた伝え方をするようにしましょう。
3.毎日厳しく管理され、土日は1日12時間勉強させられたT君の場合
中学受験をする小学生はまだまだ未熟ですから、親御さんのサポートが必要になります。
T君の保護者さんは、とても熱心にサポートしました。
スケジュールを決めて、遊びを厳しく制限し、解いた問題の採点をする。
一般的なご家庭に比べて、徹底的なサポート体制を敷きました。
遊びを制限され、ひたすら勉強をさせられる日々に、徐々にT君はストレスを募らせます。
そして、親子ゲンカも起こるようになりました。
近所の方に通報され、警察が家に来たこともありました。
交番に逃げ込んで、虐待されていると訴えたりもしました。
5年生・6年生と受験勉強が難しくなるにつれて、親子関係は悪くなっていきました。
そこまで徹底して管理をした結果、ご両親はT君を開成中学校に合格させることに成功しました。
そして、受験が終わり、T君は勉強に対してすっかり無気力になりました。
中学校に進学後、勉強は必要最低限しかやらず、成績は底辺の方をさまよいます。
そんなT君に対して、親は良い成績が取れないことを責め、暴言を吐くようになりました。
ますます親子関係が悪化し、T君は親に対して殺意を抱くようになりました。
家に帰りたくなくなり、帰らずに外で夜を明かし、そのまま学校に行くこともたびたびありました。
勉強に対して高3の最後まで無気力だったT君は、浪人することになりました。
浪人中、良い塾の先生と巡り合い、勉強に対しての自発的なやる気を初めて持つことができたT君。
大学受験に向けて真剣に勉強することに決めました。
このとき、大学受験で合格できなかったら自殺しようと決意をしたそうです。
生きるために必死に勉強をしました。
結果、なんとか合格をし、命をつなぐことはできました。
第一志望に受かったときよりも、併願校の最初の合格の方が嬉しかったそうです。
「これで死ななくて済む」という安堵の気持ちが大きかったんだそうです。
この話は、T君自身が私のYouTubeチャンネルに出演して話してくれたので、もし良ければご覧になってみてください。
「勉強」「家庭」が10代を自死に追い込む現実もある
厚生労働省のデータによれば、15~19才の子どもの死因の過半数は自殺です。
自殺の理由は、例えば高校生男子においては、入試に関する悩みは5.2%、その他進路に関する悩み11.9%、学業不振が13.0%と、勉強関係で追い込まれて自死する子が多数です。
また、家庭問題に目を向けると、親子関係の不和による自殺が6.1%、家族からのしつけ・叱責による自殺が3.6%もあります。
10代の若者の自殺は「いじめ」がニュースになることが多いですが、いじめによる自殺は0.4%と実は少数派です。
子どもを自死に追い込んでいるものは、「いじめ」よりも「勉強」と「家庭」の方が圧倒的に多いのです。(※1)
T君も、こうした「自殺をした若者」の1人になっていた可能性が十分にありました。
T君の意思に反する勉強の強要は、勉強に対しての無気力と、自殺への決意に繋がりました。
中学受験の結果としては、開成中学校に合格してハッピーエンドに見えますが、その代償はとても大きかったのではないかと思います。
T君は、まさに最初の方でお話しした、「地雷」を踏んでも「不発」となったケースといえます。
過酷な教育虐待を受けながら、中学受験を完走し、開成に合格することができました。
もし他のご家庭が同じことをしたら、十中八九は途中で潰れます。
T君の場合も、中学受験が終わった後で後遺症に苦しむことになったので、不発とは言えないのかもしれませんが。
あなたは、子どもが無気力になること、さらには自殺を考えるほど追い込まれることと引き換えにしてでも、有名難関中学校に進学することには価値があると思いますか?
もしそうではないなと考えるのであれば、こうした強制的な関わり方はしないようにしましょう。
そのかわりに、本人の意思を尊重し、本人が必要とする範囲でサポートをしていく関わり方をしていってあげましょう。
また、この連載のテーマでもありますが、子どもが自分から「もっと成績を上げたい。そのために勉強したい」と思うように、試行錯誤しながら環境を整え、子どもがやる気になる声かけの仕方、見守り方をしていってくださいね。
まとめ
以上、私がこれまでに見てきた子どもの勉強サポートの失敗事例3選でした。
あらためて最後にまとめです。
「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」といわれるように、失敗するときには必ず理由があります。
受験でも、それ以外の何ごとにおいても、成功しようと思ったら、失敗の要因を可能な限り取り除くことが重要です。
今回ご紹介した失敗事例3つを参考にして、あなたのご家庭では地雷を踏まないようにしてくださいね。
それでは。
【参考資料】
※1)厚生労働省「令和4年版自殺対策白書 第3節学生・生徒等の自殺の分析」
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

