
大正時代【3】社会運動の高まり ―― イメージで覚える中学受験歴史
大正時代は15年と短い時代ですが、さまざまな出来事が起こり、“中身”が詰まった時代でもあります。世界的にみると第一次世界大戦があったことはもちろん、それ以外にも国民がさまざまな権利を主張したり、政党内閣ができたりと、日本国内の動きも活発でした。
Contents [hide]
- 大正時代後半 ―― 国内の出来事が中心
- 護憲運動
- 第一次護憲運動
- 第二次護憲運動
- 普通選挙法と治安維持法
- 普通選挙法
- 治安維持法
- 政治以外も押さえておこう
- 関東大震災
- ラジオ放送
- “中身”が詰まった大正時代
大正時代後半 ―― 国内の出来事が中心
大正時代の後半は、国内の出来事を中心に進んでいきます。まずは下の表で、どのようなことが起こったのかをイメージしましょう。
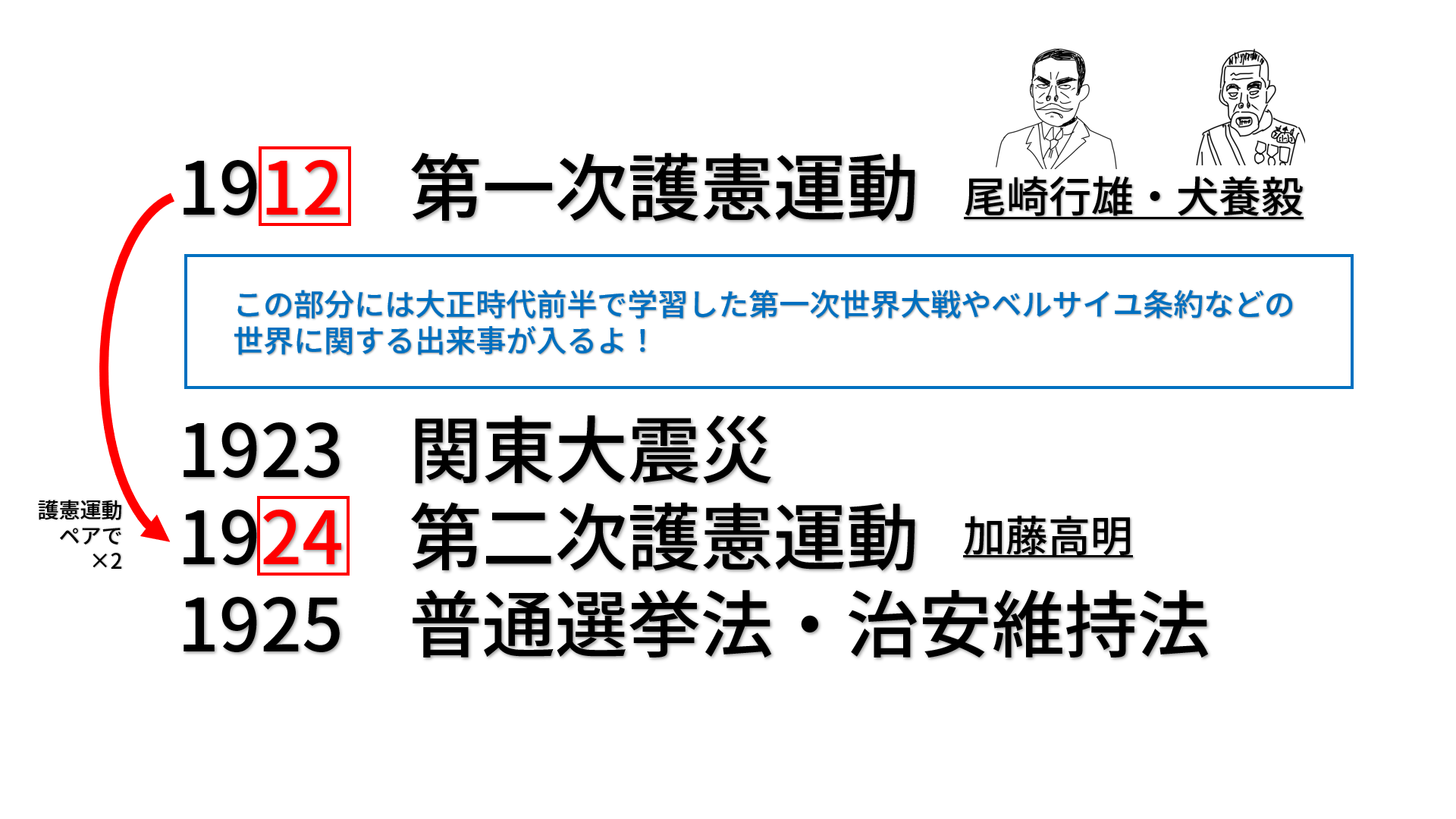
さまざまな社会運動が起こった
大正時代は、ロシア革命や米騒動の影響もあり、さまざまな社会運動が盛んにおこなわれました。これら一連の運動や社会的な思想は「大正デモクラシー」と呼ばれ、民主主義を求める動きが活発化します。
なお、東京帝国大学(現在の東京大学)の教授を務めていた吉野作造が「普通選挙と政党政治を進めるべき」という民本(みんぽん)主義を唱え、多くの人々に支持されたのもこの時代です。
民本主義
民主主義では、主権が「国民」とされていました。一方の民本主義では、主権は「天皇」に置きつつ、さらには民主主義の考えも取り入れよう、という考えが提唱されます。つまり「主権は天皇にあるが、国民の代表者が国民のための政治をすべきだ」という考えが民本主義、ということですね。そのため「普通選挙をして、国民の代表者による政治をしよう」という民主主義とはちょっと違う概念を指します。
大正時代は、性別や労働関係、身分などによる差別をなくそう、という社会運動が一気に増えた時代でもありました。具体的には、次のような運動が起こります。
大正時代の社会運動
- 女性解放運動
- メーデーの開催
- 「日本農民組合」の結成
- 「全国水平社」の結成
女性解放運動
女性解放運動とは、1911年に平塚雷鳥(ひらつからいちょう)と市川房枝(いちかわふさえ)が進めた運動のこと。政治に参加する権利、いわゆる「女性参政権」などを求めました。
平塚雷鳥は「青鞜社(せいとうしゃ)」という団体をつくった女性です。『青鞜』という雑誌を発刊し、「元始、女性は実に太陽であった~~」といった形で女性の権利を主張したことでも知られます。ちなみに青鞜とは、「青い靴下」のこと。18世紀ごろのイギリスで、政治や芸術を議論した女性がはいていた「ブルーストッキング(青い靴下)」にあやかってこの名がつけられたといわれています。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

