
故事成語とは? 中学受験では「読み方・漢字・意味」を覚えよう
中学受験ではたくさんの言葉、語彙を知っていることが重要です。受験するのは小学生ですが、読解問題に出てくるような文章は大人が読むレベルの内容だったりします。そんな語彙の中でも故事成語は苦手な子供が多い分野です。覚えるべき言葉は多くありませんが、見慣れない漢字が並ぶことで苦手意識を持ってしまうのでしょう。
そこで今回は、故事成語とは何か、何をどう覚えたらよいのかという疑問にお答えします。
Contents [hide]
- 故事成語とは
- 故事成語 中学受験で覚えることは?
- 知っておきたい故事成語10
- [中学受験頻出の故事成語1]矛盾(むじゅん)
- [中学受験頻出の故事成語2]蛇足(だそく)
- [中学受験頻出の故事成語3]漁夫の利(ぎょふのり)
- [中学受験頻出の故事成語4]呉越同舟(ごえつどうしゅう)
- [中学受験頻出の故事成語5]五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- [中学受験頻出の故事成語6]杞憂(きゆう)
- [中学受験頻出の故事成語7]背水の陣(はいすいのじん)
- [中学受験頻出の故事成語8]四面楚歌(しめんそか)
- [中学受験頻出の故事成語9]推敲(すいこう)
- [中学受験頻出の故事成語10]蛍雪の功(けいせつのこう)
- まとめ
故事成語とは
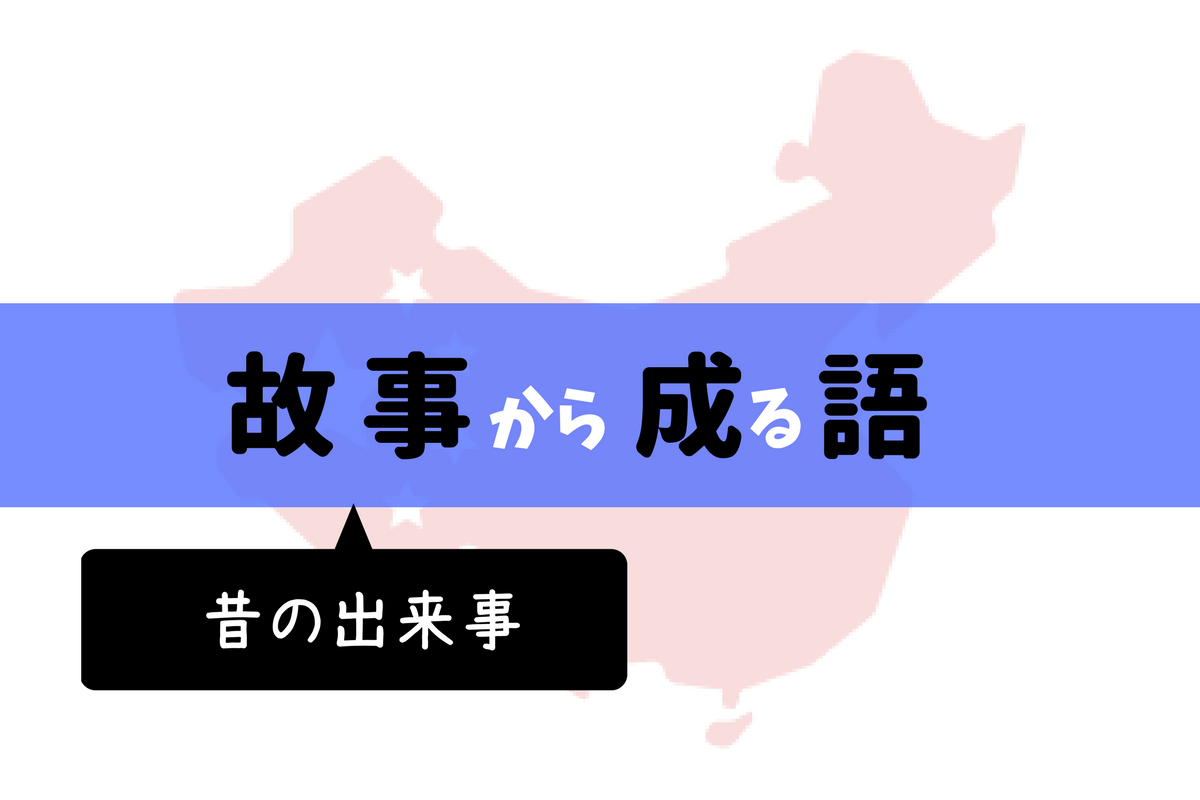
故事成語とは、「故事」から「成」る「語」です。故事は、昔の出来事という意味です。昔の出来事をもとにした言葉や慣用句のことで、多くは中国の故事に由来します。
何千年も昔に起きた中国の話がもとになっているため、見慣れない漢字も多く使われています。そのせいで苦手意識が強くなってしまう子供もいるのです。
故事成語 中学受験で覚えることは?

中学受験の故事成語で覚えるべきことは、「漢字・読み方・意味」の3つです。
漢字を書かせる問題はほとんどありませんが、漢字を知らなければ文章中に出てきても読み取れませんよね。読み方は答えさせられることもあります。
意味は語彙の問題としてだけでなく、文章を理解するためにも知っておかなければいけません。例えば、「矛盾」という故事成語に傍線をひかれて、「どのような点が矛盾しているのか」と答えさせるなど、故事成語を知っている前提で記述解答を求められることもあります。
「由来」を知ると覚えやすくなる
故事成語を覚えるときは「由来」を知っておくと、意味も定着しやすくなります。特に中国の言葉が使われている故事成語は、由来を知らないとなかなか頭に入ってきません。言葉の由来となった事象をこと細かく覚える必要はありませんが、面倒でも一度調べておくと、すっと頭に入ることは多いでしょう。「急がば回れ」ということですね。
知っておきたい故事成語10

数多くある故事成語をすべて覚えることは不可能です。手を広げすぎると、子供は勉強をあきらめてしまいます。
まずは頻出の故事成語をしっかり押さえましょう。中学受験で知っておきたい故事成語を10に絞り、由来も含めて紹介します。
[中学受験頻出の故事成語1]矛盾(むじゅん)
意味:つじつまが合わないこと
由来:「どんな盾も貫く矛(ほこ)」と「どんな矛も通さない盾」を売る商人が、「その矛でその盾を突いたらどうなるか」と客に言われ、返答に困ってしまったという話。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

