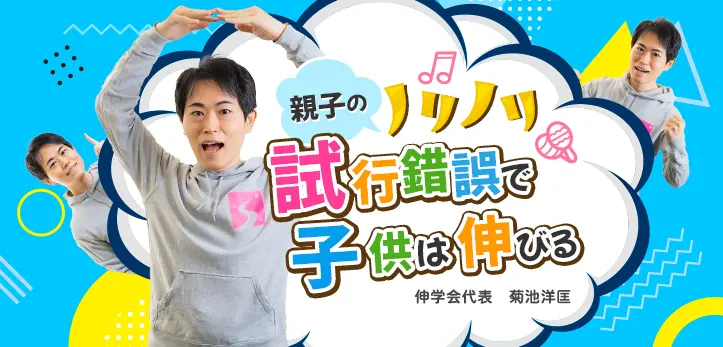
中学受験撤退のタイミングとは? ―― 親子のノリノリ試行錯誤で、子供は伸びる
こんにちは。中学受験専門塾 伸学会代表の菊池です。
もうすぐ夏期講習ですね。
新学年や夏期講習の前後という大きな節目のタイミングでは、中学受験をこのまま続けるか、それとも辞めるか、迷われるご家庭も多いのではないかと思います。
受験勉強は、子どもが「やる!」と言い出してから始めようとすると、始める時期が遅くなりがちで、最初から大きなハンデを背負います。
ですから、子どもの意識がそれほど固まっていない段階で、「中学受験をするかもしれないから、とりあえず受験勉強を始めておこう」という始め方をするご家庭が多いです。
それは正しい選択なのですが、もしいつまで経っても子どものスイッチが入らなかったときには、どこかで撤退をする必要が出てきます。
では、どういう状況になったら撤退を決断したら良いのでしょうか?
考慮した方が良いことは?考慮してはいけないことは?
今回はその判断基準について、私なりの考えをお伝えしようと思います。
もし今現在迷っている状況だったら、参考にしてみてくださいね。
考慮した方が良いこと
1.親のメンタル
まず何よりも考えた方が良いのが、親であるあなた自身とパートナーのメンタルです。
心穏やかに、というのはなかなか難しいものだとは思います。
中学受験をしていなかったとしても、子育てはとても大変なものですよね。
日々イラっとしてしまうことがあるのは当然のことです。
ですが、
- 子どもを見ると、このままで成績は、合格は大丈夫なのかと常に不安に駆られる
- 子どもが遊んでいる姿を見るとイライラする
- 言わない方がいいとわかっていても、自分をコントロールできずに余計なことを言ってしまい、後で反省することが多い
- やってはいけないとわかっていても、よその子とわが子を比べて、焦りや不安を感じることが多い
- 感情的になってしまうことが増え、親子ゲンカ・夫婦ゲンカが頻繁に発生している
といったレベルになっているようでしたら、一度冷静になって、このまま中学受験を続けるかどうか検討してみた方が良いかもしれません。
というのも、親子ゲンカや夫婦ゲンカは、子どもの脳に大きなダメージを与えるからです。
これに関しては、小児神経科医で福井大学子どものこころの発達研究センターの友田明美教授の著書『子どもの脳を傷つける親たち』(NHK出版)に詳しいので、興味があれば読んでみてください。
ケンカというと可愛らしく聞こえますが、子どもへのダメージは「虐待」と同じです。
「虐待」とは体罰や性的虐待だけをイメージする方が多いと思いますが、子どもの脳へのダメージは、暴言などによる精神的虐待でも同様に起こります。
そしてそれは親子ゲンカだけでなく、夫婦ゲンカでも起こります。
中学受験の方針をめぐって両親がケンカをしていると、多くの場合、子どもは自分が原因であると感じて罪悪感を持ちます。
その罪悪感もまたトラウマとなって、子どものこころと脳を蝕んでいきます。
実際に、夫婦ゲンカを見て育った子どもたちは、「IQが低い」「学力が低い」「メンタルの健康状態が悪い」という傾向があるそうです。
我が子が憎くて「虐待」をしているわけではなく、我が子を思ってしたことが、結果的に子どものこころと脳を傷つけてしまうのは、とてももったいないことだし悲しいことですよね。
将来のために学力・学歴を身に付けてほしい。
成功体験を通じて、自信を身に付けてほしい。
努力する経験を通じて、やり抜く力を身に付けてほしい。
そうした中学受験をさせる目的とは逆の結果になってしまいます。
もし親の側のメンタルが大きく乱れてしまうことが頻繁にあるようなら、それを解決するための方法を考えてみましょう。
それでもどうにもならなそうなら、撤退を決めるタイミングかもしれません。
2.子どものモチベーション
中学受験の勉強量は、はっきり言って異常です。
学年が上がるにつれてどんどん大変になってきます。
4年生のうちは、何となく親に言われて通っているという状態でも何とかなることが多いですが、学年が進むにつれて、徐々に勉強が辛くなっていきます。
6年生にもなると、「受験に勝ちたい!そのために努力したい!」という強い意志と、「勉強が楽しい!」という気持ちが無ければ、こなしきれない負荷になります。
子どものモチベーションが低ければ、塾でもご家庭でも、お子さんのモチベーションを高めるために手を尽くすことだろうと思います。
それでも結局やる気にならなかった場合には、選択肢は2つです。
その状態を受け入れてできる範囲でやっていくか、それとも中学受験を撤退するか。
できる範囲でやっていくという選択も、とても良いものだと私は思います。
そもそも子どもの成長にとって大事なのは「ちょっとの背伸び」の繰り返しで、過剰な負荷は子どもを潰すだけです。
異常に勉強する中学受験生の中で、他の子と比べて多いか少ないかを考えるよりも、その子に合った負荷を与えてあげる方が、その子自身の成長のためには良いでしょう。
できる範囲の目標を設定して、それが達成できたら一緒に喜ぶという前向きな関わりをしていってあげてください。
たとえば、順調に学力が伸びた場合に合格できそうな学校だけでなく、お子さんの現在の学力で無理なく合格できそうな学校のなかからも、前向きに目指したい志望校を子どもといっしょに探しておく、といった関わり方は理想的です。
しかし、どうしても人間は周囲と比較してしまいがちです。
比較してはいけない、比較したくないと思っていても、ついつい他人と比較をしてしまいます。
「あの子は御三家を目指すのに私にはとても無理」「何度模試を受けても偏差値が伸びていかない」など、他人との比較によって、本人が劣等感や罪悪感を感じてしまい、勉強に対してますます後ろ向きな気持ちになってしまうようでしたら、中学受験撤退を検討した方が良いかもしれません。
考慮してはいけないこと
これは何と言っても「これまでにかかったコスト」です。
ここまでの塾通いにかかったお金、お子さんのサポートのために割いてきた時間・手間、様々なコストがあったと思います。
「ここでやめたらそれまでのコストが無駄になってしまう!」
そうした思いから、中学受験をやめるにやめられなくなってしまうご家庭は多いです。
これは「サンクコスト効果」とか「コンコルド効果」と呼ばれる人間心理です。
冷静になって考えてみてもらえばわかりますが、「撤退をした方が良いけれど、これまでのコストがもったいなくてやめにくい」という状況は、「撤退した方が良い」状況です。(当たり前のことを言っています)
つまり、「この先続けることはマイナスである」という判断がすでに下されているのです。
続ければマイナスがどんどん拡大していくのですから、マイナスを最小限に抑えるためには、可能な限り早く撤退しなければいけません。
親子・夫婦で撤退について話し合うときには、「サンクコスト効果」について確認をしたうえで、これまでのことではなく、今後のことだけに焦点を絞って話し合うようにしてください。
また、塾と相談する場合にも、「サンクコスト効果」を持ち出されたときは、とくにお気を付けください。
残念ながら受験業界には親心に付け込んで利益を上げようとする悪徳業者も多くいます。
そうした塾は、「ここでやめたらこれまでのお金(あるいは手間)がもったいない」と言って、まさに「サンクコスト効果」を煽ってきたりします。
なんなら、「これまでのコストを無駄にしないために追加受講して成果を出しましょう」とか言って、セールスをしてきたりします。
「成果を出すために追加受講」は悪いことだとは思いません。
お子さんが抱えている問題点や成績アップへのハードルをクリアするために個別指導や家庭教師などが有効である場合はありますし、生徒・保護者の悩みを解決するサービスがあればご案内するのは良いことだと思います。
ただ、「これまでのコストを無駄にしないために」といった人間心理に付け込んだ煽りは、個人的には悪質だなと思っています。
本当にお子さんやあなたのことを思って最善策を考えてくれているか、それとも売上のために生徒を逃さないようにしているだけなのか、注意して聞いてみてくださいね。
まとめ
以上、中学受験を撤退するかどうかの私なりの判断基準でした。
中学受験という目標を持ち前向きに勉強をすれば、どんな子でもそれぞれのペースで成長していくことができます。
私は中学受験をする意義は正にそこにあると思っています。
ですから、親御さんまたはお子さんのメンタル・モチベーションの観点から、子供の成長につながらない状況になっていたら、それは撤退の時期だと考えています。
続けるという決断も、撤退するという決断も、どちらも前向きに決断すれば正解にできますよ。
大事なのは決断した後にどう日々を過ごすかです。
納得のいく決断ができるように応援しています。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

