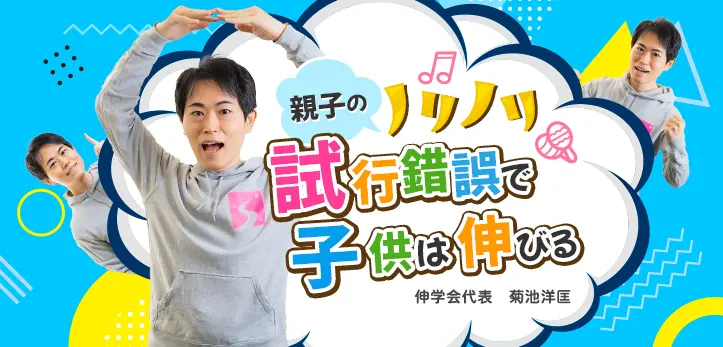
国語ができない子に国語をどう教えるか?―― 親子のノリノリ試行錯誤で、子供は伸びる
こんにちは。中学受験専門塾 伸学会代表の菊池です。
前回は算数力の育て方について書きましたが、続いて今回は国語力の育て方についてお話をしようと思います。
国語も算数と並んで悩む親子が多い教科です。
その大きな原因が、「教え方がわからない」ということ。
親御さん自身は国語が得意だったとしても、それを子どもにどう教えて良いかわからない。
問題の答えはコレだとわかるけれど、なぜそれが答えになるのか子どもに伝えられない。
そんなお悩みがとても多いのです。
かく言う私自身も、国語は中学受験から大学受験にかけてずっと得意科目だったのですが、いざ生徒に教えようと思ったときには、うまく教えられずに苦労をしました。
そして、まさにこの連載のタイトルにあるように、試行錯誤しながら指導してきました。
現在も試行錯誤中です。
今回の記事では、そんな私の最近の取り組みをお伝えしながら、あなたのご家庭でお子さんの国語力を伸ばすためのヒントをお届けしたいと思います。
参考にしてみてください。
Contents [hide]
読解の苦手な子が多いクラスをどう指導する?
私は今年、あるクラスの国語の授業を担当しました。
そのクラスでは、読解が苦手な子がたくさんいました。
約1ヶ月に1度あるカリキュラムテストでは、解答用紙は空欄だらけ。
これは困ったなという状況でした。
試行錯誤その1:読み聞かせ
そこでまず始めたのが、【読み聞かせ】です。
テキストの本文を私が読んで聞かせて、子どもたちが知らなそうな言葉が出てきたら「この言葉の意味知ってる?」と問いかけて確認し、知らなければ説明しました。
そうやって本文の内容を正確に読み取ってから問題を解かせたところ、自分で読ませていたときよりも正解できる子が増えました。
しかし、残念ながら、私が読んでいるのを集中して聞けない子もまだまだいました。
聞いてなさそうだなと思って、「今わたしが読んでいたところを読んでみて」と言うと、案の定答えられないのです。
そういう子が一人二人なら、こまめにアイコンタクトをしたり、質問をしたりして、注意を引きつけ続けることもできるのですが、たくさんいるようだとフォローしきれません。
受動的に聞いているだけだとダメだと判断して、別の方法を模索することにしました。
試行錯誤その2:音読
そこで、次に行ったのが、【音読】です。
生徒に順番に読ませれば、自分が読むときには能動的に頭を使わせることができます。
そして、順番をランダムにすれば、次に指されたときにスムーズに読めるように、ちゃんと集中して聞けるかなと期待しました。
しかし、これもあまりうまくいきませんでした。
指されたときに、「どこからですか?」と聞く子が多数。
結局このやり方も、自分が読む順番のとき以外は受動的になってしまってダメかと判断しました。
試行錯誤その3:読み聞かせ+間違い探しゲーム
その次に試してみたのが、【読み聞かせ】で間違い探しゲームです。
私が本文を読んで聞かせながら、ときどきわざと読み間違いをしました。
それに気づいて「アウト!」と指摘できたら1ポイント、というルールでやってみたのです。
これには食いついてくれる子が多く、けっこう盛り上がりました。
集中力が切れがちだった子たちも、ゲームの勝利を目指して集中して話を聞くようになったのです。
試行錯誤その4:音読+間違い探し
手ごたえを感じたので、今度は誰かが【音読】しているときに、他の子は読み間違いに気付いたら「アウト!」と言うゲームにしてみました。
それだけだと読む子はポイントを稼げないので、読む側は間違えずに読めた行数だけポイントが入るというルールにしました。
これが予想以上に盛り上がり、みんな真剣に音読をするし、他の子が読んでいる時にも集中して能動的に話を聞けるようになりました。
やってみたら、読むのが上手な子が10行20行と読んでしまって順番が回って来ない子がいたりする問題も発生したので、「最大5行まで」という制限をつけることで最終的には落ち着きました。
このあたりのルール設定は、みんなで話し合って決めたことも、みんなが前向きに楽しんでゲームに参加できるようになった理由かなと思います。
成果としては、直近のカリキュラムテストでは自己ベストを更新した子が数名いて、全体的に成績が向上してきました。
国語が苦手な子に教えるポイント2つ
この話を通じてあなたのお伝えしたいことは2点あります。
1.正確な読み方から教えよう
1つ目は、国語の基本は、やはりなんと言っても「正確に読むこと」だということです。
本文にどんなことが書いてあったか理解できていなかったら、問題を解きようがないのです。
「記述の書き方」とか「選択肢の選び方」とかの技術は、まず読めていることが前提です。
読めていない子には、解き方の技術の前に読み方を教えましょう。
2.子どもが正確に読みたくなる方法を考えよう
2つ目は、「子どもが自発的に、正確に読みたくなるやり方」を考えましょうということです。
「ちゃんと読みなさい」と叱ったところで、ちゃんと読めるようにはなりません。
子どもだって悪気があって手抜きをしているわけでは無いのです。
ただ、読むのが苦手だったり、集中力を維持するのが苦手だったりするだけ。
意欲の問題ではなく能力の不足です。
できない事を責められても、つらい気持ちになるだけで、できるようにはなりません。
勉強が嫌いになるだけです。
叱るのではなく、子どもが自分からやりたくなる状況作り・環境づくりを工夫しましょう。
特に効果的な方法が、私がしたように、「遊び」にする事です。
ぜひあなたも遊びにする方法は無いか、試行錯誤してみてくださいね。
国語の成績を伸ばすためのアプローチ
それではあらためて、国語の成績を伸ばすためのアプローチについて解説します。
1.まずは解像度を高めること
これは「算数の苦手克服」であっても「勉強嫌い克服」であっても「学習習慣作り」であっても同じですが、うまくいっていない時にはその原因を分析して、原因に合った解決策を実行することが必要です。
世の中には「算数の成績を上げる方法」も「勉強を好きにさせる方法」も様々な情報があふれていますが、どんな子にも効果的な万能の方法はありません。
例えば、「勉強を好きにさせる方法」として「成功体験をさせてあげること」があります。
勉強嫌いの原因は「できないことによる苦手意識」であることが多いので、そういう子には成功体験をさせてあげることは効果的な方法でしょう。
しかし、勉強が嫌いな理由が、「勉強が得意で、簡単すぎてつまらない」だったり、「できるから、先生はできない子の方にばかり手をかけていて、自分は放置されている」だったりしたら、「成功体験をさせてあげること」という解決策は機能しないですよね。
私は小学校時代まさにそんな感じだったので、「塾に行って、もっと難しい問題にチャレンジする」という解決策で勉強が楽しくなりました。
国語の苦手克服においても、苦手な理由に応じて対処法が変わってきます。
ですから、まずはお子さんが苦手な理由を高い解像度で把握することが最初の一歩になります。
国語が苦手な理由は、大きく分けると「解き方の技術を知らない」か、「文章を読めていない」かのどちらかです。
あなたのお子さんはどちらでしょうか?
まずはここを見極めましょう。
2.問題を解く技術を知らない場合の対処法
同じ「国語が苦手」でも、「4教科の偏差値が60以上ある中で、他の3科目の偏差値は65くらいあるのに国語だけ55前後で足をひっぱっている」のような子と、「4教科の偏差値が50くらいで国語は40前後」という子では、抱えている課題に違いがあります。
前者のような子の場合には、基本的な知識や思考力はあり、本文は読めているけれど、問いに答えることができていないというケースが多いです。
例えば、「記号選択や抜き出しの問題は正答率が高いのに、記述問題は空欄になってしまっていることが多い」とか、「記述は〇や△がもらえて点数が稼げているけれど、記号選択問題だと取りこぼしが多い」とかです。
こうした場合には、記述問題の書き方や、選択肢の切り方・選び方の技術を教えていくことで改善されることが多いです。
実際、これまでの生徒でも、記述問題に答える上で使うパーツを本文から探す方法や、それをつなげて解答を組み立てる方法、選択問題に答える上で紛らわしい選択肢を切る方法といったことを指導したら、比較的短時間で点数に改善が見られました。
市販の参考書でもこうした解法を指南しているものはたくさんあるので、いくつか買ってみてしっくりくるものを参考にしてみると良いのではないでしょうか。
問題を解かせて、それに対してフィードバックをする形が成長につながりやすいので、個別指導や家庭教師の先生に頼むのも効果的な方法です。
3.本文が読めていない場合の対処法
他の科目との比較で相対的に「算数より国語が苦手」といったことではなく、「国語の偏差値40前後」のように塾の国語の学習についていけていない子は、そもそも本文が読めていないということが多いです。
学年が上がるにつれて、素材とされる文章も難しくなります。
物語文は、登場人物が置かれている状況が子どもにとっては想像しにくいものになりますし、説明文・論説文も専門的な言葉が増えます。
そうなると、本文の内容が理解できておらず、設問に答える以前の段階でつまずく子も増えていくのです。
お子さんが本文の内容を理解できているかどうかを確かめるには、「どんなことが書いてあった?」「例えば?」「なんで?」といった感じで、内容について会話をしてみることです。
国語の読解問題の設問だと身構えてしまって答えられない子でも、会話の中でだと答えられる場合があります。
そういう場合には1の解く技術を知らないケースだと判断して、こういう問題のときにはこう解くというルールを教えていけば改善できます。
会話をしてみてトンチンカンな回答が返ってくるようであれば、まさに読めていないケースなので、解く技術を教える前に、読む力を伸ばすトレーニングをさせてあげましょう。
読む力を伸ばすために効果的な方法は、「読み聞かせ」「音読」「読書」などです。
要は、読む力を使えば、読む力が伸びるということですね。
私が担当していた生徒たちはこちらにあてはまる子が多かったので、先ほどお話ししたように、「読み聞かせ」や「音読」をしたというわけです。
楽しくなる工夫が大事
これらをどうやらせるかは、ぜひ楽しくなる工夫をしてください。
「音読をしなさい」と言っても嫌がる子も多いですし、叱って無理やりやらせたところで真剣にやらなかったりもします。
読書も、しなさいと言っても子どもはなかなかしてくれないですよね。
指示・命令では、子どもは叱られないための必要最低限しかやりませんし、徐々に叱られてもやらなくなります。
苦手意識がある子ほどそうなります。
だから、子どもが自発的にやりたいと思うように仕向ける、楽しめる工夫をしましょう。
楽しいことであれば、子どもは真剣に集中して取り組みますし、結果として能力が伸びていきますよ。
以上、国語ができない子に国語を教える方法でした。
あなたのお子さんが国語を得意になれるように応援しています。
頑張ってくださいね!
それでは。
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

