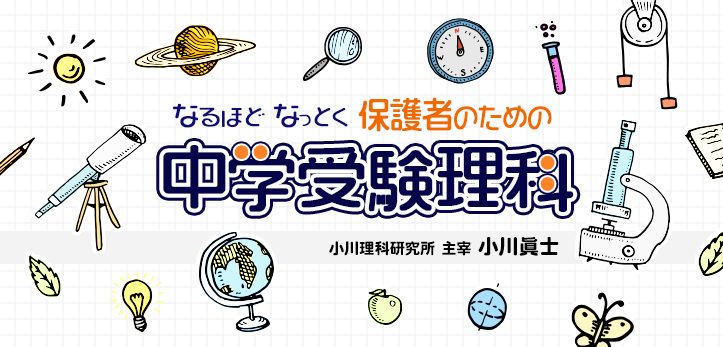
生物分野「植物」の学習は、光合成を柱にして覚える|なるほどなっとく 中学受験理科
専門家・プロ
2020年1月27日
水溜 兼一(Playce)
0
学習範囲が広く、難しいイメージがある理科の中学入試問題。難関校に多くの子どもを合格させてきたカリスマ講師・小川眞士さんが、子どもの理科力を育むためのヒントを伝えます。
理科のなかでも生物分野は、覚えることが特に多い。そう感じている受験生や保護者の方は多いようです。さまざまな事柄をどのように関連づけて学習すればよいのか? ここでは、「植物」を取り上げてお伝えします。
植物のつくりと働きは、光合成を柱にして覚える
生物分野の単元は、植物、動物、人体に分かれます。受験生は、いろいろな知識をとにかく頭に詰め込み、たくさんの問題パターンを覚えることに注力しがちです。保護者の方も植物の学習では、花の種類や特徴などを多数覚えさせなければと考えている方が多いようです。
覚えるべきことは確かにありますが、何を優先して学ぶべきかを知り、さまざまな事柄を関連づけて覚えることが大事です。知識をまとめることで、インプットだけでなくアウトプットもしやすくなります。
中学受験の植物の学習は、まず植物のつくりと働きを理解することが大事です。植物のつくりと働きに関しては、対照実験の問題もよく出題されます。問題の条件をしっかり整理し、データを確実に読み取れるようにしましょう。
植物のつくりと働きを学習するときは、
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

