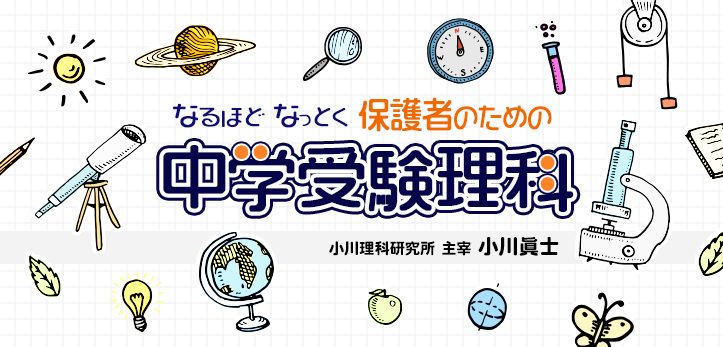
小学校の理科実験で親がフォローできること|なるほどなっとく 中学受験理科
理科の入試問題では、さまざまな実験がテーマとして扱われます。問題を解くために大切にしたいのが学校での実験授業。家庭でどんなフォローができるのかポイントをお伝えします。
器具の正しい使い方を理解し、条件整理をする
近年の理科入試では、仮説を立てて実験を行い、結果を検証する一連のプロセスを示した文章や実験データを読み取り、設問に答える問題が増えています。このような問題を解くために大事にしてほしいのが、子どもが自ら実験を行う「経験」です。
実験とは、ある事象について「こうかもしれない」と立てた仮説に対する「確認作業」と捉えることができます。たとえば、植物が発芽するために何が必要なのか仮説を立てて、水や肥料、光、空気の有無、温度など、さまざまな条件を変えて実験を行い、その結果から普遍的な結論を導き出します。
小学校ではいろいろな実験を行いますが、どの実験でも実験器具の名前と正しい使い方を確実に身につけることが基本です。顕微鏡、ガスバーナー、アルコールランプなど、実験器具の使い方は入試問題で聞かれることもあります。アルコールランプひとつとっても、ただ火をつけたり消したりすればいいわけではありません。まずアルコールが容器の八分目ぐらいまで入っているかを確認します。次に蓋を開け、マッチに火をつけ、芯の横の方から火をつけます。火を消すときは蓋をかぶせ、火が消えたらふたを取り、再度ふたをします。このように、それぞれの実験器具には正しい使い方がありますから、学校で実験を行うときもぜひ意識してください。
入試において、実験に関する問題を解く場合には、条件整理をきちんとできることが必須です。条件整理とは、
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

