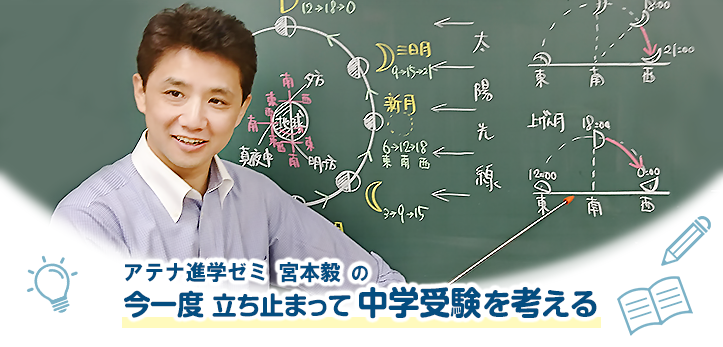
新学年 好スタートを切るためにやっておきたいこと|今一度立ち止まって中学受験を考える
首都圏では間もなく中学入試がピークを迎えます。それが終わると、2月から4年生は新5年生、5年生は新6年生の勉強が始まります。新学年で好スタートを切るために、今やっておくべきことは?
社会は少し先取り。理科は前学年でつまずいた苦手単元の見直しを
中学受験の勉強は学年が上がるごとに内容が難しくなり、量も増えていきます。ということは今成績が伸び悩んでいる子は、ますます大変になるということです。そうならないために学年が上がる今、学習のやり方を見直し、苦手教科を得意教科に変えていきましょう。各教科の学習ポイントをアドバイスします。
【社会】前学年の復習よりも新しく学ぶことを先取りしておく
社会は積み上げ式の学習です。塾では4年生から5年生の1学期まで地理を学習しますが、4年生の地理は各地方の名所旧跡や地形、農作物など、地理の基本に触れる程度で、本格的に地理を学ぶのは5年生になってからです。
5年生になると、「りんごの産地はどこか?」「りんごはどういうところで育つのか?」「果物を育てるのに適した場所はどんな地形で、どんな気候か?」など、より詳しく地理を学んでいきます。その後5年生の2学期に歴史を学び、6年生からは公民の学習が始まります。
このように5年生から6年生の1学期までは、学ぶことや覚えることがたくさん出てくるため、復習になかなか時間をかけられなくなりがちです。復習は夏休みなど時間があるときにまとめて行うほうがいいでしょう。
それよりも、私は新しく学ぶことを少しだけ先取りしておくことをおすすめします。先取りといっても、テキストに目を通しておくだけでOKです。授業でまったく知らないことを聞くのではなく、ほんの少しでも前知識があると理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。
6年生からは公民の授業が始まるのでその前に、買い物で消費税を意識させて税金のしくみを教えたり、選挙があったら共に投票所に足を運んで、政党名や国会議員の仕事などを意識させたりするなど、親御さんが少しだけ関わってあげると、子ども達の理解や暗記が進みやすいと思います。
【理科】前学年でつまずいた苦手単元を復習する
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

