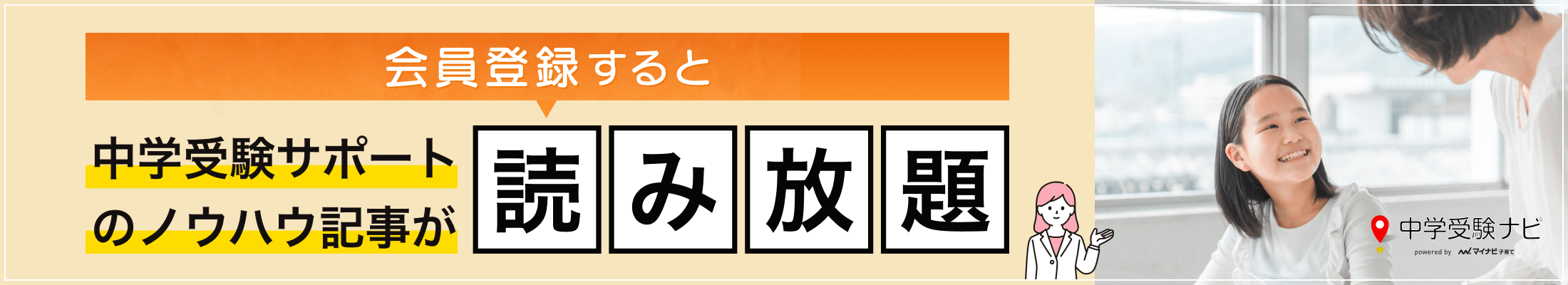「教育で社会を変えたい!」 灘中高、MIT卒業のワカモノがつくった、学びを好きになるプラットフォーム|「自分のやりたい!」がある子はどう育ったのか
AIが登場し、人間が果たす役割が変わっていこうとしています。「いい大学、いい会社に入れば安泰」という考え方が通用しなくなっていることは、多くの方が感じているでしょう。子どもたちが、しあわせに生きていくためには、どんな力が必要なのか? 親にできることは? この連載ではやりたいことを見つけ、その情熱を社会のなかで活かしているワカモノに注目します。彼らがどんな子ども時代を過ごしたのか。親子でどんな関りがあったのか。「新しい時代を生きる力」を育てるヒントを探っていきます。
今回の主人公は、子どもが学びを好きになる場「スコラボ」を運営する前田智大さん。前田さんは、灘中学・高等学校を経てアメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)に進学、大学院修了後、子ども向けオンライン学習サービス「スコラボ」を展開する株式会社Mined(マインド)を立ち上げしました。前田さんの子ども時代から今に至る話と、教育に対する想いを聞きました。
向学心を持つ子どもたちを育んでいきたい
「主体的な学びの機会を提供して、向学心を持つ子どもたちを育んでいきたい」と熱く語る前田智大さんは、大阪府和泉市出身の26歳(取材時)です。

前田智大さん
灘中学・高等学校を卒業後、MITで電子工学を専攻し、MIT Media Labの大学院に進学。将来は研究者の道に進むもうと研究に没頭していましたが、日本の教育に疑問を持ち、起業家に方向転換します。大学院卒業後は日本に帰国。オンライン学習のスタートアップ企業Minedを創業しました。
前田さんが起業しようと思った理由は次の2つです。
- 当時、所属していたMIT Media Labが、おもに社会との関わりを意識した“研究”を行う機関で、研究職よりも社会に直接的に関われる職を選択したいと思ったこと
- 孫正義育英財団の財団生に選ばれていた関係で、孫さんの講演を聞き、「事業を通じて社会を大きく変える」という考えに共感したこと
「教育分野で、社会を変えるインパクトを起こそう」と思ったのは、アメリカで学生たちが、主体的に自分の興味のあることに取り組み、目を輝かせて活躍をしていたのを見たからでした。
「本来、学ぶってもっとおもしろいことのはず。日本の教育って何か違う」
前田さんは、ちょうど社会に直接、価値を提供したいと考えてたこともあり、研究者ではなく起業家の道を選ぶことを決意したのです。そして大学院卒業後、灘高時代の親友を誘って起業しました。
2020年8月に創業。最初は高校生向けに受験勉強をマネジメントする授業を提供していましたが、それよりも「『なんのために勉強をするのか』という目的意識を育むほうが大事だ」と考えるようになります。そして子どもたちがもっと学びを好きになるようにと、オンライン少人数ライブ授業のプラットフォーム「スコラボ」を開設することにしたのです。
負けず嫌いで意思を曲げない子ども時代
前田さん自身は、どんな子ども時代を過ごしていたのでしょうか。
育ったのは大阪府の南部にある和泉市、両親と双子の弟の4人家族です。お父さんは高校を卒業後さまざまな職業を経験したあと、おじいさんの代から続くカフェを経営、お母さんも手伝っていました。いわゆる教育熱心な家庭ではなかったようです。
「両親は自分たちが4年制大学に行かなかったこともあって、『子どもたちには4年制大学には行ってほしい』という希望を持っていたそうです。ただ、そのために何か特別なことをさせようとはしませんでしたね」(前田さん)
ご両親は、子どもに「勉強してほしい」と思っていたようですが、子どもが勉強でわからないところがあって困っていても、いっさい教えなかったそうです。だから、自分でなんとかするしかないという考え方が身についたのだとか。
中学受験に関しても、ご両親はそもそもそういう受験の存在すら知らず、兄弟で通っていた公文式の先生から、「中学受験しないんですか……?」と聞かれたのがきっかけだったそう。前田さん本人も、先生から言われるままに近所の塾の体験授業に行ってみたら、これまでやったことがないレベルの高い内容で、それがおもしろくて入塾したようです。

子供の頃から意思が強く、納得のいかないことはやらないタイプだった
親の反対を押し切って灘受験を決める
「塾の先生のモチベーションの持たせ方が上手かったんです。最初は弟と競争しながら勉強していましたが……、5年生の頃からは、クラスのレベルの高い子達と競い合って勉強をしていました。ゲームのような感覚でした」(前田さん)
入塾後、小6の夏休み前には、自分から灘中を目指すようになりました。
一方の両親は、前田さんが「灘を目指す!」と言ったときに、「背伸びするより、余裕のあるところに行った方がいい」と猛反対したそうです。しかし前田さんは小さい頃から、自分の中で納得いかないことはしないタイプだったので、「どうせなら挑戦したい!」と意思を曲げずに灘中を目指して勉強することになりました。しかし、通っていた塾の校舎の先生が灘の対策を知らず、普段の学習は本人に任されたのだとか。前田さんは、自分で灘の過去問を解いて形式に慣れ、できない問題を繰り返し解いたり、『中学への算数』という問題集を解いたり、自分なりの勉強法を確立していったのです。
前田さんは当時を振り返って次のように語ります。
「おそらく、周りからいろいろと与えられすぎなかったことと、プレッシャーがなかったのがかえって良かったんです。もし両親が『是が非でも灘に!』という姿勢だったら、苦しかったと思います。『受かったところに行けばいい』というのが両親のスタンスだったので、『合格しないとダメだ』というプレッシャーを感じずに、前向きにチャレンジできました。やらされた訳ではなかったですから、それがよかったんだと思います」(前田さん)
中学受験の結果、見事合格。その瞬間のことについては、次のように回想してくれました。
「灘合格は嬉しかったです。けれども自分はギリギリで受かったと思っていたし、両親からは『これから地獄が始まる!』と脅かされていたんで、身の丈に合わない合格をもらったんだなと思って、気を引き締めてましたね」(前田さん)

何かを強制されることはなく、のびのびと育った
学校行事と生物の勉強に没頭した灘中高時代
両親からの脅し(?)もあり、灘中入学後「しばらくは緊張していた」という前田さん。でも、入学してみると、その緊張は早々にほぐれたそうです。灘は勉強の出来・不出来よりも、個々人でユニークさを競うようなところがありました。「ありのままの自分でいられる、楽しい学校生活を過ごした」と言います。
前田さんは陸上部に所属しながら、文化祭・体育祭の運営委員や、応援団などに立候補してそれらの活動に没頭していきました。勉強に関しても、恐れていたほどではなく、授業についていけたようです。

灘の文化祭では、ダンスを披露
中高時代の学習では生物が好きになりました。じつは前田さん、小学生時代は暗記ものが嫌いで、理科が一番嫌いだったそうです。ところが、中学の生物の先生の授業はとてもユニークで、暗記した内容の裏にある仕組みや理論を教わるようになると、俄然興味を持つようになったそう。
生物を学ぶ過程で進化論に関心を持つと、その関心は分子生物学まで広がりました。自分で率先して、さまざまな本を読んでいくうちに、どんどんハマっていったのです。そうしていると、生物の先生から生物学オリンピックへの挑戦を勧められるようになります。
そして中学3年生の時、生物学オリンピックに応募。このとき1次試験は通過し、全国大会には出られたものの、日本代表は逃しました。ただ、そこで諦めることなく、その翌年に再びチャレンジ。見事 日本代表に選ばれると、高校2年生の夏、シンガポールで開催された生物学オリンピック国際大会に出場します。そして銀賞を受賞したのです。
生物学オリンピックは一次試験が筆記で、2次試験は実験を行います。また、オリンピックの問題は、暗記より思考力が求められます。前田さんは特別な試験対策はしなかったそうです。日頃から生物の本を読みまくり、本質的なロジックを理解していたことが、代表に選ばれる近道となったのです。自ら興味を持って本質的なことを理解していく学び方をしていたのが、功を奏したのでした。
生物学オリンピック出場が転機に
生物学オリンピックの出場は、前田さんの将来を開くきっかけにもなりました。この時大会を運営していた研究者との出会いで、「将来自分も研究者になりたい!」という夢を描くようになったのです。
生物学オリンピック日本大会で、目標とする大人と出会ったこと。国際大会出場で海外への意識が高まったこと。生物学オリンピック出場の経歴が評価され、海外大への道がひらけたこと。これらは前田さんにとって大きな転機になりました。
そして高3、前田さんの進路を決定づける出来事が起こります。それは先輩のひと言でした。
「あれは生物学オリンピック出場後、趣味で生物を勉強しながら、『東大に行こう』と受験勉強を始めた頃だったと思います。1学年上のハーバード大学に進学を決めた先輩から、『前田なら海外大に行けるよ』と言われたんです。先輩のそのひと言が“ズシン”ときて、海外大を目指すことに決めたんです」(前田さん)
じつは前田さん、国際大会に出た時、海外の出場者たちとの交流を通して、海外大へ進学したいという思いを抱いていました。しかし当時は「帰国生でもない自分には難しいかな……」と思い込んで、モヤモヤしていたのです。先輩に励まされたことで、「やれるかもしれない」と思えて、本格的にMITを目指しはじめました。高3の4月末頃の出来事でした。

生物学オリンピックで海外の学生と交流し、視野が広がった
東大とMIT両方に合格
「MITを目指す」―― そのことを両親に話すと、当然 驚かれました。以前から、留学に興味があることは話していましたが、両親は「大学院で行くのかな……」程度に思っていたからです。ただ、両親から言われたのは意外なひと言でした。
「東大には受かりなさい。そのうえで海外大も受かったら、行っていい」
小学生の頃の「4年制大学には行ってほしい」という願いからすると、だいぶハードルは上がっていますが……、両親としてはMITで落ちこぼれた時に、日本に帰ってくるところがないと困るだろうという想いからだったようです。当時の成績なら東大は合格圏だったこともあり、前田さんは両方を目指して勉強をすることになりました。
とはいえMITと東大では、それぞれの対策が異なります、その点はどうだったのでしょう……。前田さんは次のように話します。
「アメリカの大学受験は課外活動とエッセイが大事です。私は、生物学オリンピックに出場したり、学校の生徒会活動も積極的にしていたので、エッセイを書くための材料は持っていました。一番の課題は……、英語でした。アメリカの共通テストであるSATの対策で、高3は英語の勉強にひたすら集中していましたね」(前田さん)
東大とMITを受験した結果、見事どちらも合格。そしてMITに進学を決めたのです。

MITのフォーマルディナーの様子
社会を変える切り口として教育事業を選択
留学当初は生物を専攻しようと思っていたそうです。しかし、大学での専攻は、電子工学でした。観測と計測機器が発展すると、もっと研究に貢献できるからそこを学びたいと考え、1年の途中で専攻を変えたのです。
そして大学院ではMedia Labに所属。「目に見えないものを観測する」というテーマで研究を進め、修士を取りました。Media Labは、「社会との関わりを意識して何かを生み出していこう」という考え方を推奨している機関でした。
この頃、前田さんも社会との繋がりを強く意識するようになります。
自分が研究していることは、意義はあるけれど、それが実用化されるまでに早くても10年かかる。だったら、もっと社会に密接に関われることをしたい ―― こうした想いを抱くようになります。
ちょうどそんな悩みを抱えていた時に、孫正義さんの講演を聞き、研究者ではなく起業をする決意をするのです。

MITのイベントで
「起業して何をするのか」そう考えた時に浮かんだのが、アメリカで目を輝かせて活躍する学生たちと、成長したいと思いながらも、実際は苦しみながら勉強する日本の学生との差でした。
日本の学生たちはとても真面目で、良い人間になろうとしている。けれど、主体的に自分の学びを選ぶのではなく、学校や塾で与えられたことをこなすだけになっているので、目的と興味が欠けた勉強をしている人が多い。高校生本人も実際はそんな日本の教育に納得していない。ところが、真面目な子ほど大学に行くために、「成績は取らなくてはならないもの」という現実との間で葛藤している。こんなに良くなろうとしている子どもたちがいるのに、苦痛のような勉強になってしまうのはおかしい ―― こうした想いが募っていたのです。
そんな課題意識から、学ぶことを楽しみ、前向きになれる環境を作りたいと思い、社会を変える切り口として教育事業を選択することにしました。

大学の卒業式 両親も訪れた
MITで得たのは、イタズラ心を持って取り組むマインド
前述のような想いを抱いたのには、前田さん自身のMITでの経験も影響していました。MITでは何百種類の授業から、学期ごとに2、3科目選んで受講できます。だから、ほとんどの授業が、自分の興味や目的と合致したことを学べるのです。
またMITに集まる学生は、たとえば掃除ひとつするにも、どうやったら楽しめるかを工夫するなど、日常の小さなことをとことん楽しんでいました。考え抜く力も半端なく、ゲームで遊ぶにしても、どうすればもっとうまくやれるかということを、真剣に考えていました。かたや、日本の学生は、真面目で学力を伸ばすことには長けているけれど、勉強は「しなくてはいけないもの、苦しいもの」だと思っていて、学びを楽しめていない。
もちろんアメリカの教育がバラ色というわけではありません。楽しむ姿勢や主体性を重視する姿勢に偏ることで、表面的な学びに終わってしまうこともあります。けれども、少なくとも大学教育で専門性を高めるには「好きなこと」が根底にあって、主体的に学ぶことが重要になります。そうなると、楽しくてガンガン学んでいる人に勝てないのです。
日本は高校卒業時の学力は世界一だけれど、その後伸び悩むというのは、こういうところの差から来ているのでしょう。
MITのカルチャーに「ハック」という言葉があります。これはイタズラという意味で、「イタズラ心を持って取り組め」というカルチャーです。前田さんが、MITで受け取った最大のメッセージでした。

MITのハック(いたずら心)。映画『Back to the Future』のデロリアンがモチーフ
興味や楽しさを起点に、学びを好きになってほしい
日本の塾には良い面もあります。しかし、固定されたカリキュラムを作り、できるだけ多くの人に受講してもらうため、どうしても「不安感を煽る」という構造になりやすいです。だから、押し付けられたような学びが溢れがちです。子どもたちが自分の興味あることを学びたいと思っても、それができる場所がなかなか見つからない実態もあります。
前田さんが展開する「スコラボ」は、生徒の学びたい気持ち・ニーズに合わせて、先生と生徒をマッチングするシステムです。教える側は、自分が教えたいことを教えて、副業として報酬を得ます。子どものやる気を引き出すというより、それぞれの個性を活かして子どもがやりたいことをやって、本人の興味をサポートしているのです。
「スコラボ」で学ことが楽しいという経験をしてもらうことで、子どもたちの向学心が高まり、進路について自分で決められる子が増えていく ―― そんな未来を描いているのです。
「スコラボを通して、子どもたちの可能性を伸ばし、個性があって好きなことがある人が社会に増えるといいと思っています」と想いを語ってくれました。
■スコラボの特徴
- 子どもが学ぶことを選べる
- カリキュラムが固定していない
- 普通の子どもが受けている
- 少人数制で対話をしながら進める
- 雑談で決めていくから頭が働く
- 質問に答えられることが求められる
何か一つでもいいから楽しんで打ち込めること探そう
前田さんに、子どもたちと親たちへのメッセージを聞きました。
不安に駆られてやると不安が増えていきます。子ども達には、何か一つでいいから、楽しんで心から打ち込まれることを見つけてほしいと思っています。それはたとえば、ゲームの順位を上げるでも構わないと思うのです。目標を持って打ち込めるものがあればいいんです。そこから始まります。何かをする時には、自分がエキサイティングできるかどうかを大事にしてほしいです。
保護者の皆さんには、子どもが楽しんで打ち込める時間を作ってほしいと思います。保護者がしてほしいことを子どもに押し付けるのではなく、子どもの主体的な考えをベースに、子どもと対話しながら「エキサイティングな何か」を見つけるサポートをしてあげてほしいです。
大人は子どもと比べて経験値が高いので、どうしても会話が一方的になってしまがちです。だから、子どもたちの視点では、大人が言うことに納得できないことも多いのだと思います。
大人も子どもも、納得できるまで対話をし続ける必要があるんです。ところが親子だけだと、どうしても対話が難しかったりします。そういう点では、第3者のほうが関わりやすい面もあると思います。私もまだまだ未熟ですが、できるだけ子どもたちの興味を掘り出していく手伝いをしていきたいです。
取材を終えて
今回の取材を通して感じたのは、やはり興味や関心が学びに向かう出発点だということです。誰かに強制される、やらされる勉強中心では、本当にやりたいことはなかなか見つからないということです。そういう意味で、私が『成功する子はやりたいことを見つけている 子どもの探究力の育て方』のなかで書いた、「これからは教育熱心な家庭の子どもほど伸び悩む」というメッセージを裏付けてくれるような取材でした。
前田さんの両親は勉強を強制せず、結果的に前田さん自身のやりたい気持ちを尊重していました。それによって親が思う以上の世界に飛び出していったのです。もちろん、もともと持っていた資質も素晴らしいのだと思います。しかし、興味を持ったことを妨げられなかったからこそ、ここまで伸びたのだと思います。前田さんが用意した環境で、学びを好きになった子どもたちが、どんどん自分の世界を広げていくことを期待したいと思います。
スコラボ公式ページ(https://sukolabo.com/)
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます