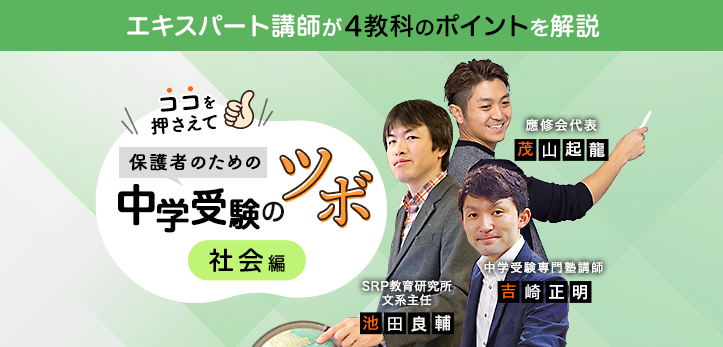
【小6社会/農業】江戸時代までの農業の歴史|中学受験のツボ[社会編]
専門家・プロ
2023年4月30日
池田良輔
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説
- 社会以外の3教科はこちら -
今回は「分野別の歴史」のうち、古い時代の農業史についてお伝えします。
この分野の流れをしっかりつかむことで、ほかの分野とのつながりも捉えやすくなりますよ。
農業技術が進展していった
「租・調・庸」という税制に見られるように、平安時代末くらいまでは稲作中心で、それに加えて繊維の原料と、少しの野菜をつくるのが平均的な農業でした。
それが鎌倉時代になると、鉄製の農具や牛馬耕(ぎゅうばこう)が普及し始めます。牛馬耕とは、牛や馬に犂(すき)を引かせ、深く耕す方法のこと。同じ田畑で一年に2種類の作物を栽培する「二毛作」が西日本で広がったため、土壌の深い層の栄養すらも引き出す必要があったのです。そして、それだけでは足りない栄養を補うために草木の灰なども肥料に使うようになりました。
室町時代には二毛作が全国に広がり、西日本では「三毛作」さえ見られたそうです。そのためさらに肥料が必要になり、人や家畜の糞尿を肥料にする技術が広まりました。
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

