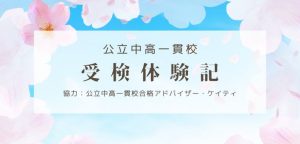【公立中高一貫校受検合格に向けて】2024年度の振り返り【後編】 |公立中高一貫校合格への道#12
こんにちは!公立中高一貫校合格アドバイザーの、ケイティです。公立中高一貫校合格を目指す、保護者のための「ケイティサロン」を主宰しています。
前回の記事では、公立中高一貫校受検に関する倍率の捉え方や、2024年度に合格した子がこの時期もっていた「書く力の高さ」について、お伝えしました。
この記事では後編として、「2024年度に合格したご家庭の取り組み」についてさらに掘り下げて紹介していきたいと思います。
決してあなどれない!【報告書】のこわさ
一般的に、公立中高一貫校の合否は適性検査の得点と、出願時に提出する報告書の得点を合わせた総合成績で決まります。
報告書(調査書と呼ぶエリアもあります)とは、学校で作成が義務付けられている指導要録をもとにして作られる書類で、通知表と同じように三段階の評定が記載されています。
通知表は学期末に受け取りますが、指導要録は学年ごとの評価なので、通知表の評定とは若干の差があります。
ほとんどの学校で五年生・六年生の評定が使われますが、四年~六年までの評定が報告書に必要な公立中高一貫校もあります。(六年生の評定については、出願書類を作る時点ではまだ学年末を迎えていないために、「一学期及び二学期の評価等を十分参考にして、年末までの評価等を記入する」と決められています)
報告書の配分は一律ではありませんが、総合得点のうち3割を報告書が占める学校もあるので、検討している学校の比重がどうなっているか、募集要項で確認をしておきましょう。(公表していない学校もあります。)
私自身、様々なところで「適性検査の点数が何より大事」と言ってきましたが、そうは言っても、得点が同じでも報告書の差で不合格になってしまったという、いわゆる「報告書の下剋上」は、起こっているので、報告書を軽視することはできません。
報告書は、たとえば都立富士中を例に紹介すると「3」 なら25点、「2」なら15点、「1」なら5点、というように加算され、その合計点を300/450に「圧縮」したものが最終的な得点となります。
仮に、「3」をとった場合と「2」をとった場合で比較してみると、(25-15)×300/450で、7点弱の差が付くことになります。
なお、例に挙げた都立富士中の場合、適性検査の点数と報告書の点数を合わせた全体の総合成績 は1000点満点なので、「3」と「2」の差は0.7%弱ということになりますが、このような科目が3科目、4科目とあるならどうでしょうか。
公立中高一貫校を受ける子の場合、報告書も「3」が過半数をしめる子が多いので、わずかな数%でも積み重なれば結果に影響することは、ご想像頂けるかと思います。
実際、今年ある都立中では、適性検査Ⅰが満点で、かつ、Ⅱが他の合格者よりも上回っていた子でも、不合格になってしまったケースがありました。
また、東京都以外でも、たとえば神奈川の県立中や横浜市立の公立中高一貫校でも、適性検査における不合格者最高点が合格者最低点を上回っていることが「普通」に起こっています。
(不合格者最高点>合格者最低点ということはつまり、適性検査で上回っていても、報告書の差で不合格になっている、ということです。)
あくまでも本番の適性検査の得点が重要ではありますが、ボーダー付近は1%未満の争いにもなるので、報告書をあなどることはできません。
合格者のご家庭は、テストの得点やクラスの中での立ち位置などよく把握なさっていて、先生に対しても上手にお子さんのアピールをしているように感じます。
また、たとえば自学ノートなども、調査する「ネタ」を保護者の方からも提案したり、調べ学習の際は積極的に協力したり一緒に足を運んだりなさっているようです。
日頃から報告書を意識して目を光らせているというよりは、学校からの指示に対して積極的に関わった結果、自主性についてプラスの評価に繋がっているのだと思います。
本番の得点で圧倒できればそれに越したことはないのですが、倍率の高い公立中高一貫校は、「たった1点」の差で壁を超えられないこともあるのです。
数年前、あと一歩のところでご縁がなく、「適性検査で点を取れれば大丈夫、と思って通知表は目をつぶってきたけれど、今思えば、その数%にもこだわれば良かった……」とおっしゃったお母さんがいます。
一生懸命に適性検査対策をした結果が報告書で覆されることのないよう、学校生活に「慣れ」が出始めた今の時期こそ改めて、お子さんの学校でのご様子や取り組みにも注目して頂ければと思います。
▼報告書についてはこちらの記事もご覧ください
保護者による積極的な介入を楽しめること
適性検査は記述の問題が多く、また、仮に選択肢問題が多い学校だったとしても、丁寧な読解や情報整理能力が問われるため、本人任せ、塾任せにはせず、保護者の方が対策に関わることを私は推奨しています。
放っておいても自分でどんどん思考力が伸ばせる子も、いないわけではありませんが、かなり稀です。
適性検査は単に計算すれば答えが出るような問題ではないので、たとえばお子さんの答えが空欄のままだった場合、分からなかったのか、分かったけれど記述ができなかったのか、時間がなく飛ばしたのか、長い問題文の整理ができなかったのか、など、要因を一つずつ潰しながら分析し、それに応じたフォローを考えなければいけません。
このような対応は、よほど手厚く見てくれるような塾でない限り、難しいと言えます。
理想は、受検生本人が丁寧に自分の取り組みと向き合い、熱意と自主性を持って学力を向上させていくことですが(実際、公立中高一貫校が求める子はこのような能力を持っている子であり、その力がないと進学してからが辛いのですが)、そうは言っても、みんながみんな最初から 出来ることではないと思います。
私自身が中学受験生だった頃とはずいぶん様子が変わり、高いハードルに目の色を変えて食らいつくような子は今は少なく、隣に寄り添い、前向きに励まし、時には気持ちを盛り上げながら、一緒に走ってあげて、そして徐々に手を放していく方が結果的によく伸びるように感じます。
特に今の時代は保護者の方も熱心に情報収集なさっていて、適切で適度な声がけをするノウハウやツール(教材や講習)もよくご存知です。
合格者のご家庭の保護者の方は、受検体験記を読んで頂ければわかるように、学習管理や計画立て、添削など、非常に熱心に関わっていらっしゃいます。
公立中高一貫校受検においては「完全塾任せ」の合格は難しいので、積極的な介入を楽しんでいた方が、2024年度も多かったと感じます。
(もちろん、充実した時間だったと今だからこそ言えるのであって、当時は本当に大変な日々だったとは思いますが……。)
「前に言ったよね?」は当たり前、と割り切ること
適性検査対策を効率よく進めるためにも積極的な保護者のサポートが鍵であることは常々感じているのですが、伴走する以上、親子の衝突も当然多く起こってしまいます。
なかでも、本格的に対策を始めて以降、保護者が何度もぶつかることになるのが、同じミスを発見したときのガッカリ感です。
一番近くで見ているからこそ気付くことではあるのですが、「ついこの前も同じ間違いで部分点しか貰えなかったのに…!」といったモヤモヤを、何度も感じることになります。
このような度重なる減点は本当に心をすり減らしますが、最終的にはみなさんおっしゃるのが、「信じるしかない」という言葉です。
適性検査の場合、暗記知識や公式で解けるような問題はほぼ無く、同じようなジャンルでもあの手この手で切り口を変えて出題するので、「以前、引っかかったから次は気を付けたいこと」を頭の中で整理するのが難しいと言えます。
保護者の方は冷静な状態で問題と解説を見ながら添削しますが、受検生は手探りの状態で制限時間を気にしながら問題を解いているので、(言い方は悪いですが)常に「出たとこ勝負」の状態で問題に臨んでいると考えてください。
以前にアドバイスしたことが確実に活かせる訳ではなく、何度も何度も、何か月もかけて同じことを伝え続け、その結果、数回に一回はうまくアドバイスが活かせるようになっていくものです。
たとえば資料読み取り問題では、「変化が突出しているところに注目すること」、「比較するときはそれぞれの特徴に触れながら記述すること」、など、どうしても曖昧なアドバイスが多くなりがちですし、アドバイスを参考にして書いたら逆に裏目に出てしまうようなこともあるので、子供達は日々、四苦八苦しながら適性検査と向き合っています。
それでも一生懸命毎日机に向かっていることを尊重したうえで、何度も同じようなことを伝えることになったとしても気持ちはグッとおさえてなるべく衝突は避けましょう。点と点が繋がっていく時期が必ず来ますから、お子さんを信じて、根気強くアドバイスをしてあげてください。
まとめ
さて今回は、2024年度の振り返りとして、合格者のご家庭が取り組んでいた様子を紹介させて頂きました。
学校見学会や授業公開、適性検査解説会など、学校が開催する行事も多くなってくる時期です。
モチベーションを高く保ち、「天王山」とよばれる夏休みを迎えられるよう、先輩保護者の歩みを参考にしながら、学校生活や受検対策にぜひ積極的に関わって頂きたいと思います。
▼公立中高一貫校の受検体験記もぜひご覧ください
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます