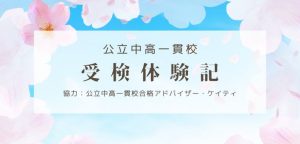東京、神奈川、千葉、埼玉の公立中高一貫校の特徴 |公立中高一貫校合格への道#13
こんにちは!公立中高一貫校合格アドバイザーの、ケイティです。公立中高一貫校合格を目指す、保護者のための「ケイティサロン」を主宰しています。
今回の記事では、改めて、公立中高一貫校の選抜の仕組みや、問題の特徴について紹介していきたいと思います。
公立中高一貫校を検討中の方や、私立中学が第一希望で公立中高一貫校についても情報収集中の方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
なお、この記事は令和6年度(令和6年・2024年に新中1になった学年)の募集要項をもとに作成しています。例年、夏休み明けから秋頃にかけて次の年の募集要項や詳細が発表されるので、受ける学年に合わせて最新の募集要項を確認するようにしてくださいね!
Contents [hide]
そもそも、公立中高一貫校の選抜とは?
今回は東京、神奈川、千葉、埼玉の公立中高一貫校の募集について紹介しますが、まずは、全ての学校に共通する点をまとめると、
・複数の公立中高一貫校を併願することはできない
・小学校が作成する調査書も、評価の対象
・倍率は、基本的に私立中学よりも高め
・科目の枠を超えた「検査」が行われる
この4点です。
私立中学はレベルにあわせて、本命校以外にも「チャレンジ校」や「おさえ」の学校を受けたりすることもありますが、公立中高一貫校は一校だけを選ぶ必要があります。
また、午前・午後受験のような複数のチャンスが与えられることもありません。
まさに「一発勝負」なのです。
調査書(報告書)が必要であることも大きな特徴です。
学校によっては、4年、5年、6年の3学年分の調査書が必要なことも。
公立中高一貫校を検討し始めたら、小学校との関わり方も考慮しなければいけません。
私立中学受験を検討する場合は、手持ちの偏差値や、通学時間、教育方針や特色……などから受ける学校を選ぶことができますが、公立中高一貫校の場合は、お住まいの都道府県にある公立中高一貫校(現実的な通学時間で絞ると多くても2、3校)の中から、通知表や適性検査の取れ具合、倍率を総合的に分析して1校選び、適性検査に少しでも慣れるための特訓をしながら可能性を1%でも高めていくための戦略を立てることになります。
東京都の公立中高一貫校
東京都には、10校の都立中、1校の区立中があります。
・都立小石川(文京区)
・都立白鷗(台東区)
・都立両国(墨田区)
・都立桜修館(目黒区)
・都立富士(中野区)
・都立大泉(練馬区)
・都立三鷹(三鷹市)
・都立武蔵(武蔵野市)
・都立立川国際(立川市)
・都立南多摩(八王子市)
・区立九段(千代田区)
検査は2月3日に行われるので、私立中学受験組も、2月1日、2日に本命校の受験を終えて2月3日は中高一貫校に参戦、というパターンも大いにあります。
実際、私立中学受験に特化した対策をしてきた子たちが、(本格的に適性検査対策をしていなくても)公立中高一貫校に向けてずっと対策してきた子以上の高確率で都立中に受かっており、「低学年から私立中学受験に向けてトレーニングを積んできた猛者達もライバルである」ことを、公立中高一貫校専願のご家庭もしっかりとふまえておく必要があります。
検査については、適性検査Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとあり、面接はありません。(一部、特別枠と呼ばれる受検タイプでは面接が実施されるのですが、卓越した能力を示す資格や受賞歴が必要となる枠なので、今回は割愛します)
なお、都立桜修館、都立三鷹、都立立川国際、都立南多摩の4校は、適性検査Ⅰ・Ⅱのみを行い、Ⅲはありません。
基本的にはⅠが文系(読解と作文)、Ⅱ、Ⅲが総合問題という位置付けですが、Ⅲは、難易度の高い理系問題が主な出題となっています。
都立10校については、一部、共通した問題を使用しています。これを、共同問題と呼びます。共同問題ではなく、学校ごとに作成された独自問題を使っている学校もあります。
独自問題については、欲しい生徒の適性や学習到達度に合わせた内容を学校ごとに作成するため、共同問題に比べて個性的であり、難易度も高いのが特徴です。
学校の教育方針をよく理解し、くり返し過去問演習をして傾向を把握する必要があります。
適性検査Ⅲは全て、独自問題です。また、小石川、武蔵、桜修館、三鷹は、適性検査Ⅱの一部の大問で独自問題を使用しています。
文系の検査Ⅰについては、桜修館、三鷹、立川国際、南多摩が独自問題となっています。
どの学校も魅力的で特色ある授業を行っているので、志望校が決めきれないこともあるかと思いますが、独自問題の有無、それから、検査ごとの配点の違いもあるので、できれば夏休み明けくらいには志望校を確定させ、その学校に特化した対策を行っていった方が良いでしょう。
ここからは、学校ごとの大まかな特徴と対策について説明していきます。
都立小石川
都立中の中でも、最難関の学校です。
私立中学受験に特化した塾からの参入も多く、求められる計算力が非常に高いという特徴があります。
検査ごとの配点は同じで100点満点×3つの検査なので、苦手を作らない学力バランスの良さを意識し、例年出ている桁数が多い小数計算と、適性検査Ⅱの大問2と、適性検査Ⅲの独自問題への慣れを追求したいところです。
Ⅱ、Ⅲともに、数字を扱う能力の高さが求められるため、早い段階からコツコツと計算のトレーニングを積み、難易度の高い算数応用問題にも積極的に挑戦しながら、自分の考えを「証明」するような記述の特訓も必要です。
都立白鷗
適性検査Ⅰは独自問題を採用していましたが、令和6年度からは共同問題になりました。
検査Ⅲは難しすぎるということはありませんが、理科分野は本質的な理解が求められ、算数分野も多数の試行錯誤をしながら記述する問題も出されるため、「算数が苦手」と感じる子は「何とかして半分は取る!」というつもりで時間内に取れる問題を探す戦略を一緒に組んであげるのが良いです。
都立両国
適性検査Ⅲの難易度が突出して高い学校です。
算数がもともと好きな子や、粘って書き出して……という地道な作業でも投げ出さず食らいつけるタイプの子であれば対応できますが、両国の適性検査Ⅲは、大人でもお手上げになるような問題が多数出題されます。
また、記述がほぼ無いという特徴もあり、答えが導けなければ全く点が積み重ねられず、点差も広がっていきます。算数に強みがある子に薦めたい学校です。
得点の換算は総合問題のⅡが2倍、算数に特化したⅢが3倍になるので、そういった比重から考えても、検討する場合は「算数(検査Ⅲ)が取れるかどうか」で判断すると良いでしょう。
都立桜修館
適性検査Ⅰと、Ⅱの算数分野が独自問題となっています。
検査Ⅱの算数は大問1つ分とはいえ、かなり煩雑な書き出し、仮説検証が必要な問題ばかりで、なおかつ、記述力も求められます。この大問1の配点は100点中40点を占めるので、しっかりと過去問演習をして傾向をつかむ必要があります。
また、得点は、検査Ⅰが2倍換算に対し、検査Ⅱが5倍換算されるのも大きな特徴です。
特筆すべきは、適性検査Ⅰの作文についてです。
高い論理的思考力と語彙力を求める学校だけに、検査Ⅰの難易度が非常に高いです。
よくあるタイプの、意見を書いて、体験を書いて、まとめを書く……というオーソドックスな作文の型では通用せず、文章を読んで考えたこと、つまり自分の意見だけで400字以上500字以内を書ききる力が求められます。
大人でも、自分の意見(しかも、相手を納得させるだけの深みのある意見)を400字以上書くのはなかなか苦しいものです。
日頃から、言葉や学び、教養などについて考えたり議論したりする習慣がある子には非常に相性の良い学校です。
都立富士
適性検査Ⅲが、独自問題です。
HPで問題が公開されているので問題をご覧いただければわかると思いますが、とてつもなく情報量が多く、読んで、何が行われているのか理解するだけでも相当な根気と冷静な読解力が求められます。
資料や図を含む説明が約2ページ続き、そのあとやっと1問……そしてまた長い説明が2ページ……というような構成ではありますが、よく読んで指示通り試せば答えが出る、というサービス問題も隠れているので、ある程度適性型の算数に慣れた後は、過去問演習をして富士らしい形式に恐れないようにしていきたいです。
都立大泉
富士と同じく、適性検査Ⅲが独自問題です。
近年は算数だけでなく理科分野からも出題されており、特に実験観察が好きな子にとっては、解いていて面白さを感じる出題となっています。
難易度も平均的ではありますが、手数の多い計算や高い立体センスが求められる年度もあるため、バランスよく「理系に強い」子が望ましいです。得点は、検査Ⅱが2倍換算に対し、検査Ⅲが3倍換算になることも特徴です。
都立三鷹
検査Ⅰと、検査Ⅱの算数が独自問題です。
検査Ⅰは都立中の中でも特殊で、物語文や、詩からも出題されています。
そのため、情緒的な文章が得意ではない子にとっては、慣れるまでは点が伸ばしづらいと感じる学校です。
特に男子は、女子が主人公の物語文から心の機微を汲み取ることができず、過去問演習をしていても苦戦することが多いです。
とはいえ、総合分野である適性検査Ⅱの換算は5倍(文系のⅠは3倍)という差があり、算数分野の得点が100点中40点をしめることから、文系で大きな失点をせず、算数分野がしっかり得点できれば健闘できる学校と言えます。
都立武蔵
小石川と並ぶ、難易度の高い学校です。
倍率は都立中の中でも穏やかな方なので、倍率だけ見ると入りやすそうにも見えますが、独自問題である適性検査Ⅲの算数が非常に難しく、また、理科もそもそもの関心が高くないと着眼点から差がつくような問題になっているため、付け焼き刃の対策では対応ができません。
算数分野においては、図形の移動や規則性といった私立中学受験組が強い分野からも出題され、また、理科においても知識があれば解きやすい(裏を返せば、知識量に差を付けられると正解に辿り着くまでに時間が取られる)問題であることから、入学後の学習難易度の高い武蔵だからこそ、小学6年生の時点で学習体力や学習習慣がしっかり出来上がっている子を求めていることが読み取れます。
適性検査Ⅱの社会も独自問題ですが、国語的な読み取りや要約の問題が多く、それほど難しくはありません。やはり鍵となるのは適性検査Ⅲ対策の完成度になるでしょう。
都立立川国際
適性検査Ⅰが独自問題です。
割と読みやすい文章が多く、また、テーマも公立中高一貫校によくあるリーダーシップを問う傾向が続いています。
大きな傾向の変化はないので対策がしやすいようにも見えますが、非常に長い文章をしっかり読み込んで主旨をつかみ、そしてその内容に沿って「自分はその考えをどんな場面でどう活かすか」を述べる必要があります。
そのため、読解のトレーニングが不足している子や、立川国際進学後のイメージが固まっていない子には、点を伸ばすことが難しいと言えます。
都立南多摩
立川国際同様、適性検査Ⅰが独自問題です。
難解な文章が出るわけではありませんが、二つの文章が与えられそこから共通する主旨を読み取るという抽象力や概要把握力が求められるため、根本的な読解力が求められます。
また、細かな条件があるので、それをきちんと整理して徹底して守るという慎重さも求められます。慣れていないと一朝一夕ではできないですし、みなさんしっかりと南多摩の型で特訓したうえで臨みますから、難し過ぎないからこそ、大きな失点を防ぎバランスよく取れるよう練習していきたいところです。
区立九段
千代田区にある公立中高一貫校で、区分A、区分B、という二つの枠があることが大きな特徴です。
区分Aは、学校のある千代田区に住所があり、卒業まで千代田区に居住することが求められます。一方、区分Bは、千代田区外からの受検者の枠です。
区分Bは非常に狭き門であり、一筋縄ではいかない学校です。
適性検査はⅠ、Ⅱ、Ⅲともに独自問題であり、難しすぎる問題はありませんが、問題数が多く、正確な計算力、読解力、高い処理速度が求められるため、地頭が良く要領の良い子におすすめしたい問題です。
作文分野では、物語文や詩からも出題されており、言い換えのできる語彙力や感受性、シンプルに体験談や意見をまとめ切る表現力が求められます。
神奈川県にある公立中高一貫校
神奈川県には、県立、市立、それぞれに公立中高一貫校があります。
・県立相模原(相模原市)
・県立平塚(平塚市)
・横浜市立南高附属(横浜市港南区)
・横浜市立サイエンスフロンティア高附属(横浜市鶴見区)
・川崎市立川崎高附属(川崎市)
この5校です。
受検倍率は下がりつつありますが、それでも平均して5倍弱という、かなり狭き門のエリアと言えます。
また、県立、市立、どのタイプの問題も骨太な難易度であり量も課されるため、相当な練習を積んでいないと、この倍率を突破することは難しいです。
では、それぞれの対策について見ていきましょう。
県立相模原・県立平塚
この二校は同じ適性検査が使用されます。
検査数はⅠとⅡの二つであり、一部、数値や記号を記述する問題もありますが、基本マークシート型という大きな特徴があります。
また、作文、というほどの長さではありませんが、70字程度の記述が2つ、出題されています。短いので簡単そうに見えますが、実はこの作文が非常に厄介です。
作文は、長ければ長いほど書くことは簡単で、短くまとめようとすればするほど、難易度は高くなります。
書くべきことをシンプルに指示通りの形で短く1,2文でまとめるのは、情報量を適切に削ったり言い換えたりする力が求められるので、多くの受検生が苦戦するところです。
かなり辛口で採点されるのですが、合格者の話を聞くとこの2つの記述でしっかり満点を取れていた子が多いので、練習量の差が出るのだと感じます。
検査全体の特徴としては、理科分野や社会分野、家庭科のような分野からも出題されるのですが、基本的には資料の読み取りと計算処理が求められるため、「ほぼ算数」とみなすこともできます。
選択肢問題ばかりだからといって雑な読み取りをせず、丁寧に、そして計算トレーニングと立体問題の演習を地道に続けることが、合格への近道になります。
横浜市立南高附属
全国的に見ても、非常にハイレベルな学校です。
検査はⅠ、Ⅱのみですが、受検者層の偏差値が高く、高い学力の子たちの中で狭き門めがけて競うことになるので、学習量や学習時間の負荷はどうしても避けられません。
授業の質の高さや英語教育も魅力の学校ですが、小学6年生の時点で厳しい競争を経験してきたことによる学力の基盤が、大学進学実績にも繋がっているのだと思います。
適性検査Ⅰについては、社会分野や国語分野の読解が主に選択方式で出題されます。それと同時に、短文記述と、長文記述の2パターンの記述問題も含むのが例年の傾向です。
特に長文記述の方は、自分の体験や意見を述べるのではなく長文要約が求められるため、慣れていないと厳しいです。
しかし裏を返せば、日頃から要約のトレーニングを積むことができれば、得点につながるとも言えます。
検査Ⅱについては、難易度は高いものの丁寧に読んで計算していけば対応できる、という良問揃いではありますが、45分という制限時間で埋めないといけない枠が30近くあり、高い処理能力と根本的な算数力が求められます。
横浜市立サイエンスフロンティア高附属
適性検査Ⅰについては、横浜市立南と共同なので割愛します。
検査Ⅱは独自問題なのですが、非常に個性的で、人を選ぶ内容と言えます。
ただ、サイエンスフロンティアを目指す理科や実験が大好きな子にとっては、ワクワクするような問題かもしれません。
設備も素晴らしい学校なので、実験がしたいから、という理由で志願する子も多いのですが、サイエンスフロンティアの問題は専門用語も多数登場し、また、難解な説明文や見たことがないような資料も怒涛の勢いで登場するので、冷静に情報を整理し分解して理解する読解力が不可欠です。
また、算数問題においても、全国的に見て非常にレベルの高い部類に入ることから、総合的に全ての分野で素地の高い子が求められる学校と言えます。
川崎市立川崎高附属
適性検査Ⅰ、Ⅱが実施され、Ⅰは総合型、Ⅱが文系です。年により入れ替わりもありますが、全体の中で半分超が理系分野であり、また、作文の配点が総合得点の5分の1を占めるという特徴があります。
合格ラインが高いのも特徴で、できれば8割は取りたいところです。難易度はそれほど高いわけではないので、わずかなケアレスミスも合否を分けることになりかねません。
また、作文はかなり個性的で例年驚かされますが、「複数の文章を見て多角的に物事を見ながら自分の意見を述べる」という本質は変わらないため、くり返し過去問演習に取り組み、市立川崎が求める生徒像を意識して適性のアピールをすることも求められます。
検査Ⅰでは、ほとんど全てのページに資料が使われており、なおかつ、問題数も25問近くあるので、素早い読解と資料の把握が求められる学校です。
千葉県にある公立中高一貫校
続いて、千葉県にある公立中高一貫校です。
千葉も、県立、市立、それぞれに公立中高一貫校があります。
・千葉県立千葉(千葉市中央区)
・千葉県立東葛飾(柏市)
・千葉市立稲毛国際中等(千葉市美浜区)
この3校です。
県立の2校は、同じ問題が使われます。
県立、市立に共通するポイントは、12月に一次、1月に二次、という二段階方式で検査が行われるという点です。
一般的な中学受験シーズンといえば1月後半~2月初旬ですが、それよりもかなり早い段階で行われるため、夏休みが終わる頃には「もうあと3か月しかない」という差し迫った状況になることと、一次突破最優先で一次対策を行うのか、一次・二次全体を見据えた対策を行うのか、という対策軸の置き所に悩まされるのが千葉の特徴です。
では、それぞれの対策についてポイントを見ていきましょう。
千葉県立千葉・千葉県立東葛飾
この2校の検査問題は共通しており、一次では7倍~10倍という高い倍率はよく知られていますが、問題の難しさも際立っている学校です。
一次には1-1、1-2という二つの検査、二次には2-1、2-2という二つの検査とさらに面接、という流れで進んでいきますが、特に二次検査の難易度が高く、「これを時間内に解ける子は一体どんな子なんだ?」と疑問に思ってしまうような難しさです。
直近年度は、過去の県立問題と比較すると少し解きやすい問題も増え高得点勝負になってはいるのですが、小学校では「よく出来る」という層にいる子でも、よほど訓練をしない限りは太刀打ちできない学校と言えます。
社会分野では、複雑な割合計算が絡む問題が出題され、資料を正確に読み取ったうえで正確に、そして素早く計算する力が求められます。
理科分野については幅広く出題されますが、生活の延長にあるような現象をとことん突き詰めて分析し理解を深めていくような会話文が登場するため、理科に対する日頃の関心の高さや好奇心はもちろん、長い会話文からヒントを探し出す読解力が求められます。他のエリアの公立中高一貫校とは一線を画す難易度と言えます。
算数分野は、大人も頭を抱える難易度であり、私立中学受験の知識があった方が素早く解ける問題が多いです。もちろん丁寧に読めば小学校で習ったことをもとに解くことができますが、解法の引き出しの多さや、積み重ねてきた算数経験値の差によって時間内に解ける量の差が開いていくので、私立中学受験組の方が有利と言えます。
国語分野(作文)は、短い言葉で言い換えたり、複数の文章から共通する主旨を要約したりと、総合的な力(読解力・語彙力・表現力)が求められます。
言い換えは社会分野でも試されるので、過去問演習をすることで慣れていくと対応しやすいと言えますが、もともとの語彙量によって、感じる難易度に差が出ます。
作文は、オーソドックスなテーマなので書きやすいです。
市立稲毛国際
稲毛国際も、一次、二次と二段階で行われます。
一次は検査Ⅰと検査Ⅱが行われ、二次は検査Ⅲと面接が行われます。
検査Ⅰは文系、検査Ⅱは理系、検査Ⅲは作文と英語です。
まず検査Ⅰですが、短めの文章が出されたうえで、選択肢や記述問題、という非常にオーソドックスな国語の形式です。
記述が2問ほどありますが、それ以外は選択肢問題となっています。基本的な国語力があり、かつ、理由などを記述する問題の練習をしていくことで、対応できる難易度となっています。
社会分野については、千葉に関連する様々な施設や歴史、地理、輸出入といった問題が出題されるので、自分が住んでいる地域の特徴や、生産されているものの特徴など、地域に対する関心の高さが求められます。
暗記していないと解けないような問題はありませんが、小学校の教科書に載っていた資料から出題されることもあるので、小学校の範囲は教科書ワーク等を使ってしっかりと頭に入れておいた方が良いでしょう。
検査Ⅱについては、大きく分けて、算数の大問と、理科の大問という構成になるのですが、「理科っぽい切り口で中身はほぼ計算(算数)」というつくりになっていたり、会話や資料を読み取って選択肢を選ぶという読解力を試すような問題になっていたりするので、総合型とも言えます。
体のつくりや、太陽の動き、ふりこの周期など、土台となる知識があった方が早く正確に解ける問題が多いので、模試を積極的に利用して、抜けのある単元を探して補強していくようにしてください。
検査Ⅲは、放送による外国語問題と、作文が課されます。
外国語問題は、放送を聞いてその内容に合うものをイラストから選ぶ問題が基本で、小学校で習う外国語の授業である程度は対応できる難易度です。小学校で習う範囲の単語を覚えて聞き取れるようにしておくことはもちろん、「under」や「on」の違いなど、視覚的に理解するような学習も望ましいです。
作文に関しては、文章と、資料をもとにして自分の考えや根拠となる体験を述べていく形式です。難しすぎるものではないからこそ、正しい書き言葉で誤字脱字なく丁寧に書く練習をしておきましょう。
埼玉県にある公立中高一貫校
埼玉県にも、県立、市立、それぞれに公立中高一貫校があります。
・埼玉県立伊奈学園(北足立郡)
・さいたま市立浦和(さいたま市浦和区)
・さいたま市立大宮国際(さいたま市大宮区)
・川口市立高附属(川口市)
県立、市立、それぞれに異なる特徴があり、また、市立の中でもそれぞれで傾向、難易度が異なるエリアです。
もし複数の公立中高一貫校の中で迷っている場合は、学校の方針だけでなく、実際に解いてそれぞれの学校の難易度も把握したうえで候補を絞るのが良いかと思います。
共通するのは、1月に一次が行われ、一週間ほどしたらすぐに二次が行われるという点と、面接があるという点です。
一次については併願、つまり、大宮国際と浦和、というように二つの学校を受検できるという点は、他のエリアにはない特徴です。ただし、二次の日程は同じなので、最終的には一校にしぼる必要があります。
では、検査の特徴を見ていきましょう。
埼玉県立伊奈学園
伊奈学園は、一次は作文の検査、二次は面接が行われます。
検査は「作文」とひとくくりになっていますが、作文Ⅰと作文Ⅱがあり、分野としては、外国語の放送問題、国語・作文、社会、算数、理科…と、オーソドックスな適性検査に外国語が追加されているというつくりです。
難易度はそれほど高いわけではなく、よくあるテーマからの出題にはなりますが、「作文」と名付けてあるだけに、記述量が多いです。どの分野においても理由や方法を説明する、という指示問題があるため、誰が読んでも分かるシンプルな説明を書く練習が欠かせません。
一部、社会分野と理科分野では暗記型の問題も出題されるため、教科書ワークや中堅私立中学受験用の問題集を使ってインプット・アウトプットの反復をしておくと安心です。
さいたま市立浦和
全国的に見ても、最難関レベルの学校です。
県内の優秀な層が集まる学校であり、問題の難易度も、ライバルのレベルも相当に高い学校と言えます。
検査は一次に検査ⅠとⅡ、二次に検査Ⅲと面接が行われます。
検査Ⅰは文系問題で、前半は国語、後半は社会、という構成になっています。基本的に選択肢問題からの出題となりますが、国語の文章は小学生が一読して理解するには難しく、また、社会分野は怒涛の情報量を与えられるので、難解な文章に対して臆すことのない読解力の高さはもちろん、資料を見て状況を理解する一般常識力、そして社会分野では概算力(大きな桁やバラバラの数値の集合を見て、ざっくりと関係性を読み取る力)も求められる学校です。
検査Ⅱは、理系分野からの出題です。検査Ⅰでも一部英語の文章が登場しますが、検査Ⅱでも、英語の会話文が使われています。分野を問わず、総合的に高い力を持っている子を選ぼうとする狙いを感じます。
算数、理科、ともに、適性検査でよく見るジャンルからの出題ではありますが、基本的に会話文や実験の説明が1ページほど続いたうえでの選択肢になるので、大事なところに線を引きながら落ち着いて情報を整理していく必要があります。
特筆すべきは、検査Ⅲです。大宮国際の検査Cと形式は似ていますが、複雑な計算も求められることもあり、相当な慣れが必要です。近年は英語との組み合わせになっていますが、「発表原稿を用意する」という形式としては変わらないので、時間内に全ての原稿を仕上げられるようになるまで、徹底して過去問演習をして慣れておきましょう。
さいたま市立大宮国際
大宮国際は、一次に検査A・検査B、二次に検査C、集団活動が行われます。
検査Aはまず放送による外国語問題です。放送を聞いて、内容に合うイラストを選んだり並び替えたり、といった選択型の問題です。
大問2からは、総合型の問題となっています。良問揃いの学校で、丁寧に読む、情報を整理する、図を活用する、正確に計算する、といった力をバランスよく持っていることが求められます。
決して難しいわけではないのですが、早合点してしまうと引っかかる問題が多いので、日々の取り組みに対する慎重さや丁寧さ、見直しの姿勢なども得点に影響します。
検査Bも分野を問わない複合型ですが、与えられた資料を分析・考察する力や、少し難しい国語的文章も落ち着いて読み取る力が求められます。
検査Cは、市立浦和の検査Ⅲとタイプは似ていますが、どちらかというと社会分野や国語分野からの出題であり、社会課題や、自分との向き合い方といったテーマから出題されることが多いです。ある程度は型に沿った書き方が出来る検査なので、練習量の差が点に出ると言えます。
川口市立川口高附属
令和3年に開校したこともあって、施設も新しく、今後の進学実績に期待が寄せられている学校です。倍率は5倍程度と高くなっており、傾向をよく把握して対策をすることが望ましいです。
一次には検査Ⅰと検査Ⅱ、二次には検査Ⅲと作文、面接が実施されます。
検査Ⅰは、国語的文章の読解と、社会分野の資料読解問題で構成されています。どちらの分野も、文量に対して情報量が多く、丁寧に主旨を読み取らないと当てずっぽうで選択肢を選ぶことになり、記述でもズレが出てしまいます。
ザッと読んで「何となく」の読解をするのではなく、読んだ後に自分の言葉でも要約できるような正確な読み取り練習をしていくと良いでしょう。
検査Ⅱは、理系分野です。記述はほぼ見られませんが、問題数が多いため、50分で20問弱を解ききる回転の速さが求められます。
また、グラフ作図問題も出題されるため、他県の問題も使って慣れておく必要があります。
特筆すべきは、検査Ⅲの難易度の高さです。
私自身、オンラインサロンで川口の問題を解説することがあるのですが、解説だけで何ページにもおよび、大人でも困ってしまうような難易度だと感じます。千葉県立の二次や、横浜市立サイエンスフロンティアにタイプは似ており、小学生にはあまり馴染みのないような専門用語やグラフも多数登場します。
また、検査時間が60分と長い点も大きな特徴です。
非常に難易度の高い理数系問題に60分向き合うだけの学習体力は、短い期間では身に付きません。応用問題や発展問題と向き合う粘り強さ、最後まで諦めずに資料から情報を探す根気強さが求められる学校です。
まとめ
さて今回は、東京、神奈川、千葉、埼玉の公立中高一貫校で行われる検査の特徴と対策について、紹介しました。
どの学校もそれぞれに個性がありますが、そうは言っても、部分的に見れば似ている学校もあるため、そろそろ時期的にも色々な学校の過去問に挑戦して適性型への対応力を磨いていきたいところです。
間もなく夏休み。次回は、秋の模試ラッシュに向けて、目標設定のポイントについてお伝えします!
▼公立中高一貫校の受検体験記もぜひご覧ください
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます