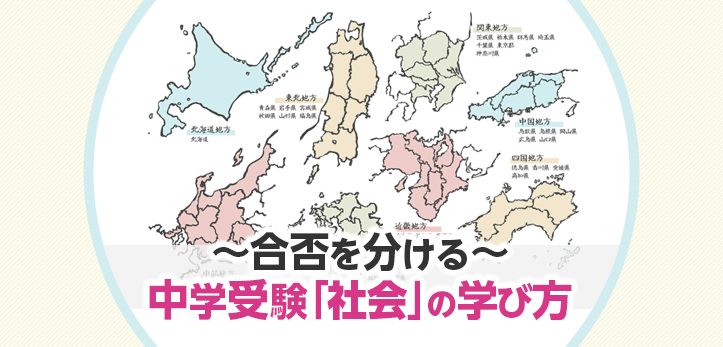
合否を分ける中学受験「社会」の学び方(10)|年号の暗記から逃げない
こんにちは。中学受験専門の個別指導教室「SS-1」教務主任の馬屋原です。
前回は、歴史に強くなるための秘訣として、それぞれの時代の『イメージ』を持つことが大切だ、というお話をさせていただきました。
さて、歴史の学習についてお話しているときに頻繁にいただくご質問があります。
今日はそれにお答えします。
年号は覚えた方がいいのか? 覚えなくてもいいのか?
年号は覚えた方が良いですか? という質問に結論から申し上げます。
「Yes」です。年号は覚えなければなりません。
もちろん、いくつ覚えるべきかは受験校によって異なります。
しかし、多かれ少なかれ、歴史に強くなりたいのであれば、年号暗記には正面から向き合う必要があります。
受験で勝つためには年号の暗記が必須
積極的に年号を暗記した方が良い理由はいろいろあります。
あえて少し変わった理由を挙げるならば、
「SAPIXが年号を○○○個叩き込むから」(念のため個数は伏せます)
です。
必ずしも年号を暗記する必要はない、と主張する社会の先生もいらっしゃいます。
- 年号そのものを問う問題は少ない
- 年号を暗記するよりも、出来事同士の因果関係を理解する方が大切
というのがその主張の主な根拠かと思われます。これはたしかに正論です。
ただ、歴史のテストは、結局のところ、
「○○は何時代のいつ頃のことか」
がわかれば解ける問題がかなりの量を占めており、
年号を暗記している受験生は、この部分の判断が圧倒的に速く、そして正確なのです。
つまり、得点力が高い。
SAPIX生が全員、年号を○○○個覚えた状態で入試に臨むとは考えにくいですが、少なくとも上位生は覚えているでしょう。
さらに、年号に関する知識は、覚えれば覚えるほど、「○○は××の□年前」といった形でもって加速度的に増えていきます。
たとえば、中学入試の歴史ではかなり細かい部類に入る「琉球王国成立」の年、「1429年」をいきなり覚えるのはきついかもしれません。多くの場合、覚える必要もないでしょう。
ただ、「正長の土一揆」の年、「1428年」をしっかり覚えている子の頭には、「はいはい、正長の翌年ね」と、あっさり入ったりもするのです。
難関校の合格を勝ち取る、ということは、このようにして鍛えられてきた受験生たちと戦って勝つということです。
したがって、「年号を覚えた方が良いですか?」というご相談には、私は迷わず「はい」とお答えしています。
とはいえ、ただ「覚えろ」とだけ叫ぶのでは指導者として失格です。
次回は「年号」をどうやって覚えていくか、という点について考えてみたいと思います。
またお越しいただければ嬉しく思います。
※この記事は「マイナビ家庭教師」Webサイトに掲載されたコラムを再編集のうえ転載したものです
■合否を分ける中学受験「社会」の学び方 バックナンバー
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(26)|世の中について語れ! 麻布中 平成29年度「社会」
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(25)|東京観光のススメ!? 開成中 平成29年度「社会」
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(24)|社会の記述問題は、頭が良い子ほど得点できない
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(23)|過去問の「直し」はどうすれば良い?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(22)|過去問はいつ、どこから始めて、何年分解くのか?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(21)|過去問は何のために解くのか?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(20)|「メモリーチェック」や「四科のまとめ」は解けないのが普通です
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(19)|夏休みの旅行どうしますか?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(18)|SAPIXに通う6年生が夏期講習の最初の4回を絶対に休んではいけない理由
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(17)|7月10日の夜は親子で選挙速報を見よう!
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(16)|SAPIX 7月組分けがやってくる!
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(15)|最悪なノートの書き方とは?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(14)|「公民」って結局何を学ぶの?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(13)|塾の理屈、子供のキモチ
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(12)|「公民」を効率よく学習するには?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(11)|ゴロ合わせすら覚えたくない!?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(10)|年号の暗記から逃げない
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(9)|時代ごとのイメージを持つ
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(8)|これだけは絶対に覚えておきなさい
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(7)|直前なのに真っ白! 入試直前期の社会の学び方
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(6)|日本歴史の時代名、全部言えますか?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(5)|都道府県パズルでタイムアタック!
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(4)|すべての始まりは都道府県名の暗記
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(3)|「テストになるとできない病」を克服しましょう!
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(2)|お子さんは「覚え方」を覚えていますか?
- 合否を分ける中学受験「社会」の学び方(1)|暗記だけでは対応できない問題が増えている
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

