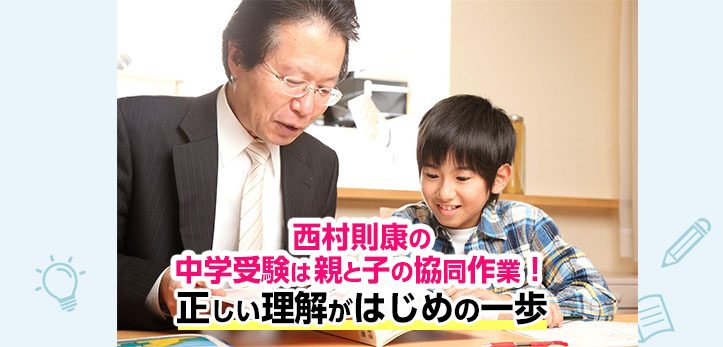
子どものやる気を奪う間違った親の声かけ|中学受験は親と子の協同作業! 正しい理解がはじめの一歩 Vol.36
毎日勉強をしているのに、なかなか結果に結びつかない。つまらない計算ミスをして、得点を落としてしまう……。そんなわが子を見ていると、親はついあれこれと言いたくなります。でも、そんな親御さんの一言が、子どものやる気を奪ってしまうかもしれないのです。
子どもの欠点ばかりを指摘する“受験親”になっていませんか?
母親:「なんでこんな点数なの?」
子:「だって、時間が足りなくなって、焦っちゃったから……」
母親:「だから、ちゃんと落ち着いてやりなさい!って言ったじゃないの!」
どこのご家庭でもありがちなやりとりですよね。親御さんからしてみれば、「毎日たくさん勉強をしているのに、なぜこんなつまらないミスをするの? 悔しくないの?」という思いがあるのでしょう。だから、つい声を荒げてしまう。
でも、こうしたダブルバインドの質問は、子どもを追い詰めます。ダブルバインドの質問とは、どう返答しても叱られることが予測できる質問を投げかけ、相手に矛盾やストレスを感じさせる行為。子育て中の親が無意識にやってしまいがちです。
ここでは、まずお母さんが子どものテストの結果に対しての不満を伝え、その理由を子どもに問いただしています。そして、その理由を子どもが答えますが、それに対してさらにダメ出しをしています。こうした問いただし方は、子どもがどのように答えても、結局叱られるという展開になります。
親御さんからしてみれば「ちゃんと落ち着いてやりなさい」と言うのはアドバイスかもしれませんが、それを言われた子どもは「くどくど叱られた」と感じるだけです。
子どもに響く声かけとは?
何を言っても叱られる。こうした質問を続けていくと、やがて子どもは2つの反応を見せるようになります。
ひとつは、「うるさいなぁ〜!」と反抗的になる。幼い頃は親の言うことを素直に聞いていた子も、小学5〜6年生頃になると自我に目覚め、こうした親の矛盾を疑問に思ったり、うっとうしく感じたりするようになります。ここで、「うるさい! くそババァ!」とバトルになることもあります。これはある意味、正しい成長の証と言えますが、学習へのモチベーションを著しく下げてしまう心の動きです。
もうひとつは、何を言われても黙るケース。親からすると、素直に聞いているように見えるため、ついダメ出しを続けてしまいますが、それを言われ続けている子どもは、心の中で怒りを貯め込んでいます。そして、親のちょっとした言葉に過剰反応するようになります。それが受験が終わっても続き、ある日突然感情を爆発させてしまうことがあります。
いずれにしろ、こういう言葉がけは、子どもにとって嬉しいものではありません。もし、同じメッセージを伝えるのであれば、お子さんの欠点を指摘するのではなく、なぜそうなったのかを一緒に考えてあげてください。
母親:「今回のテストは残念だったね。何が原因だったと思う?」
子ども:「上から順番に解いていったら、時間がなくなってきて、途中から焦って解いちゃったんだよね」
母親:「そうか、時間が足りなくなって焦っちゃったんだね。じゃあ、時間があれば解けたと思う?」
子ども:「解けた問題もあった」
母親:「そうなんだね。それは悔しいね。じゃあ、これからどうやったらうまくいくか、一緒に時間配分を考えていこうか」
いかがでしょう? 前向きに考えることができますよね。このように、同じことを伝えるにも、相手に響く声かけと相手のやる気を奪う声かけがあるのです。
勉強のことでいつも叱られると「勉強=嫌なもの」になる
中学受験の勉強が始まると、親御さんは勉強のことばかり口にするようになります。しかも、どちらかといえば、叱ることのほうが多くなります。すると、子どもは「勉強=嫌なもの」になってしまいます。
一方で、私が最近気になっているのは、中学受験をする家庭では、受験勉強だけが重要視され、あとの生活のルールが疎かになっている点です。勉強をしているときの姿勢が悪いと注意をするのに、食事のときの姿勢についてはあまり指摘をしない。こうした親の姿勢に疑問を感じています。
勉強だけが特別ではなく、勉強も生活の一部です。勉強のことばかり口にしてしまいがちな受験期こそ、親として生活についてもきちんとしつけやアドバイスをしましょう。そうやって「生活全般を良くしよう」という声かけを意識すると、勉強だけが特別なものという感じ方はなくなります。
親御さんから見ると幼い子どもでも、受験生は自分が勉強をしなければいけないことは十分にわかっています。自分ができない行動に対して、「なんとかしなきゃ!」という思いも持っています。
だからこそ、子どもの欠点を指摘するような言葉や、勉強だけが特別といった態度を見せることはやめましょう。あまり勉強、勉強と言うと、子どもは勉強が嫌いになってしまいます。今の頑張りを認め、応援してあげましょう。そして、子どもが何か困っていたら、これまでの努力を認めながら一緒に解決策を考えてあげましょう。
これまでの記事はこちら『中学受験は親と子の協同作業! 正しい理解がはじめの一歩』
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

