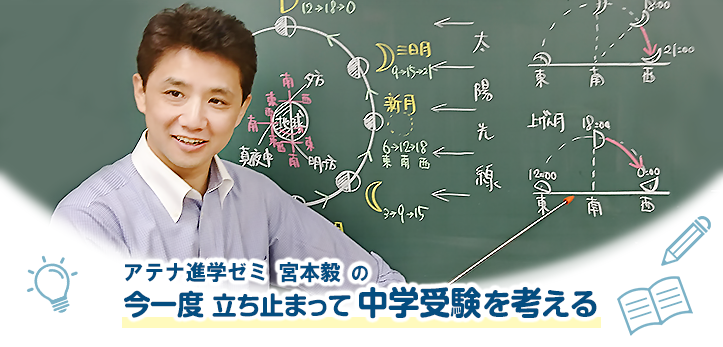
時間の無駄かも? 塾の保護者面談でありがちな“もったいない”質問|今一度立ち止まって中学受験を考える
「成績がぜんぜん上がらないのですが、どうしたらいいですか?」 塾講師をしていると、こうした質問を受けます。しかし、あまりにも抽象的すぎて、返答に困ることがあります。もし仮に返答できたとしても、その返答は漠然としがちです。面談の時間を有意義にするには質問の工夫が必要です。
Contents
漠然とした質問 ―― 「国語ができないのですが、どうしたらいいでしょうか?」
「偏差値を上げるには何を勉強させればいいでしょうか?」
「国語ができないのですが、どうしたらいいでしょうか?」
塾の面談では保護者からこうした質問をよく受けます。私はこうした質問を受けるたびに返答に悩んでしまいます。なぜなら普段から学習のやり方を伝えているからです。
大手塾・中小塾に限らず、常識的な塾講師であれば、科目ごとにやるべきことを本人や保護者に伝えているでしょう。たとえば国語なら「まずはきちんと音読をさせましょう」とか「語彙力をつけるためには、わからない単語は出てきたら国語辞典を引いて、付箋を貼っておきましょう」とか「宿題の解き直しでは解答解説の解説部分を必ず読ませましょう」といったように、学習の仕方に細かい指示を出しているはずです。
「うちはちゃんとやっています」という親御さんもいらっしゃいますが、生徒を見ていると、そうは思えないことが珍しくありません。よくよく話を聞くと言われたことはやらずに、ただ量をこなす勉強をしていて、やっている気分になっていたというご家庭もあります。
わが子の成績を上げたければ、まずは講師のアドバイスに素直に耳を傾け、そのとおり実行してみることです。それでも成績が上がらないなら相談が必要ですが、具体的な対策を講じるためにも、できるだけ具体的に相談することをおすすめします。
たとえば、「うちの子、小説文が苦手なのですが、宿題以外で何をやらせたらいいですか?」とか「志望校に対して偏差値が10足りていないのですが、合格に向けてどの科目をどのように上げていけばよいですか? そのためには夏期講習はどの科目をどう学習すればいいでしょうか?」といったように、まずは現状を説明し、そのために何をどうやればいいのか具体的に聞いてみるのです。そうすれば、講師も具体的な対策を考えてくれます。
答えようのない質問 ――「ズバリ合格可能性は○%ですか?」
漠然とした質問のほかに、困ってしまうのが次のような答えようのない質問です。
「この学校はうちの子に合っていると思いますか?」
「ズバリうちの子の志望校合格は何%くらいでしょう?」
合格の可能性が知りたいのであれば、模試の「合格可能性」の欄を見るのが現実的です。そこに書かれている数値以上の数値を塾講師からなんとか引き出そうとされているのでしょうが、極めて難しい話です。希望的観測を入れてしまうと油断を招きかねません。
また、どの学校がうちの子に合うかなどは塾講師にはわかりません。親以上に子どものことを知っている人はそういません。塾講師も無責任なことは言えないですから、あたり触りのないその学校の特徴を教えるくらいしかできません。
でも、同じことを聞くにしても、質問の仕方を変えるだけで効果は違ってきます。たとえば「模試の結果を見ると、合格可能性20%なのですが、過去問では算数の相性がいいみたいです。入試との相性の要素を加味すると可能性は変わってきますか?」という質問をしてみます。
すると、講師はその学校の問題傾向と照らし合わせながら、アドバイスができるでしょう。模試に出題するようなオーソドックスな入試問題を出す学校であれば、模試の結果はかなり現実味があります。でも、思考系や記述系の問題を多く出す学校の場合は、独自の入試スタイルなので、模試の結果はあまり参考になりません。むしろ、過去問で点が取れているほうが合格の可能性は高くなります。このように、質問の仕方によって、講師もアドバイスがしやすくなるのです。
塾を敵に回すような質問 ―― 「いったい何を教えているんですか?」
「成績がぜんぜん上がっていないのですが、塾はいったい何を教えているんですか?」
「先生の授業がわかりにくいと言っているんですが、どうなっているんですか?」
ときどきこういう質問の仕方をする保護者がいますが、子どもの成績不振を塾のせいにしたり、講師のせいにしたりしても仕方がありません。塾の先生も人間ですから、言われて嬉しいことと嫌なことがあります。中学受験で塾を目の敵にしてもお互いにあまり良いことはありません。やはり「ウィンウィン」の関係を目指すべきでしょう。塾に通っているのに、成績が上がっていないことが心配だったら、こんな感じで相談をしてみてください。
「なんだか授業を一度で理解することが難しいようです。時間をとらせてしまいすみませんが、授業後に個別で教えていただくことはできないでしょうか?」
このように言われて嫌な感情を抱く講師はいないでしょう。むしろ、生徒をなんとか伸ばしてあげたいと思うはずです。塾の講師は基本的には面倒見がよく、誰かのために役に立ちたいと思っています。言い方ひとつで相手の心を動かせるのであれば、質問や相談の仕方を工夫したほうがいいでしょう。中学受験で親ができることは限られています。そのなかでも塾への質問、相談の仕方はとても重要であることを知っておいてほしいと思います。
これまでの記事はこちら『今一度立ち止まって中学受験を考える』
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

