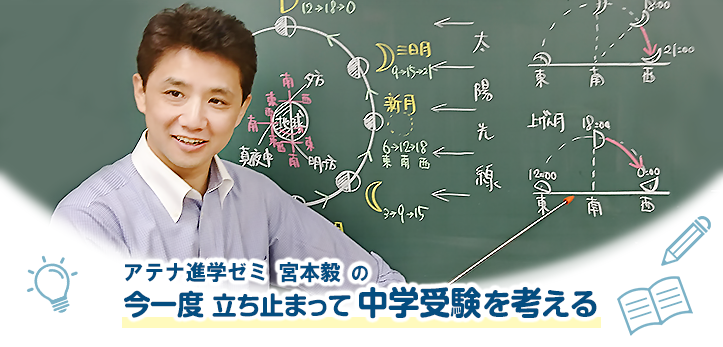
勉強のモチベーションを上げるのに、ご褒美とペナルティーは必要?|今一度立ち止まって中学受験を考える
「自分から進んで勉強してくれたら……」「模試前なんだから、もう少し頑張って勉強して欲しい」など、なかなかやる気を見せない、行動に移さないわが子にモヤモヤしている親御さんは多いことでしょう。そんなときに、「次の模試でいい成績をとったら○○を買ってあげる」とご褒美を提示したり、「次の模試でクラスが下がったら、夏の旅行はナシよ」とペナルティーを示唆したりすると、子どもはどんな反応を見せるのでしょう? 今回は学習におけるご褒美とペナルティーについて考えます。
「勉強したらご褒美」は一概にNGではない
「さぁ、今日は大掃除! ちゃんと頑張ったらご褒美に300円あげるわよ!」
こう言うと、大抵の子どもは張り切って掃除のお手伝いをするでしょう。子どもに何かをさせたいとき、ご褒美は効果大です。では勉強をさせたいときは、どうなのでしょうか?
今から30年ほど前、私が大学で教育心理学を学んでいた頃は、「勉強したときにお金でご褒美を与えると、子どもはその刺激に慣れてしまい、やがてしなくなる。勉強させるためには金額をつり上げていかなければならなくなり、そのうちご褒美効果がなくなってしまう」と習いました。どちらかというと「お金をご褒美に勉強させることは、すべきではないこと」と捉えられていたのです。
ところが最近の研究では一概にNGと言えない面も示されています。ハーバード大学のローランド・フライヤー教授によると、アメリカの小学2年生の子ども達に、「本を1冊読み、その内容に関する質問に正しく答えられれば200円もらえる」という実験を試みたところ、子ども達の学力が向上したそうです。この実験で子ども達は平均1400円の報酬を得たそうですが、1回200円という少額で、しかも途中でその金額が上がらなくても、平均して7回は継続して読書を続けられたことになります。平均して7回継続という数字が多いか少ないか、もちろん両論あるでしょうが、必ずしも「お金で釣って学習させると、ご褒美効果がなくなってしまうから、絶対にやらないほうがいい」というわけではないということです。
もうひとつ面白いデータがあります。シカゴ大学のスティーヴン・レヴィット教授が、シカゴの小中高6500人の生徒を対象に行った実験は、「もし前回のテストより好成績を残せば、300円程度のお金やおもちゃがもらえる」というものでした。このとき、最も効果があった報酬のあげ方は、テストの前に報酬を先渡ししておいて、基準の成績がとれなかった場合にはその報酬を取り上げるというものでした。これは人間行動でいう「損失回避」というもので、人間は利益を得るよりも損失を被ることを恐れるものなのです。
また、報酬を与えるタイミングについてですが、報酬を先渡しにはしない場合、渡すタイミングはテスト終了直後が最も効果的で、テストから日が経つにつれて効果が薄れていくことがわかりました。お金やモノをご褒美とするのが必ずしも、悪しきことではないということです。あげるものの内容、あげるタイミングがポイントなのです。
高額なものを与えると、「次はもっと」と期待してしまう
子どもの勉強にご褒美をあげる・あげない問題はいつも賛否両論ですが、私個人としては、ご褒美をあげてもいいと考えています。子どものうちから「もっと知りたい」と勉強を頑張ってくれたらよいですが、どうしても勉強に対するモチベーションが上がらないなら、モチベーションを上げるための”最初の手段(きっかけ)”として、ご褒美をあげてもよいと思っています。それによってモチベーションが上がり、頑張って勉強したら成績が上がった。成績が上がって嬉しかったから、もっと頑張ってみた、と自分から頑張れるサイクルを作れることもあるからです。
ただし注意も必要です。やはり、小学生の子どもに「高額なもの」は与えない方がいいでしょう。たとえば「今度の模試でクラスアップしたら、スマホを買ってあげる」というのは、おすすめしません。やがて子どもの要求がエスカレートし、高額なものをくれないと勉強をしなくなってしまう危険性があるからです。
また、ご褒美を与える際には、勉強の時間に影響を与えないものを選びましょう。「ちゃんと宿題を終わらせたらゲームをしていいよ」「マンガを読んでいいよ」としてしまうと、子ども達はゲームやマンガに夢中になってしまいがちです。よくテレビ番組などで「東大生はゲームをよくする」などという話が取り上げられたりしますが、「ゲームをしていたから東大に入れた」のではなくゲームをしていても自分で切り上げられる自制心を持っていたからなのです。誤解しないようにお願いしたいです。小学生の時点でそういった自制心を持つ子もいますが、やはり少数派だといえるでしょう。自分でコントロールできるようになってほしいという親心もわかりますが、なかなか切り上げられない子であるなら、ゲームやマンガを交換条件にしたご褒美は提示しない方が賢明です。
「高額なもの」「勉強時間に影響を与えるもの」以外であれば、ご褒美は何でも構いません。大人からすると意外に思えるかもしれませんが、小学生の子どもの場合「目標を達成したらシールを貼ってあげる」というレベルの報酬でも十分モチベーションを上げることができます。この場合、報酬というとニュアンスが違うのかもしれませんが、勉強を頑張った“しるし”や、“象徴”として、シールを活用するのは、モチベーションを高める有用な手段の一つです。実際に私の塾でも、宿題をやったらその証(あかし)として、シールを貼っています。特に女の子はかわいいシールを貼ってあげると喜ぶものです。
また、ご褒美は毎日決まったものを与え続ける必要はありません。学習にはメリハリも大事ですから、「次の模試を頑張ったら、日曜日に遊園地に行こう!」「焼き肉を食べに行こう!」といった具合に、ご褒美にメリハリをつけてあげるのもよいと思います。
ペナルティーは子どものやる気を奪う
では、学習に対するペナルティーはどうでしょう?
前出のスティーヴン・レヴィット教授の実験によると、「勉強をしないと、○○禁止/○○させない」といったペナルティーは、学習意欲を上げるのに効果がなかったと発表しています。ペナルティーはかえってやる気を削いでしまうようです。
ただ、これはペナルティーとはちょっと違うのですが、私が子どもの頃、わが家には「夕飯の前に宿題をやること。夕飯は宿題が終わってから」という暗黙の決まりがありました。自分がダラダラしていたら、夕飯の時間が遅くなってしまう。それは嫌だな……と、夕飯前に必ず宿題を終えていました。そうすることで、自然と学習習慣が身に付きました。
このように家庭内でルールを作っておくと、効果が高いと思います。でも「お風呂の前に」では、子どもには響かないと思いますので、「夕飯前に」とか「好きなテレビ番組を見る前に」とか、子どもにとって大事な時間の前までに終わらせるというのがいいでしょう。
なかなか勉強を始められない子、勉強に対するモチベーションがイマイチ上がらない子には、ご褒美作戦と家庭内ルールをぜひ試してみてください。
これまでの記事はこちら『今一度立ち止まって中学受験を考える』
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

