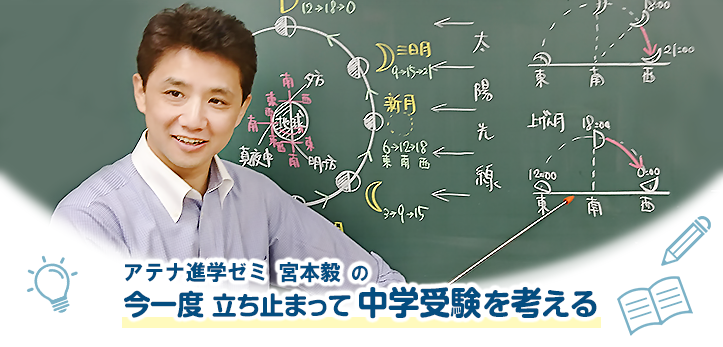
中学受験 社会&理科を得意な子にするには|今一度立ち止まって中学受験を考える
社会・理科は暗記科目と考える親御さんは少なくありません。しかし、中学入試に出題される範囲は膨大で、丸暗記だけではとても追いつきません。この2科目を得意にする秘訣は、ズバリ興味関心を持たせること。では、どのような方法が有効なのでしょうか?
道路地図や鉄道路線図で地理を学ぶ
中学受験の社会は地理、歴史、公民の3分野が出題されます。なかでも子ども達にとって負担が大きいのが地理です。都道府県の位置や各地の気候、農業、産業など覚えるべきことがたくさんあるからです。
地理の学習に使われるのが、学校や塾で配布される地図帳です。しかしこの地図帳は、河川の名前、山地・山脈名、平野・盆地名、都市名はもちろん、農業、産業などあらゆる情報が詰め込まれていて大変読みづらく、情報過多で頭に入ってこない難点があります。そこで、私は日本道路地図や鉄道路線図などで地理を学ぶことをおすすめしています。
これらの地図は、道路や路線以外の情報は書かれていないので、読みやすく、自分で必要な情報を書き足せます。また、情報満載の塾の地図帳は、どこか難しく感じるものですが、道路地図や鉄道路線図なら旅行で使ったことがあるので身近に感じられ、学習のハードルがグンと下がります。
鉄道路線図は山地・山脈や川などの記載もないですが、そうした情報は駅名から類推することも可能です。鉄道好きの小学生は案外多く存在していて、たいてい「地理は好きだが、歴史は苦手」なのですが、歴史上の地名などを鉄道路線図で確認したりすることで、歴史への興味が湧いたりするものです。要は「興味喚起」さえできてしまえば、後は子どもたちが勝手に覚えていきます。
たとえば、歴史でも地理でも出てくる大山古墳。これは仁徳天皇の陵墓で世界遺産にもなりました。最寄り駅のひとつが「三国ヶ丘」駅で、南海鉄道高野線とJR線が交わるターミナル駅です。この「三国ヶ丘」という駅名は、かつて摂津国・河内国・和泉国の三国が交わるところから取られました。
摂津の国は聖徳太子が四天王寺を建て、大化の改新以後、難波宮という首都がおかれた場所でもあります。河内国は鎌倉幕府を滅亡に追いやった立役者の一人、楠木正成の出身地です。南海鉄道高野線の終点には、空海が開山した高野山金剛峰寺があります。
こんな風にして、歴史と鉄道路線図をリンクさせれば、歴史に興味を持ちやすいでしょう。社会の学習に道路地図や鉄道路線図を活用しない手はありません。
歴史学習は漫画や大河ドラマを活用。楽しみながらストーリーで学ぶ
地理同様に覚えることが多いのが歴史です。歴史は好きな子にとっては楽しい分野ですが、そうでない子にとっては、負担の大きい分野です。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

