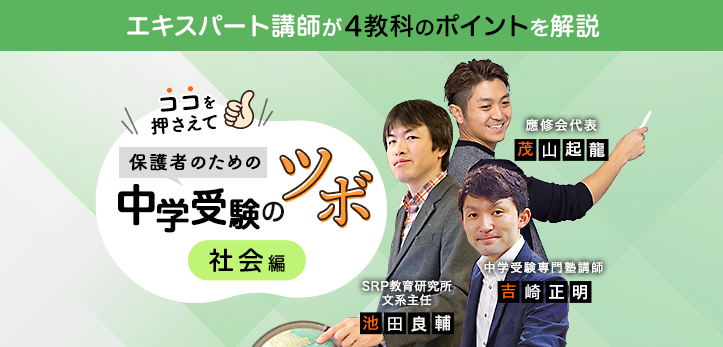
【小4社会/製鉄業】歴史をさかのぼりつつ、製鉄のイメージを膨らませよう|中学受験のツボ[社会編]
専門家・プロ
2022年12月10日
池田良輔
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 社会編 は吉崎正明先生、池田良輔先生、茂山起龍先生が担当します。
- 社会以外の3教科はこちら -
製鉄業について地理の授業で習うときは、「鉄鉱石・石炭・石灰石を原料としている……」「かつては『産業の米』と呼ばれ、重工業の中心だった……」といった“つまらない説明”を聞いて終わりがちです。
しかし、これでは記憶に残りにくく、おもしろくもありません。
一方で「昔はどうやって鉄をつくっていたのかな?」と歴史をさかのぼってみると、楽しく学習を進められますよ。
製鉄業の歴史
青銅器などと同じく、製鉄技術は弥生時代の頃に大陸から伝わったと言われています。鉄器は青銅器と比べると硬いため「武器」や「農具」として、青銅器は「祭器」として使われました。
鉄は、鉄鉱石と石炭(コークス)を炉の中に投入して高温にした後、鉄鉱石から酸素を取り除き、純度の低い鉄(銑鉄)を取り出すことでつくられます。
現代では、不純物を取り除くために「石灰石」も炉に投入されていますが、このようなつくり方になったのは江戸時代から。それまでは鉄鉱石も石炭も本格的な採掘はおこなわれておらず、鉄鉱石の代わりに日本各地の山や海岸で採れた「砂鉄」を使い、さらには石炭のかわりにバーベキューで使うような「木炭」を使っていたんですね。
砂鉄は、かつては出雲地方(島根県)の辺りで多く採れたため、
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

