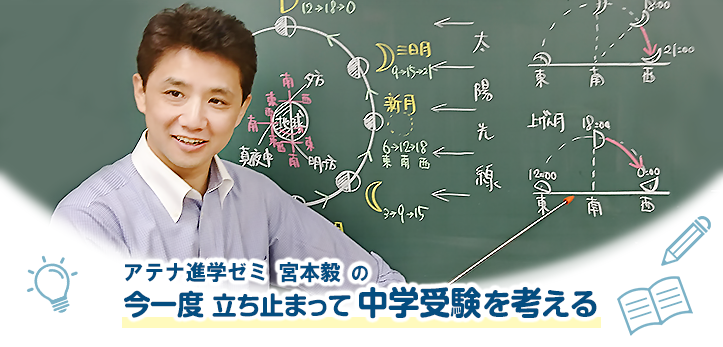
「リビング学習」がいいって聞くけど、本当に効果はある?|今一度立ち止まって中学受験を考える
リビング学習を推奨する本や雑誌の特集がよく見られるようになりました。実際、お子さんをリビングで勉強させているというご家庭も多いことでしょう。しかしリビングで勉強をさせれば、子どもが自ら進んで勉強を始め、成績が上がるということではありません。やり方を間違えれば、効果は望めないのです。では、どのような点に注意が必要なのでしょうか?
リビング学習の3つのメリット
リビング学習をさせることのメリットとして、次の3つがあげられます。
- 子どもの学習状況を親が把握できる
- 子どものわからないところを親がすぐにフォローできる
- 親子のコミュニケーションの頻度が上がる
小学生のうちは、自分の部屋が用意されていても、そこで一人で勉強するのを嫌がる子は少なくありません。やはりまだ幼いので、誰かがそばにいないと不安に感じてしまうのでしょう。子どもは心が安定していないと、勉強に向かうことができないものです。
親の立場からすると子どもがリビングで勉強をしていれば、食事の支度で忙しいお母さんも、手を動かしながら子どもの様子が見えます。頑張っていたらすぐにその場で褒めてあげられるし、困っていたら助けてあげることができます。また、子どももわからないことがあれば、すぐにお母さんに聞くことができます。何よりも大好きなお母さんがそばにいて、コミュニケーションをとりながら勉強するのが楽しい。リビング学習をさせる一番のメリットは、子どもの心が安定することです。
リビング学習の効果は親の行動次第
リビング学習の効果は、親御さんがちゃんと関わってあげられればこそ生まれるものです。子どもがリビングで勉強しているのに、親がテレビを観ていたり、スマホをいじっていたりしていては、子どもは勉強に集中できません。ずっと横についている必要はありませんが、子どもが集中しているときは、親も「今は子どもが勉強中」ということを頭に入れ、見守る姿勢を持つ必要があります。食事の支度をしながらでもいいから、しっかり様子を見てあげてください。同じ机で読書をしたり、資格の勉強をしたりしながら、見守るのもいいでしょう。大事なのは勉強している子どもの気持ちに寄り添うことです。
前述したリビング学習のメリットのひとつに、「わからないところを親がフォローできる」点を挙げました。リビング学習をしていると、当然お子さんから「ここがわからない……」などといった話を聞くことになるでしょう。このとき、親御さんがまったく何もアドバイスできないのも、やはり困ります。一から十まで手取り足取り親が教える必要はありませんが、たとえば基礎問題の考え方や語句の意味くらいは教えてあげたり、教材やノートを一緒に振り返ったりするなどといったことは、ぜひフォローしていただきたいところです。
また、リビング学習をするのであれば、親御さんもお子さんがどんな勉強をしているのか、ぜひ知っておいて欲しいと思います。お子さんがどんな勉強をしていて、どんな点でつまずいているのか、親御さんがまったく理解できていないのに、成績の良し悪しだけを指摘するのは酷な話です。中学受験の勉強を、親がすべて理解する必要はありませんが、私のこれまでの経験から言うと、親御さんが子どもの勉強に関心を持ち、子どもと一緒に勉強をしているご家庭は、お子さんの成績も上がっていきやすいと感じます。
もちろん、今の中学受験の学習内容はとても難しくなっていて、親御さんもわからないことが出てくるでしょうし、カリキュラムが進むにつれて、親御さんがアドバイスできることは、少なくなっていくのが自然です。そういったケースが増えてきたら、わからない問題は塾の先生に聞くように促すのが得策です。ただ、お子さんのタイプによっては、塾の先生に質問するのが苦手ということが結構あります。そんなときは、親御さんから塾の先生に『うちの子、こういったタイプの問題が苦手みたいで、教えてあげていただけませんか?』などと、お願いしてみましょう。
子どもにとって「良い学習環境」は?
リビング学習の効果は親御さんの関わり方で大きく違ってきます。極端な話ですが、子どもが気持ちよく勉強できるのであれば、どこで勉強をさせても構いません。自分の部屋で勉強をした方が落ち着くのであれば、それでいいのです。
「小学生の子どもはリビング学習がいいと本に書いてあったから」といって、みんながみんな「リビング学習がいい」とは限りません。小さなきょうだいがいる場合は、騒がしくて集中できないこともあります。また、親御さんがそばにいると、子どものダメなところばかりに目が行き、「ダラダラ勉強していたら合格できないわよ!」「なんでこんな問題が解けないの……」と小言ばかりが増えてしまうことがあります。そうなってしまうと、子どもは「どうせ僕は勉強ができないんだ……」と自信をなくし、勉強に対するモチベーションも下がってしまいかねません。
良い学習環境とは、子どもが自分から勉強に取りかかり、気持ちよく勉強できる環境です。リビング学習を取り入れる際も、そういった観点を大切にして頂きたいと思います。親が監視するのではなく、放っておくのでもなく、“見守る”姿勢を持つようにしましょう。
これまでの記事はこちら『今一度立ち止まって中学受験を考える』
※記事の内容は執筆時点のものです
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

