
【小6算数/平面図形】図形を描く順番の考え方と手順|中学受験のツボ[算数編]
専門家・プロ
2022年9月21日
杉本啓太
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 算数編 は杉本啓太先生と有賀隆夫先生が担当します。
- 算数以外の3教科はこちら -
こんにちは、杉本です。
今回のテーマは、「図形を描く順番の考え方」です。
先月の記事「問題を解くヒントは「図形を描く順番」にあり」で「複雑な問題を解くときには、図形を描く順番を意識するのが有効な場合がある」とお話ししました。
今回はその具体的な方法について、例題を解きながら「最初に引く直線はどれかな?」と、具体的な手順を解説していきます。
ぜひご家庭でも、お子さんと一緒に実際に図を描きながら「ああ、この図はこういう順番で描かれたんだ!」と実感してもらえればと思います。
Contents [hide]
- 「最初に与えられる図」から一つひとつ直線や点を追加しよう
- 実際に図を描く順番を確認しながら長さを求めてみよう
- 例題2
- まとめ
「最初に与えられる図」から一つひとつ直線や点を追加しよう
まずは、長さを求めるところは考えず、図を描く順番を考えるトレーニングだけやってみましょう。
そのときに気を付けてほしいのは、以下の3点です。
① 「最初に与えられる図は何か」を確認する
② 直線や点は一つひとつ追加する
③ 直線を引くときは「すでにある2点を結ぶ」ことを意識する
以下の問題を見てください。
例題1
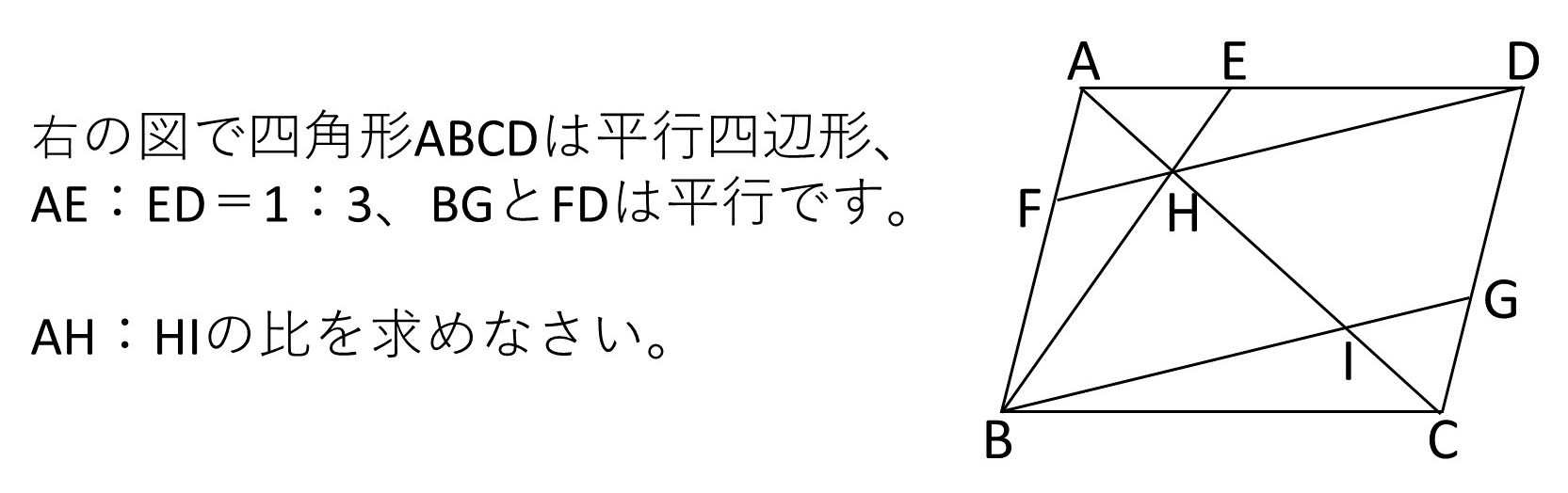
※今回はトレーニングなので、文中の「AH:HIの比を求めなさい。」の部分は一旦置いておいてください。
この問題の場合は、
最初に与えられる図:平行四辺形ABCD、点E
追加で引かれた線:AC、BE、DF、BG
となります。
では、平行四辺形ABCDが描かれた状態から問題の図が完成するまでには、どのような手順で描いていけばよいでしょうか?
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

