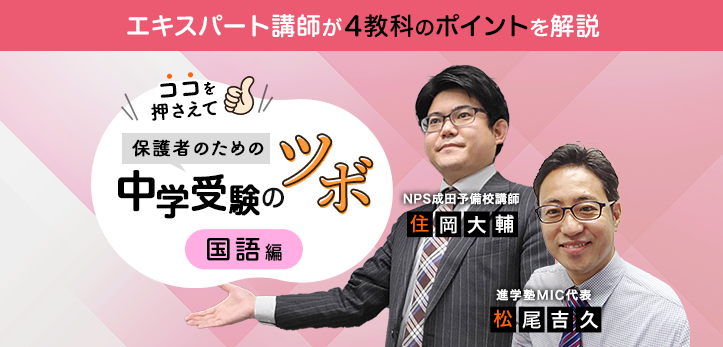
【小4国語/接続語】代表的な8つの接続語と、その働き|中学受験のツボ[国語編]
専門家・プロ
2022年12月05日
松尾吉久
2
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 国語編 は松尾吉久先生、住岡大輔先生、茂山起龍先生が担当します。
- 国語以外の3教科はこちら -
こんにちは、松尾です。
今回は「接続語」についてお伝えします。
接続語は中学入試の国語で必ずと言っていいほど出題されるため、得点力アップを目指すうえでは対策が欠かせません。文や語を一定の関係で結びつける接続語は、文章を理解するうえでも重要な意味をもつので、しっかりと押さえていきましょう。
Contents
接続語の働きと種類を理解しよう
接続語の問題を解くとなると、空欄の前後を読んだけでなんとなくの感覚で答えてしまい、間違えてしまう子は少なくありません。ただし接続語の働きと種類を理解し、「どのように考えるべきか」を身に着けることができれば高い確率で正解できるようになります。
4年生の段階では、まずは代表的な接続語について、どのような働きがあり、どのような言葉があるか、を理解することが大切です。ちなみに「順接」「逆接」といった言葉を覚える必要はありませんが、意味がわかると接続語の働きを理解する際の手助けとなるでしょう。
では、4年生の段階で覚えたほうが良い接続語を、それぞれの例文と共に8つ紹介します。
1、順接(だから)
順接の接続語は、接続語の前が「原因・理由」、後ろが「結果」となるときに使われます。
例:寝坊した。だから、学校に遅刻した。
2、説明・補足(なぜなら)
説明・補足の接続語は、
2
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

