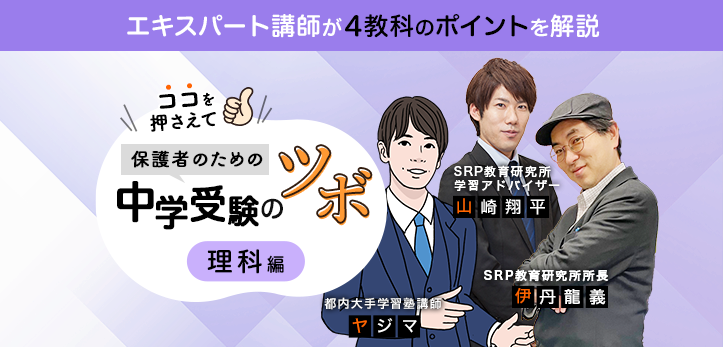
【小6理科/地学】柱状図をもとに、地層のつながりを考えよう|中学受験のツボ[理科編]
専門家・プロ
2022年12月22日
伊丹龍義
1
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 理科編 は伊丹龍義先生、山崎翔平先生が担当します。
- 理科以外の3教科はこちら -
こんにちは、伊丹です。
今回は、ふたつの地点の「地層の傾きを調べる問題」について、その解き方を紹介します。
地面の下の地層がどのようになっているかを図で表したものを「柱状図」といいますが、特定の地層に注目して、2地点の柱状図を比べることで地層が傾いているかを判断できます。
地層の傾きについての問題は昔から出題されている“定番の問題”ですが、正答率は依然として低く、いまでも中学入試での出題頻度が高いです。ただの暗記では太刀打ちできないため、これからお伝えする内容をもとにしっかりと理解を深めていきましょう。
かぎ層とは?
まずは「かぎ層」について復習しましょう。
問題:
凝灰(ぎょうかい)岩が、「かぎ層」として使われることが多いのはなぜ?
離れた場所の地層のつながりを考えるとき、その“かぎ”として注目される地層を「かぎ層」といいます。
まず、モノが積もってできる堆積(たいせき)岩にはいくつか種類があります。凝灰岩のほかに、土や岩が積み重なってできた「れき岩・砂岩・泥岩」、生物の殻などが積み重なってできた
1
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

