
【小6理科/滑車と輪軸】定滑車と動滑車。2つの滑車の使いみち|中学受験のツボ[理科編]
専門家・プロ
2022年8月04日
伊丹龍義
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 理科編 は伊丹龍義先生、山崎翔平先生が担当します。
- 理科以外の3教科はこちら -
こんにちは、伊丹です。今回は小6理科の単元から、滑車と輪軸について扱います。
Contents [hide]
- 事前にチェックしたいポイント
- 定滑車と動滑車の違い
- 解答例
- 保護者向け(実は)
- 内容チェックポイント(1)
- 動滑車の弱点
- 解答例
- 保護者向け(実は)
- 内容チェックポイント(2)
- 輪軸
- まとめ
事前にチェックしたいポイント
定滑車と動滑車の違い
問題:定滑車と動滑車は、それぞれ何をする道具?
滑車とは簡単にいうと、わっかに「ひも」などをひっかけて回す道具ですが、中学受験では大きく「定滑車」と「動滑車」に分けられます。
定滑車は文字通り「固定」されている滑車で、ひもを引っ張っても滑車自体は動かないのに対し、動滑車は滑車自体が固定されていない「動く」滑車です。
■定滑車
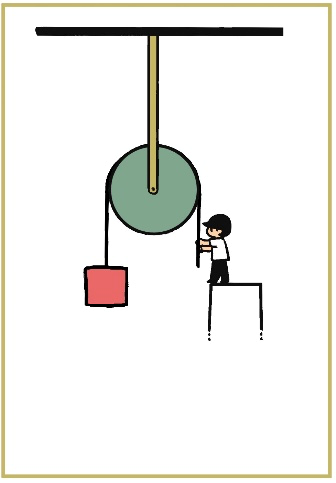
■動滑車
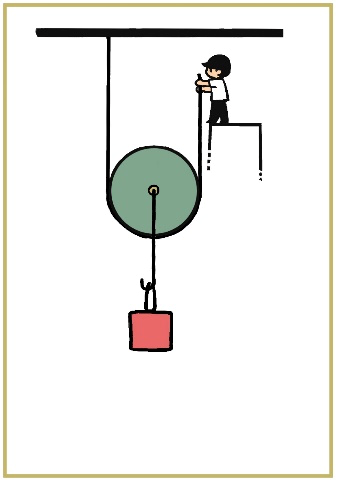
定滑車は「荷物」と「人がひっぱるひも」が直接つながっているので、もし30kgの荷物を持ちあげたい場合、30kgの力でひっぱる必要があり、楽ができる道具ではありません。
しかし、この絵のように定滑車を使うと、物を持ち上げるときに、手で抱えるときのような上向きの力ではなく、下向きの力を加えて持ち上げることができるようになります。つまり、定滑車は力の向きを変えることができる道具なのです。
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

