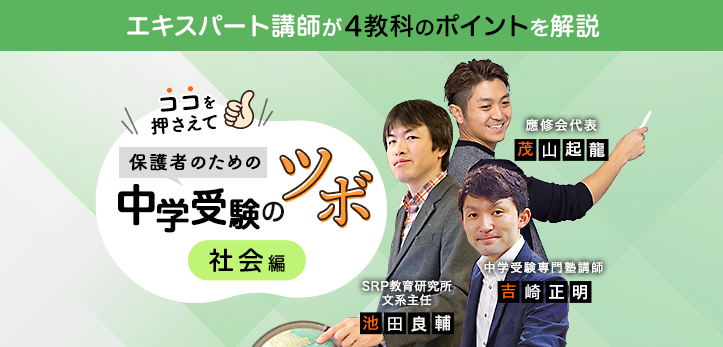
【小6社会/地理】工業地帯の名前の由来 ふたつの地名を合わせよう|中学受験のツボ[社会編]
専門家・プロ
2022年9月26日
池田良輔
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 社会編 は吉崎正明先生、池田良輔先生、茂山起龍先生が担当します。
- 社会以外の3教科はこちら -
前回の記事「工場の分布図を攻略する」では、地理攻略のポイントのひとつとして、工場の分布図を考えました。
今回は、工業地帯の名前の由来に注目します。ポイントは「ふたつの地名を合わせる」です。
覚えるのに困っているお子さんにはきっと助けになるはずです。ぜひ活用してください。
「工業地帯」と「工業地域」
まずは「工業地帯」と「工業地域」の違いからです。
このふたつ、どちらも似た言葉ですよね。
なんで違うのかには、さまざまな説があるんですが、中学受験の社会科では、
・戦前から工業が発展しているのが工業地帯
・戦後に発展したものが工業地域
とされることが多いようです。
工業地帯は、まだ工場で多くの人手を必要としていた戦前に発展しました。
そのため多くの労働者が集まって、人口増加につながった、という側面があります。
このあとに紹介する三大工業地帯は、そのまま首都圏・関西圏・中京圏の三大都市圏の位置と一致します。
ちなみに、この工業地帯の定義に合わないのが、北九州工業地域です。
かつては四大工業地帯として「北九州工業地帯」と呼ばれていましたが、近年は工業生産額の低下などから「工業地域」と呼ばれることがほとんどです。
三大工業地帯の名前の由来
さて三大工業地帯の話をします。
三大工業地帯は生産額順に、中京工業地帯・阪神工業地帯・京浜工業地帯です。
それぞれの名前の由来を知ると、地図上での場所もおのずとわかりますよ。
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

