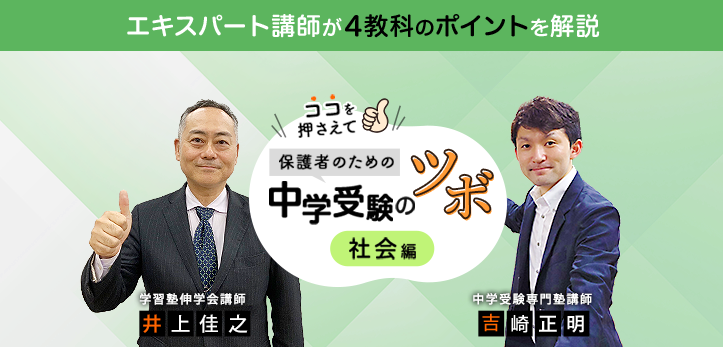
【小6社会/過去問】記述問題と選択問題の解き直し方|中学受験のツボ[社会編]
こんにちは、井上です。
9月から10月のはじめにかけておこなわれる保護者説明会や保護者面談を経て、いよいよ受験校ごとの過去問を解き始める子もいるかと思います。
今回は、社会の入試問題で見られる「記述問題」や「選択問題」について、それぞれの効果的な解き直し方を紹介します。
お子さんにアドバイスする際の参考にしてみてくださいね。
Contents
誤った過去問演習法 ―― “つまみ食い” 禁止!
過去問には、次のような重要な役割があります。
「初見で、制限時間内にチャレンジすればどれくらいできるか」を知り、学習の指針にしたり、合格までの距離を測ったり、受験校選択の基準にしたりする役割
ですから、過去問を購入したあと、ぺらぺらと冊子をめくり、できそうな問題のみを解き、1問でも正解したら合格したかのようにはしゃぐ……、という“つまみ食い”は避けましょう。
過去問入手後は、正しい使い方が決まるまでは「保管方法」にぜひ気を付けてください。
記述問題の効果的な解き直し方 ――「キーワード」をチェックしよう!
記述問題が毎年きまって出題される学校への対策として、解き直しのコツを紹介します。
まず、記述問題は以下の1~4のパターンに分類できます。お子さんには、パターン別にアドバイスをしてあげてください。
- 定義を書かせる問題
- 比較させながら、複数のものごとを説明させる問題
- 資料の読み取りをさせる問題
- 価値判断を問う問題
いずれのパターンの問題も、模範解答を「カード化」して、丸暗記に努めるような解き直しはあまり効率的ではありません。
時間と労力を使ったとしても、受験校でまったく同じ問題がでることもほぼないでしょう。
そこでおすすめなのが、模範解答のなかに登場する「キーワード」を発見し、問題のタイプごとにその使われ方を確認することです。
1、定義を書かせる問題
(例)「国民主権」の定義
定義:国の政治のあり方を決める力のこと
キーワード……「政治のあり方」「決める力」
これまでテストで直接聞かれることが少なかった「ことば」を「キーワード」として意識できるようになると、さまざまな定義の言葉に応用できるようになり、意味のある解き直しができます。
2、比較させながら、複数のものごとを説明させる問題
(例)火力発電と水力発電の場所の比較
キーワード……「臨海部」「ダムのある内陸部」
※これらを「対句のかたち」で使う
対句とは、「おじいさんは、山に、柴刈りに、おばあさんは、川に、洗濯に」のように、複数の内容をセットで説明するかたちのこと。
この文であれば、太字の箇所がキーワードです。
対句を使った説明は、国語の記述問題で部分点を確保するときにも大活躍するので、お子さんにぜひアドバイスしてあげてください。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

