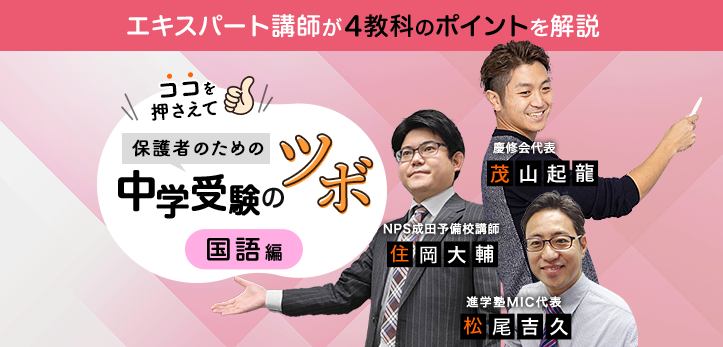
【小4国語/学習のポイント】国語に取り組むときに「できたほうがいいこと」|中学受験のツボ[国語編]
専門家・プロ
2023年5月27日
住岡大輔
1
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説
- 国語以外の3教科はこちら -
こんにちは、NPS成田予備校の住岡です。
以前の記事「国語の『土台固め』で意識したい3つのこと」では国語の勉強に取り組むときの注意点をお伝えしましたが、それに引き続き、今回は「できたほうがいいこと」をお伝えします。
「注意すること」と共に、今回の「できたほうがいいこと」も確認しつつ、お子さんと一緒に国語に取り組んでもらえるとうれしいです。
それではいきましょう!
できたほうがいい3つのこと
国語の勉強で「できたほうがいいこと」は、次の3つです。
- コミュニケーションを円滑に取れる
- 常識や日常的な知識を知っている
- 作業を面倒くさがらない
コミュニケーションを円滑に取れる
国語は“言語”の科目ということもあり、コミュニケーションが円滑に取れると、ほかの受験生と比べて優位に立つことができます。
塾や家庭教師の先生との問答だけでなく、ご家庭でのやりとりも国語力アップには欠かせません。
コミュニケーションと一言で言っても「文字でのやりとり」「会話でのやりとり」などさまざま。
まずはどのやり方でも構いませんが、ひとつでも得意なやり方があると良いですね。4年生であれば「会話でのやりとり」が特に重要でしょう。
1
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

