
【小6理科/物理】凸レンズの作図は「3つのルール」を意識して取り組もう|中学受験のツボ[理科編]
専門家・プロ
2023年9月14日
倉石圭悟
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。
- 理科以外の3教科はこちら -
こんにちは、倉石です。
「凸(とつ)レンズ」が苦手な受験生は少なくありません。
凸レンズだけでなく、物理の分野が苦手な受験生の多くが、そもそも基本的な事柄から理解できていません。
今回は、凸レンズの基本である「作図の仕方」について説明していきます。
作図さえできれば、どこに、どんな像ができるのかも求めることができますよ。
凸レンズの作図の「3つのルール」
凸レンズの作図には、凸レンズの3つの性質を使います。
凸レンズの3つの性質
① レンズの中央を通る光は直進する
② 光軸に平行に入った光は焦点を通る
③ 焦点を通った光は光軸に平行に進む
この「3つのルール」に従って光の道筋を作図していけば、どこに、どんな像ができるかわかります。
物体を置く場所によって、できる像の種類や大きさ、向きも異なります。
ここでポイントとなるのが「焦点距離」です。
焦点距離
焦点距離とは、凸レンズから焦点までの距離のこと。
これを2倍したのが「焦点距離の2倍の位置」となります。
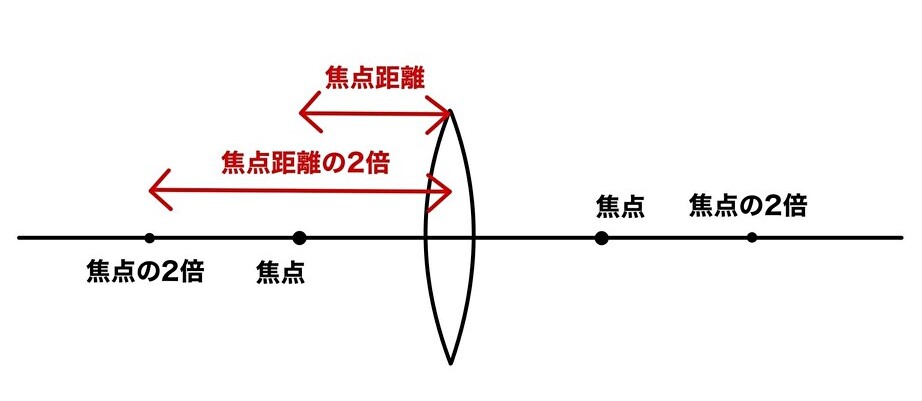
注目したいのは、焦点距離や、焦点距離の2倍の位置と比べてどこに物体を置くか、ということ。
これによって、できる像が異なるのです。
作図の仕方
それでは、像の種類ごとに作図の仕方を説明します。
- 実像ができるとき
- 虚像ができるとき
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

