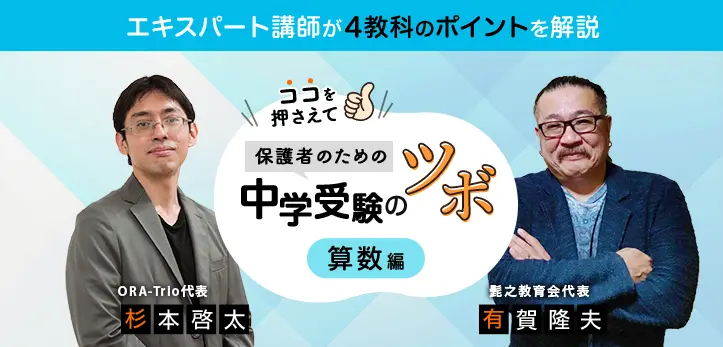
【小6算数/学習のポイント】塾教材と市販教材の利用法|中学受験のツボ[算数編]
髭之教育会代表の有賀です。
夏期講習も終わり、9月もすでに後半になりました。
この時期になると、本屋の参考書コーナーで、真剣な顔で問題集の選定をしている保護者の姿を見かける機会が増えます。
塾のカリキュラムも6年生後半に入り、総合的な内容になります。そのため、個々の子供によって学習すべき内容は異なっていきます。
- 基本的な内容の確認
- 志望校の出題傾向に向けた学習
- 苦手単元の補強
などです。
これらの多種多様な内容に対応するときには、どうしても塾の教材だけでは足りなくなることがありますね。
そのために、保護者の方々は、市販の学習参考書から適切なものがないか、頭を悩ませているのです。
先日も本屋の参考書コーナーで悩んでいる方がいたので、テキストの選別を手伝いました。
今回は、塾教材と市販教材の利用法について説明します。
Contents [hide]
- 基本的には塾の教材を中心に復習する
- 思考力・対応力をつける教材
- まとめ
基本的には塾の教材を中心に復習する
4年生から受験勉強を始めていても、子供たちはすでに2年半もの間、通っている塾のテキストで学習しています。
算数の問題文を読んだ回数は、何百回にも及ぶことでしょう。また、そのテキストを使って学習し、模試も何度も受けてきています。
問題によっては「最初の数文字を読んだだけで、どのパターンの問題かわかる」という状態のものもあるでしょう。
見た瞬間に、どうすれば良いかわかるレベルまで練習したことは大きな力になっています。
お子さんも親御さんも、自信をもってください。
なぜ、基本の確認には塾の教材が良いのか
算数の学力には「処理能力」と「思考力」のふたつの側面があります。
近年は思考力重視の学力観が主流です。しかし、処理能力の土台がなければ、思考力を発揮することはできません。
処理能力とは具体的には、
- 計算能力
- 基本的な問題を速く正確に把握し、解く能力
を指します。
この2の条件を速く正確に把握する訓練は、まずは慣れ親しんだ塾の教材で確認すると効率が良いですね。
なぜなら、「各大手塾には、それぞれの『言葉遣い』がある」からです。
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

