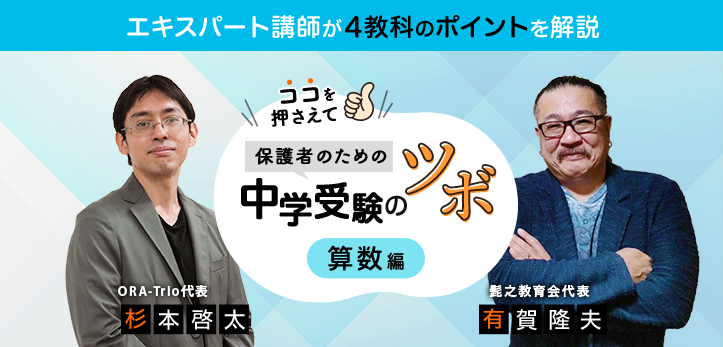
【小6算数/過去問】過去問の効果的な活用法|中学受験のツボ[算数編]
専門家・プロ
2023年11月20日
有賀隆夫
0
保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説
- 算数以外の3教科はこちら -
髭之教育会代表の有賀です。
過去問演習は、志望校に合格するための必須の学習です。残り少ない時間で最大限に得点力を上げるため、効果的な過去問演習をやっていきたいですね。
ぼくが書いた過去の記事でも過去問演習について触れましたが、今回は「より細かい過去問演習のコツ」を説明します。
理想は、実物の過去の入試問題を手に入れること
最初に、最も理想的な方法をお伝えします。
それは「実物の過去の入試問題を手に入れて演習をやること」です。
入手方法は、
- 受験校から直接入手(学校窓口、ホームページ)
- 実物がダウンロードできるサイトから入手
- 通塾している塾の先生に相談
の3つがあります。
第1志望の学校なら、まずは塾に実物の入試問題がないか聞いてみてください。学校によっては、保管されていることもあります。
実際の解答用紙は赤本とは形式が違う
過去の問題を集めた問題集を一般的に「赤本」と呼びます。実際は過去問演習をする際、この赤本の解答用紙をコピーして実施することが多いでしょう。
「実物の解答用紙を縮小したもの」なら、何も問題ありません。拡大の比率も書かれていることが多いので、拡大して使いましょう。
なぜ、実物と同じサイズに拡大するのか?
それは、「考え方を書くスペースによって、書く量が変わる」からです。
0
とじる
お気に入り機能は
会員の方のみご利用できます
会員登録のうえログインすると
お気に入り保存できるようになります。
お気に入りのコンテンツは、
マイページから確認できます

